2024.04.24
教育動画の作り方とは?社内研修やマニュアルに役立つポイントやメリットを紹介

教育動画とは、社内研修や業務マニュアルなどを動画にしたものを指します。
「教育動画の作成に挑戦したいけど、スタートの方法がわからない」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、教育動画のメリットや制作の手順、活用法についてご紹介いたします。
制作プロセスの基本ステップから動画内容の更新や質疑応答への対応策まで、実践的な情報が満載です。
教育動画を導入することで、社内研修や業務マニュアル作成をより理解しやすく効率的なものにできます。
教育動画を活用して、社内教育の質と効率を向上させましょう。
教育動画のメリット

教育動画のメリットは伝わりやすい、内容やレベルの均一化、自由に受講できることなどが挙げられます。
以下で詳しく見ていきましょう。
文字よりも動画の方が伝わりやすい
Forrester ResearchのMcQuivey博士によると、動画は文字よりも約3,000倍の情報を伝えられると言われています。
つまり、1分間の動画で得られる情報量は、約180万語分、ウェブページに換算すると約3,600ページにもなるのです。
動画を用いることで、視覚や聴覚を通じて、より多くの情報を効率的に伝えることが可能になります。
教育分野においても、この特性を生かした動画コンテンツの活用は、学習者への理解を深める上で大きなメリットがあるといえるでしょう。
研修の内容やレベルを均一化できる
教育動画を活用することで、全社員が同じ研修内容を学べ、研修の質の均一化を図ることが可能です。
従来の対面式研修では、講師によって伝えられる情報の質やレベルにばらつきがありましたが、教育動画を使えばこの問題を解決できるでしょう。
同一の教育動画を使用することで、知識やスキルの水準を社員全体で揃えられ、組織全体が均一にスキルアップできます。
また教育動画の活用は、新入社員の教育だけでなく、階層別研修や特定の技能を向上させる研修など、多岐にわたるシチュエーションでの活用が見込めます。
社内の共通理解の促進や業務の標準化にも貢献できるでしょう。
時間・場所を選ばず受講できる
教育動画を活用することで、社員は時間や場所を選ばずに研修を受けられます。
動画なら、社員一人ひとりが自分の空いている時間に、好きな場所で学習を進められます。
自宅での受講も、セキュリティ面の配慮をすれば実現可能です。
教育動画の柔軟性は、社員がより積極的に学習に取り組むことを促し、個々のスキル向上はもちろん、組織全体の能力向上にも繋がります。
教育動画の導入は、忙しい現代人のライフスタイルに合わせた、効率的で効果的な学習方法を提供するでしょう。
また企業側も、研修会場の予約やスケジュール調整をして全員を集める必要がなくなります。
何度も受講できる
教育動画を作成する際には初期費用がかかりますが、内容を何度でも繰り返し視聴できるため、長期的に見るとコストパフォーマンスが非常に高いといえます。
社員は自分の理解に合わせて、わからない部分だけを何度も見返すことが可能です。
もし理解できなかった場合は、すぐに動画を巻き戻して再度確認できるので、自分のペースでしっかりと学習を進められます。
繰り返し視聴が可能な点は教育動画の魅力であり、社員にとっても企業側にとっても大きなメリットです。
一度の投資で繰り返し使える教育ツールは、時間や場所に制約されず、効率的にスキルアップを図れるでしょう。
教育動画の種類

教育動画の種類にはセミナー動画、マニュアル動画が挙げられます。
以下で、それぞれの特徴を見ていきましょう。
セミナー動画
セミナー動画は、これまでは会場に社員を集めて行っていたセミナーや研修を、動画にして提供するものです。
実際のセミナーや研修の様子を録画したものや、アニメーションや図表を用いて編集して制作したものなどがあります。
社員は自分のペースで、いつでもどこでも必要なスキルや知識を学ぶことが可能になります。
代表的なものとして、企業文化の理解や仕事の基本を学ぶ新人社員研修、社員の倫理観や法令遵守の意識を強化するマナー研修やコンプライアンス研修などが挙げられます。
セミナーを動画にすることで、企業側は会場の手配やスケジュール調整をする必要がありません。
セミナー動画は実用性から、多くの企業で広く利用されています。
マニュアル動画
マニュアル動画は、業務の手順や機器の使い方を分かりやすく動画で示したものです。
テキストのマニュアルでは伝えにくい細かな操作や振る舞いも、動画ならば視覚的に理解しやすくなります。
マニュアル動画は、特に重機操作や機械の使用方法、社内で使うソフトウェアの操作、接客の流れなど、具体的なスキルが求められる場面で効果的です。
動画を通じて、正確な操作手順や適切な行動が直接目で見て学べるため、理解が深まり、より実践に近い形で知識を身につけられます。
新しい機器の導入やサービス品質の向上を目指す際に、マニュアル動画は大きな助けとなるでしょう。
従来のテキストベースのマニュアルよりもマニュアル動画は、受講者にとって直感的で分かりやすいものになります。
教育動画の事例紹介

「教育動画の導入を考えているけど、どのようなものがいいんだろう……」とお悩みの人に向けて、今回はYouTubeで観れるものを2つ紹介します。
セミナー動画の事例
この動画は「ヒューマンエラーの仕組みと対策」をテーマにしたセミナー動画になります。
教育動画がいかにテキストベースの学習を超えた理解を促進できるかを示す優れた事例です。
この動画では、従来の文章や図表をアニメーションとナレーションで表現し、複雑な内容を直感的に理解しやすくしています。
アニメーションの視覚的情報と、ナレーションでの詳細な説明により、より効果的に理解を促します。
もしアニメーションの導入が難しい場合でも、講師と受講者が質疑応答を交えながら情報を提供する形式にすると、受講者にとって理解しやすく、親近感を持たせることが可能です。
親近感を持たせることにより、受講者が能動的に内容を吸収し、疑問を解消しながら学び進めることを助けるでしょう。
動画を通じて、ヒューマンエラーのような難解なテーマでも、具体的な例や対策を視覚的、聴覚的に捉えられ、より深い理解へと導くことが可能です。
教育動画の活用は、さまざまな分野での学習に応用が可能であり、効果的な教育手法として今後もさらに発展していくことが期待されます。
マニュアル動画の事例
この動画は、足場の組み立てに必要な「コンステージの取り扱い方」を映像にしたマニュアル動画です。
実際の作業プロセスを詳細に映し出し、ただ手順を説明するだけでなく、安全に作業を進めるための重要な注意点も視聴者に分かりやすく伝えています。
従来のマニュアルが紙やPDF形式で提供されていた時代には、大量の情報を読み解く必要があり、社員にとっては心理的な負担でした。
また、文字だけの説明では、業務の流れや細かな作業内容を正確に伝えることが難しく、誤解を招く可能性もあります。
動画を用いることで、実際の動きや手順を直接見せることが可能になり、より具体的で直感的な理解ができ、作業の品質向上や効率化、安全性の向上に直結します。
また、全員が同じ内容を視聴し、必要な情報を獲得できるため、指導にかかる時間や労力を大幅に削減できるのです。
マニュアル動画は、従来のテキストベースのマニュアルに比べて、受講者に対してより分かりやすく、効果的な情報提供を実現します。
また繰り返し視聴が可能であるため、理解度を自分のペースで深められるというメリットもあります。
教育動画を作成する流れ

ここからは、教育動画を作成する流れを紹介します。
教育動画の作成に関して、より理解を深めましょう。
ターゲットと内容を決める
教育動画制作の出発点は、「誰に」「どんな内容を伝えたいか」を明確にすることから始まります。
動画を通じて達成したい目的や具体的な学習ゴールを設定することが重要です。
以下は、一例です。
● 新入社員に対して接客業の基本用語を教える
● 全社員を対象に新しい勤怠管理システムの使い方を解説する
明確な目標やゴールを定めることが、効果的な教育動画を作成する上での鍵となります。
そのためには、対象となる受講者のニーズや既存の知識レベルを把握し、直面する問題や疑問に対する解決策を提供する内容を組み込むことが必要です。
ターゲットと内容を決めることで、受講者にとって実用的で価値のある教育動画の制作が可能になります。
動画のテーマと本数を決める
教育動画を作成する際には、どのようなテーマで何本の動画を作るかを決めましょう。
長時間の動画は作成も労力がかかり、視聴の際の集中力の維持も難しいものです。
そこで、短めの動画をテーマ別に複数作成することがおすすめです。
例えば、全体を通して30分かかる接客マニュアルを一本の動画にするのではなく、言葉遣いやレジ対応といったテーマに分けて、それぞれ10分程度の動画を作成すると良いでしょう。
短めの動画は、長時間の動画よりも集中力の維持を必要としないため、内容が頭に入ってきやすくなります。
短時間の動画は、教育の目的を効率的に達成するためにも重要です。
伝えたいポイントが複数ある場合は、それに応じて動画の本数を増やす必要があります。
各動画には明確な焦点を当て、テーマに沿ったコンテンツを提供することが、受講者にとっても、制作者にとっても最大の効果をもたらします。
制作前に動画のテーマと本数を決めることで、目的に合った、効率的で理解しやすい教育動画を制作できるでしょう。
自作するか外注するかを決める
教育動画を作成する際、自作するかプロに外注するかの選択は、目指すクオリティや予算、制作にかけられる時間などに基づいて慎重に行いましょう。
自作は、コストを安く抑えられるという大きなメリットがあります。
最近では多種多様な動画編集フリーソフトが利用できるため、基本的な編集は自作でも問題ないでしょう。
ただしクオリティの高い教育動画や、アニメーションなど専門的な技術が必要な内容を取り入れる場合は、外注がおすすめです。
プロの制作会社なら、技術的な面はもちろん、動画制作の豊富な経験から生まれるアイデアや提案も期待でき、最終的な出来栄えの差は明らかです。
教育動画は単に情報を伝えるだけでなく、受講者が理解しやすい動画を目指す必要があります。
そのため動画制作を始める前に、内製と外注のメリットとデメリットをしっかりと比較検討し、目的に最適な選択をすることが重要です。
動画の配信方法を決める
教育動画の配信方法の選択は、内容が社内情報を扱っているか否かで大きく異なります。
一般的な知識やスキルに関する動画であれば、YouTubeの限定公開機能を使うことも可能です。
ただし多くの教育動画は企業の内部情報を含むため、セキュリティを確保した配信方法を選ぶ必要があります。
ここで重要になるのが、閲覧権限の厳格な管理と、視聴者を追跡できるシステムの導入です。
セキュリティが確保された動画配信プラットフォームとして、ULIZAがあります。
ULIZAは企業向けに特化した動画配信プラットフォームで、セキュリティ面での安全性の確保と教育動画の管理・配信が行えます。
高度なアクセス管理機能により、暗号化をした動画の配信や同時視聴人数を制限、ワンタイム(ユニーク)URLの発行などが可能です。
ULIZAを利用することで、安全かつ効率的に教育動画を社内で活用する土台を築けるでしょう。
教育動画の注意点
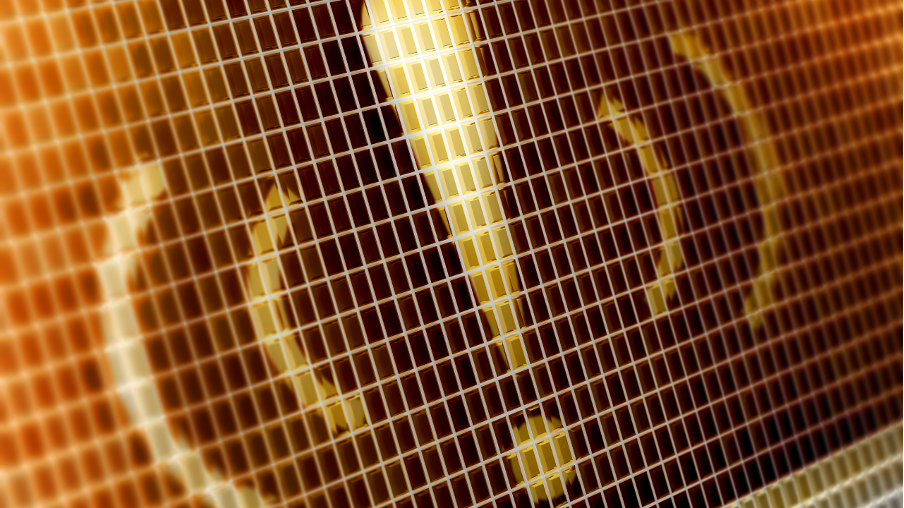
教育動画を制作するにあたり、注意点も理解しましょう。
ここからは、教育動画の注意点を紹介します。
修正や変更に対応しにくい
教育動画を活用する際に注意が必要な点として、内容の修正や変更に対応しにくいことが挙げられます。
特に外注で作成した場合、情報の更新や修正が必要になったときに素早く対処してもらうのが難しいことが多いでしょう。
変更が頻繁に起こり得る情報は、動画ではなくテキストでの管理が有効です。
例えば、定期的な更新が予想される社内規則やツールの使用方法などは、文書やウェブページで提供することで、情報の更新が簡単になります。
このような対策を事前に考えることで、教育動画の長期的な利用を実現し、変更に伴う手間やコストを削減できるでしょう。
質疑応答を共有する
教育動画を使用する際の重要な注意点の一つは、質疑応答の機会をどう確保するかです。
対面での研修では即座に質問を募り回答できますが、動画配信では質疑応答ができません。
動画配信での質疑応答ができないという問題を解決するためには、質問や回答の場をしっかりと設けることが重要です。
質問を集めて回答するフォーラムの設置や、FAQとしてドキュメントを作成し共有するなど、質疑応答の機会を作り出し、学習の質を高める工夫が求められます。
質疑応答のシステムを通じて、双方向のコミュニケーションを可能にし、質疑応答の内容を他の社員と共有することで、全員の理解を深められるでしょう。
まとめ
この記事では、教育動画の効果的な作成と活用法を詳しく紹介しました。
特に重要なのは、ターゲットと内容の明確化、内製か外注かの選択などです。
教育動画の作り方のポイントを押さえることで、教育動画を用いた学習効果を最大化することが可能になるでしょう。
教育動画を作る際には配信方法を決める必要があります。
動画配信プラットフォームULIZAは、セキュリティが保証された環境で教育動画を管理・配信する際に役立つでしょう。














