2023.09.22
ライブ配信とは?配信のメリット・デメリット、配信の流れを解説

ライブ配信は、リアルタイムで音声や映像を配信することや、そのサービスを指します。新型コロナウイルス感染症の影響によるイベントの自粛や、高速インターネット回線の普及などにより、近年ライブ配信の開催・視聴は増えました。イベントの中継から商品やサービスの紹介、雑談などさまざまな用途で利用されており、主要なSNSにもライブ配信機能が追加され、今後も利用者は増加していくでしょう。
企業でもSNSマーケティングなどのほか、会社説明会やセミナー、研修など、ライブ配信を利用する機会が増えています。本記事では、ライブ配信のメリットや注意点、のほか、ライブ配信の方法やサービスの選び方などについてご紹介します。
目次
ライブ配信とはリアルタイムの配信のこと
ライブ配信とは、映像をストリーミング配信用のサーバに送り、リアルタイムに配信することです。配信者が撮影した映像や音声は順次ストリーミング用のデータとしてサーバに送られ、視聴者はサーバにアクセスすることで視聴ができます。撮影と同じタイミングで視聴できるため、コメント機能やチャット機能などを利用し、配信者と視聴者がコミュニケーションをとれる点が特徴です。
ライブ配信アプリやサービスなどを利用すれば、スマートフォンなどでも気軽に利用できるため、個人からビジネスまで、利用は拡大し続けています。
オンデマンド配信との違い
ライブ配信と似たものとして、「オンデマンド配信」があります。制作した動画を配信用サーバにアップし、動画配信サービスや再生ページなどで公開することで、視聴者は見たいタイミングで動画を視聴できます。
ライブ配信もオンデマンド配信も、どちらも動画を配信することですが、大きな違いは「視聴タイミング」「動画の編集」「視聴者とのコミュニケーション」の3点です。
ライブ配信は撮影した映像がそのまま配信されるため、配信のタイミングでなければ視聴できません。また、そのまま配信するという特性上、編集することは不可能です。オンデマンド配信の場合は、事前に制作した動画を配信するため、視聴者は見たいタイミングでアクセスでき、編集も可能です。
ライブ配信はリアルタイムに配信するため、視聴者とコミュニケーションをとることができます。オンデマンド配信は事前に制作した動画を利用しているため、視聴者とその場でコミュニケーションを図ることはできない点も違いです。
オンデマンド配信とは?意味やメリット・デメリット、配信方法を解説
疑似ライブ配信との違い
配信方法には、ライブ配信、オンデマンド配信のほか、収録済み動画を指定時間に配信する「疑似ライブ配信」があります。疑似ライブ配信では、録画した動画を流しますが、チャットなどコミュニケーション部分はリアルタイムで行うことが可能です。
ライブ配信との違いは、「配信時の緊張感・プレッシャー」「動画の編集」です。
ライブ配信は、リアルタイムで配信するため、配信中に予期せぬトラブルが発生する可能性があり、運営側には緊張感やプレッシャーが伴います。一方の疑似ライブ配信は、事前に編集された録画を再生するため、技術的な問題や配信の中断が少なく、こうした緊張感やプレッシャーは少ないといえます。
ライブ配信は、リアルタイムに配信するため編集が不可能ですが、疑似ライブ配信は、録画を配信するため編集が可能です。
ライブ配信の主な活用シーン
ライブ配信は、社内勉強会やイベント、顧客向けのセミナーなど多くのシーンで活用されています。主な活用シーンを見てみましょう。
社内教育や社内イベント
ライブ配信は、社内教育や社内イベントなどの社内向けに活用されることがよくあります。ライブ配信にすることで、情報共有が迅速に行えるほか、出張交通費などのコスト削減につながることがメリットです。
特に周年行事や社内表彰などの社内イベントは、リアルタイムならではの臨場感や一体感を感じられるライブ配信に適しており、会場とライブ配信が併用されることも増えています。
このような社内向けのライブ配信は社外向けに比べると気軽に始められるため、自社で最初に取り組む動画コンテンツとしておすすめです。
顧客向けセミナー
見込み顧客やサービス利用者向けのセミナーでも、ライブ配信が活用できます。会員や取引先など視聴者を限定した配信を行う場合は、セキュリティ機能が備わったライブ配信サービスを選ぶことがポイントです。また、多くの視聴者が見込まれる場合は、安定して配信が行えるかどうか、通信インフラを確認しておきましょう。
採用説明会
ライブ配信による採用説明会も、ライブ配信の活用例のひとつです。企業側には運用の手間やコストが減るメリットがあり、求職者側には移動時間や交通費を気にせずに気軽に参加できるメリットがあります。ライブ配信での採用説明会は、オンライン面接と併せて行われることが多く、新しい採用のあり方として注目されています。
株主総会
株主総会をライブ配信で行う企業も増えています。株主総会の場合は、リアル会場で開催しつつライブ配信を行うことが一般的です。ライブ配信を取り入れることで、国内外問わず、遠方の株主が参加しやすくなるというメリットがあります。
株主総会をライブ配信する場合は、映像と音声をわかりやすく届けるほか、株主の顔が映らないなどプライバシーに配慮が必要なため、専門スタッフに委託して開催するケースが大半です。
ライブ配信のメリット

配信者・視聴者ともに利用が拡大しているライブ配信ですが、実際どのようなメリットがあるのでしょうか。ライブ配信の具体的なメリットをご紹介します。
リアルタイムのコミュニケーションができる
リアルタイムのコミュニケーションは、ライブ配信の最大のメリットです。視聴者が質問したりリアクションしたりすることで、憧れの芸能人や有名なインフルエンサーと交流することもできます。何が起きるかわからない臨場感も、ライブ配信ならではのおもしろさでしょう。配信者も視聴者の反応がダイレクトにわかり、関係構築がしやすくなります。
制作のハードルが低い
動画コンテンツを配信したくても、編集する機材や技術がなく、二の足を踏む人は多いでしょう。ライブ配信の場合は、撮影した映像や音声をそのまま配信するだけなので、特別な機材や技術は必要ありません。インターネット環境があれば、スマートフォンのみで配信も視聴も可能なため、配信者も視聴者もコストをあまりかけずに手軽に楽しめます。
アーカイブもできる
基本的に撮影した映像をそのまま配信するのがライブ配信ですが、映像をアーカイブしてオンデマンド配信することも可能です。
不適切な発言や映像があった場合などは編集することもでき、ライブ配信のタイミングで参加できなかった視聴者に動画コンテンツを届けることもできます。
ライブ配信のデメリット
ライブ配信には、デメリットもあります。事前に理解してデメリットを最小限に抑えられるよう、注意点を紹介します。
トラブルの可能性がある
ライブ配信では、通信トラブルや機器のトラブルが付き物です。映像が止まったり音が聞こえなくなったり、最悪の場合は配信が停止してしまうかもしれません。配信が長時間止まってしまえば視聴者は離脱しますし、配信者に対する不信感につながる可能性もあるでしょう。
予備のPCやネット回線、トラブル時に映す画像などを準備しておくと安心です。トラブルがあっても慌てず、冷静に対処してください。
入念な準備が必要
撮影した映像をそのまま配信するという特性上、ライブ配信は撮り直しがでません。一般人が雑談をライブ配信するなどであれば、スマートフォンひとつあれば問題ないかもしれませんが、企業が行う場合は入念な準備が必要です。
会場や機材のセッティング、台本の作成や映像と音声の確認など、チェックしておくことが膨大にあり、リハーサルも複数回行うべきでしょう。回数を重ねれば慣れる部分もありますが、スムーズに行うためにはライブ配信のマニュアル作成なども必要です。
さらに、安定したライブ配信のためには、安定した動画配信サービスを利用することも重要。どれを利用するか、しっかり選んでください。
特定の時間にしか見られない
ライブ配信の時間にオンラインでないと視聴できない点は、ライブ配信のデメリットです。多くの人に動画を届けるためには、配信の時間帯を慎重に検討したり、告知に力を入れたりしなければなりません。
ただし、ライブ配信の動画コンテンツはアーカイブとしてオンデマンド配信することも可能です。あえてライブ配信のみとしてプレミア感を出すか、後からも見られるようにアーカイブとするか検討しましょう。
ライブ配信に必要な機材・設備とスタッフ
企業がライブ配信を行うにあたっては、配信する動画のクオリティに見合った機材・設備とスタッフが必要です。それぞれ詳しく見ていきましょう。
機材・設備
ライブ配信を行う場合は、以下のような機材・設備が必要です。自社でそろえるのが難しい場合はレンタルすることも可能です。
・配信用PC
配信中に映像を取り込みつつデータを送信し続ける配信用PCが必要です。PCのスペックが不十分だと、映像が遅れたり停止したりする可能性もあります。求められるスペックを把握して準備しておきましょう。また、トラブルに備えて予備のPCも用意しておくと安心です。
・カメラ・三脚
画角や明るさが調整できるビデオカメラやデジタルカメラを用意します。複数のカメラを用意し、状況に応じて切り替えられるようにしておくと、より臨場感のある映像を配信できます。また、カメラをしっかり固定するために、三脚も用意しておきましょう。
・マイク
マイクは、登壇者の声をしっかり拾うためにあると便利でしょう。登壇者が複数いるパネルディスカッションのような場合は、1人につき1本のマイクを用意するのがおすすめです。
・照明
人物に光を当てないと暗く映ってしまうため、照明も用意することをおすすめします。会場の広さに応じて、十分な明るさの照明を選びましょう。
・映像キャプチャデバイス
映像キャプチャデバイスは、カメラで撮影した映像をPCに取り込むためのデバイスです。カメラの種類によっては、直接PCに映像を送れないため、映像キャプチャデバイスが必要になる場合があります。
・音声ミキサー
音声ミキサーは、入力された音のバランスを調整し、聞き取りやすい音を作るための音響機器です。対談など2人以上の登壇者がいる場合は、音声ミキサーの準備を検討するとよいでしょう。
・インターネット環境
ライブ配信では安定したインターネット環境が必要です。ライブ配信をするなら、有線での接続がおすすめです。無線回線よりも安定性が期待できます。
スタッフ
ライブ配信の規模によって必要なスタッフの数は変わりますが、ライブ配信には主に以下のような役割を担うスタッフがいます。
・ディレクター
ディレクターは、配信コンテンツの企画・構成から環境整備、各種調整まですべてを行う総責任者です。ライブ配信の全般を統括する重要な役割を果たします。
・MC
配信するイベントの司会進行を務めるのがMCです。時間配分を意識しながら視聴者とのコミュニケーションを取り入れるなど、臨機応変にプログラムを進行する役割があります。
・カメラマン
カメラマンは、配信の撮影を担当します。進行に合わせて最適なアングルを選ぶ技術が必要です。必要な人数は、設置するカメラの数によって異なります。
・ビデオエンジニア
ビデオエンジニアは、機材の設営や配信を担当するIT技術者です。映像システムの構築や機材の動作確認のほか、配信当日のオペレーションなどを担当します。
・オペレーター
BGMや効果音の再生、テロップの作成、画面の切り替えなどを担当するのがオペレーターです。ビデオエンジニアが兼務する場合もあります。
ライブ配信を行う流れ

特に編集技術も機材も必要なく、手軽に始められることが魅力のライブ配信。しかし、より良い動画コンテンツを配信しようと考えれば、事前の準備が重要です。ここからは、実際にライブ配信を行う流れを紹介します。
1. ライブ配信を企画する
まずはターゲットに合わせたコンテンツ内容など、ライブ配信の企画を立てましょう。ターゲットする視聴者層や内容によって集客できる時間帯は異なりますから、配信日時も検討してください。例えばセミナーの場合、勤務時間を避けた平日の20~22時、土・日曜の10~12時、14~16時に参加しやすいとされています。
ライブ配信視聴者数や動画を見たユーザーのWebサイト流入数など、何をライブ配信の成果とするか、指標を決めておくことも重要です。
2. コンテンツ内容に応じて準備する
企画を立てたら、カメラやマイクといった撮影・配信機材、演出用の小物、BGMの用意・検討など、ライブ配信の準備をします。台本も制作し、万全を期すなら絵コンテも準備すると確実です。コンテンツ内容や演出によっては、スライドを用意する必要もあるでしょう。また、ライブ配信の開催に必要な人員も確保しておきます。
インターネット回線の速度の確認や、電源の確保も重要です。配信場所にない場合は臨時で用意することになりますから、早めに手配してください。
3. ライブ配信の告知を行う
基本的には配信のタイミングでしか視聴できないライブ配信ですから、告知は重要です。ライブ配信の1週間前、前日、1時間前、配信中など、タイミングを考えて複数回の告知を行いましょう。
配信のターゲットに合わせて、複数のSNSを利用すると効果的です。画像を使った告知を使う場合は、告知用画像の制作も必要です。
4. リハーサルを行う
ライブ配信は撮り直しができませんから、リハーサルを行うことも大切です。ライブ配信を行う会場のレイアウトに合わせて、実際に機材をセッティングして台本どおりにリハーサルを行います。
映像や音声が出ないなどのトラブルがあれば機材やつなぎ方を見直し、結果に応じで台本も修正します。
5. ライブ配信を実施する
当日はこれまで準備したことを確認しながら、ライブ配信を行います。直前の告知もお忘れなく。
回線や機材のトラブルに備えて、PCやネット回線などを複数準備しておくと安心です。「しばらくお待ちください」などのテロップも用意しておきましょう。
ライブ配信サービスを選ぶポイント
ライブ配信を行う場合、配信用のサービスやアプリを開発することもできますが、開発費用やその後の運用コストは決して安くはありません。動画配信のビジネスを行うのでなければ、ライブ配信サービスの利用をおすすめします。
ライブ配信には誰でも簡単に配信できるような17LIVEのようなサービスや、法人向け動画配信サービスなどさまざまなサービスがあります。多数あるため、どれを選ぶべきか迷ってしまうかもしれません。ここでは、ライブ配信ができるサービスを選ぶポイントをご紹介します。
ユーザー数(ダウンロード数)
視聴者数がユーザー数を超えることはありませんから、ライブ配信サービスを選ぶ上でユーザー数(ダウンロード数)は重要です。100万ユーザー(ダウンロード)以上を目安として、ある程度多いアプリやサービスを選ぶといいでしょう。配信ジャンルが特化されたタイプなら、もっと少なくても問題ありません。
配信ジャンルと利用者のニーズ
ライブ配信サービス内でどのような配信のジャンルが多いのか、事前に確認しておいてください。行うライブ配信のジャンルと、ライブ配信サービスでよく配信されているジャンルが違っていれば、視聴者は集まりにくくなるでしょう。中には、配信ジャンルが特定されている特化型のライブ配信サービスもあります。
画質と通信速度
ライブ配信サービス自体の画質や通信速度は要チェックです。画質が悪かったり、通信が途切れたりすれば、視聴者が離脱してしまいます。ライブ配信サービスの提供する画質や通信速度の情報のほか、口コミなども確認しましょう。
管理体制
ライブ配信サービスの管理体制も事前にチェックしておくといいでしょう。監視体制があるか、問題が発生したときどのような措置をとってくれるかなどは確認しておくと安心です。
マネタイズ
マネタイズの機能があるかどうかも、ライブ配信サービスを選ぶポイントとなります。ライブ配信で収益化を望まない場合は必要ありませんが、盛り上がればライブ配信でお金を稼ぐことができます。「投げ銭」機能や、配信した時間分に応じた時給制機能などがありますが、企業が利用する場合は、ライブ配信の視聴チケットの事前販売や、ライブ配信のアーカイブ動画の販売などが考えられるでしょう。
【2026年版】動画配信で収益化するには?条件や戦略・活用方法を徹底解説
事前にしっかり準備して効果的にライブ配信しよう
ライブ配信はコロナ禍をきっかけに、配信者も視聴者も増加を続けています。それだけに、ライブ配信ができるサービスは無数にありますから、利用する場合はライブ配信の目的を考えて慎重に選んでください。
手軽に始められるといっても、クオリティを求めれば検討することは膨大にあります。しっかり事前の準備を行って、効果的なライブ配信を行いましょう。
動画配信サービス「ULIZA(ウリザ)」は、日本国内で開発されて10年以上の利用実績や同時視聴者数が10万人以上のライブ配信の実績がある動画配信サービスです。小規模なライブ配信はもちろん、大規模なライブ配信のほか、擬似ライブ配信も可能です。動画配信をご検討の際は、ぜひお問い合わせください。
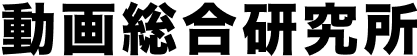
この記事の監修者: 動画総合研究所 編集部
動画総合研究所は、動画配信技術の活用による企業のDX推進をお手伝いするためのメディアです。
動画の収益化・動画制作・ライブ配信・セキュリティ・著作権など、動画配信に関わるのさまざまなコンテンツを提供いたします。





-45.jpg)







