2026.01.22
動画配信をビジネスで活用するには?配信方法や目的別おすすめサービスを紹介

動画配信は、企業のビジネスに新たな可能性をもたらす手段として注目されています。
集客や社内研修、営業支援、オンラインイベント、有料コンテンツの販売など、多様な場面で効果を発揮し、顧客との接点を増やしながら業務の効率化にもつながります。
本記事では、動画配信をビジネスで使うメリットや配信形式の違い、目的に応じたサービスの選び方を含め、担当者が知っておくべき実務情報を整理して紹介します。
目次
企業が動画配信をビジネスに活用するメリット

企業が動画配信を導入する背景には、業務を効率的に進めたいというニーズがあります。
社内研修や情報共有を動画で標準化すれば、時間や場所の制約を受けずに同じ品質の内容を届けられるでしょう。
また、顧客との接点を増やす手段として、オンラインセミナーや商品説明動画、オンラインイベント(ライブ配信)など多彩な場面で効果を発揮します。
動画配信は、組織運営の効率化や売上拡大を支える手段として活用が広がっています。
業務効率化とコスト削減効果
研修やマニュアルを動画で配信すれば、従来の集合研修や対面指導にかかる移動費や会場費を大幅に削減できます。
講師の稼働時間も減らせるため、人件費の圧縮につながるでしょう。
また、製品説明や業務マニュアルを動画化すれば、同じ内容を何度も説明する手間が省け、担当者の対応工数が減ります。
新人や拠点スタッフは好きなタイミングで繰り返し視聴でき、特定の担当者に依存せず均一な教育が実現できる点も大きな魅力です。
動画は一度作成すれば、全国の拠点スタッフや新入社員に対して同じ品質の情報を届けられるため、教育や情報共有のコストを継続的に抑えながら、組織全体の生産性向上にも貢献します。
マーケティング・販売活動の強化
製品紹介動画やオンライン説明会を活用すれば、地理的な制約を超えて全国の見込み客にアプローチできます。
ウェビナーを定期開催すれば、興味を持った潜在顧客と接点を持つ機会が増えるでしょう。
製品紹介動画で、商談前に製品の特徴や使い方を理解してもらえば、営業担当者の説明時間を短縮でき、商談そのものの質が高まります。
さらに、導入事例やお客様の声を動画で紹介すれば、文章や写真だけでは伝わりにくい導入後のイメージが具体的に伝わり、購買意欲を高める効果が期待できます。
結果として、営業活動全体の効率化と売上拡大の両面で大きな成果につながり、持続的な顧客関係の構築にも役立つでしょう。
ビジネス用途で使われる動画配信の種類
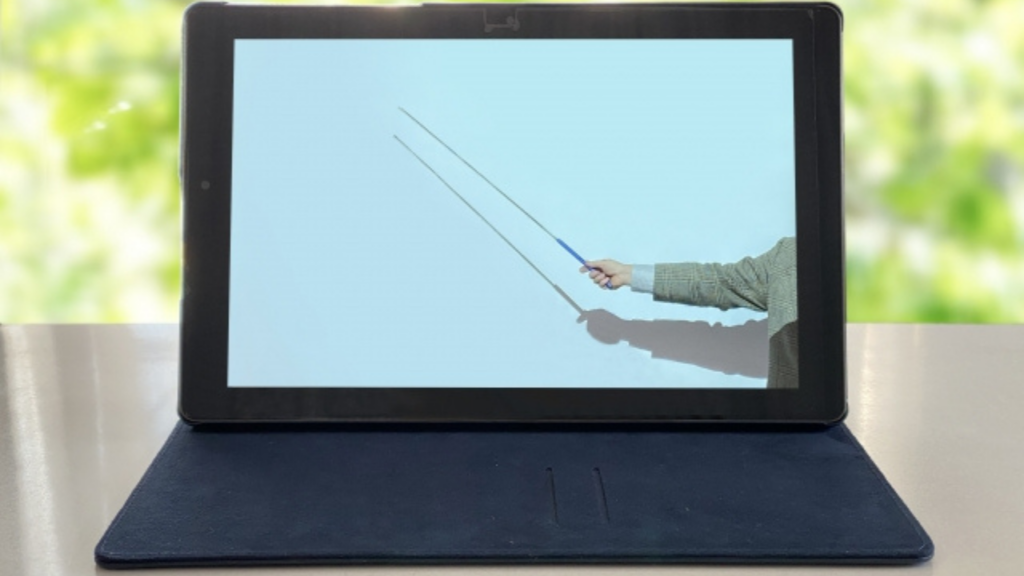
企業が動画を利用する場面は多岐にわたり、目的に応じて配信形式を選ぶことが重要です。
リアルタイムで情報を届けたいウェビナーや社内イベントにはライブ配信が向いており、好きな時間に繰り返し視聴できる研修やマニュアルにはオンデマンド配信が適しています。
配信形式の違いを理解すれば、社内外へ効果的に情報を届けられます。
まずは代表的な配信形式の特徴と利用シーンの把握から始めてみましょう。
ライブ配信(ウェビナー・イベント)
ライブ配信は、リアルタイムで映像と音声を届けられる配信形式であり、視聴者と同じ時間を共有できる臨場感が魅力です。
ウェビナーや製品発表会、株主総会、社内イベントなど、参加者と双方向のやり取りが必要な場面で効果を発揮します。
チャット機能やアンケート機能を使えば、視聴者からの質問にその場で答えたり、リアクションを確認したりできるため、一体感のある体験を生み出せるでしょう。
また、録画データをアーカイブ配信に切り替えれば、当日参加できなかった人にも内容を共有できます。
ただし配信トラブルを避けるため、あらかじめ録画した動画を本番時刻に配信する疑似ライブ配信を選ぶ企業も増えており、目的に応じて配信手法の使い分けをすることが大切です。
オンデマンド配信(研修・マニュアル・講座)
オンデマンド配信は、視聴者が好きな時間に自分のペースで動画を見られる配信形式であり、研修やマニュアル、製品レクチャーに向いています。
社内研修では、全員が同じ日時に集まる必要がなく、各自のスケジュールに合わせて受講できるため、業務への影響を最小限に抑えられるでしょう。
また業務マニュアルを動画化すれば、新人は何度も繰り返し視聴しながら手順を確認でき、理解度を深められます。
有料講座やeラーニングでは、受講者の視聴履歴を記録して進捗管理を行えば、学習状況を把握できます。
また、製品の使い方や技術的な説明を動画にすれば、顧客が必要なときにいつでもアクセスでき、サポート対応の負担軽減にもつながるでしょう。
ビジネスで使用する動画配信サービスの選び方

動画配信サービスを選ぶ際は、自社の目的に合った機能が備わっているかを確認する必要があります。
配信する対象の規模や視聴者の範囲によって、求められるセキュリティレベルや配信容量が変わってくるでしょう。
また、視聴履歴の管理機能やアクセス制限機能など、運用面での利便性も重要な判断材料となります。
初期費用や月額料金、サポート体制も含めて総合的に比較検討すれば、長期的に安心して使えるサービスを見つけられるはずです。
ビジネス配信に求められる基本機能
企業が動画配信サービスを選ぶ際、まず確認すべきは画質の安定性です。
視聴者にストレスを与えない高画質配信ができれば、内容がしっかり伝わるでしょう。
さらに視聴分析(視聴ログ分析)機能があれば、誰がどの動画をどれだけ視聴したかを把握でき、研修の受講状況やコンテンツの効果測定に役立ちます。
アクセス制御機能は、社外秘の情報や特定の部署向け動画を限定公開する際に欠かせません。
ウェビナーやオンラインイベントでは、スライド資料の同時表示やチャット機能、Q&A機能があると、参加者との双方向コミュニケーションがスムーズになります。
また録画データの保存や編集機能、複数デバイスへの対応も、実務で使いやすいサービスを選ぶ重要なポイントです。
セキュリティ・安定性でチェックすべき点
企業の動画配信では、情報漏えいを防ぐセキュリティ対策が欠かせません。
DRM(デジタル著作権管理)や暗号化技術を用いれば、不正ダウンロードやコピーを防げます。
またIP制限やパスワード保護機能があれば、特定の社員や取引先だけに動画を公開でき、機密情報の管理も安心です。
さらに、ウェビナーや社内イベントでは、アクセスが集中しても安定して配信できるサーバー負荷分散の仕組みが重要になります。
配信が途中で途切れたり画質が低下したりすれば、視聴者の満足度が下がり、企業の信頼にも影響するでしょう。
また、視聴期限の設定や視聴回数の制限、ダウンロード禁止設定など、きめ細かなアクセス制御ができるサービスを選べば、運用の柔軟性が高まります。
ビジネスの動画配信を成功させるための運用ポイント

動画配信を導入しても、ただ配信するだけでは十分な効果は得られません。
はっきりした目的設定があれば、視聴者に何を伝えるべきかが定まり、コンテンツ企画の方向性も決まります。
動画の品質や運用体制を管理し、視聴者がストレスなく見られる状態を保つことも欠かせないでしょう。
さらに、継続的に成果を出すには、配信後の分析から改善など、運用体制を整えるのが重要です。
目的に沿ったコンテンツ設計
動画コンテンツを設計する際は、誰に何を伝えるのかを明らかにする必要があります。
社内研修では、新人向けなら基礎から解説し、管理職向けならマネジメント手法を深く掘り下げるなど、対象者のレベルに合わせた構成が求められるでしょう。
ウェビナーでは、冒頭で課題を提示し、解決策を順序立てて説明すれば、視聴者の興味を保ちながら最後まで見てもらえます。
営業資料動画は、製品の特徴や導入メリットを簡潔に伝え、問い合わせへの導線を明らかにするのが大切です。
長すぎる動画は途中離脱を招くため、10分程度に収めるか、チャプター分割して必要な部分だけ視聴できるようにする工夫も効果的です。
撮影・編集のクオリティを高める工夫
企業動画のクオリティは、視聴者の印象を大きく左右します。
画質が粗かったり音声が聞き取りにくかったりすれば、内容が伝わる前に離脱される可能性が高まります。
撮影時は照明を工夫して明るさを確保し、マイクを使ってクリアな音声を収録するのが基本です。
字幕やテロップを入れれば、音声なしでも内容が理解できるため、外出先や移動中の視聴にも対応できます。
構図は画面の中心に話者を配置し背景を整理すれば、見やすくプロフェッショナルな印象になります。
また、企業ロゴやカラー、フォントを統一すれば、ブランドイメージを強化できるでしょう。
最後に編集では不要な間を削り、テンポよく仕上げると、視聴者の集中力を保ちやすくなります。
配信後の分析と改善サイクル
動画配信後は、視聴ログやアンケート結果を分析して改善につなげるのが重要です。
視聴ログから、どの部分で視聴者が離脱したかを把握すれば、内容が長すぎる箇所や分かりにくい説明を見直せるでしょう。
研修動画では、視聴完了率や理解度テストの結果を確認し、効果が低い場合は構成や説明方法を変更します。
ウェビナーでは、参加者アンケートから関心の高いテーマや改善要望を収集し、次回の企画に反映させれば、集客力や満足度が高まるでしょう。
営業資料動画なら、視聴後の問い合わせ数や成約率を追跡すれば、動画の訴求力を測れます。
このように定期的に効果を検証し、PDCAサイクルを回せば、動画配信の成果を継続的に向上させられます。
ビジネス用途の動画配信に強いサービスは

動画配信サービスは多数存在し、それぞれに強みや特徴があります。
社内研修に特化したサービス、ウェビナー開催に強いサービス、有料コンテンツ販売に適したサービスなど、用途によって選ぶべき機能や仕様が異なるでしょう。
機能の充実度、料金体系、サポート体制、セキュリティレベルなど、比較すべきポイントを整理すれば、自社に合ったサービスを見つけやすくなります。
用途別の選定基準を理解してサービスを見極めるのが、成功への第一歩です。
ここでは、企業利用を前提とした動画配信サービスの特徴を整理します。
社内向け(研修・マニュアル)に適したサービスの特徴
社内向けの動画配信サービスを選ぶ際は、特定の社員だけがアクセスできる限定公開機能が欠かせません。
IPアドレス制限やパスワード保護、ユーザー認証により、社外への情報流出を防げるでしょう。
また視聴管理機能があれば、各社員の受講状況や視聴完了率を一覧で確認でき、未視聴者への個別連絡も簡単に行えます。
研修効果を測定するため、理解度テストやアンケートを組み込める機能も重要です。
また、安定した配信品質を保てるサービスであれば、全国の拠点や在宅勤務の社員も快適に視聴できます。
さらに、動画の編集やチャプター分割、資料の同時表示など、学習効果を高める補助機能が充実していれば、研修やマニュアル共有の質が向上するでしょう。
社外向け(ウェビナー・販売)に適したサービスの特徴
社外向けの動画配信サービスでは、決済機能の充実度が重要になります。
クレジットカード決済やサブスクリプション課金、単品販売など、複数の課金形態に対応していれば、ビジネスモデルの幅が広がるでしょう。
さらに視聴権限の管理機能があれば、購入者だけに動画を公開したり、視聴期限を設定したりできます。
ウェビナーでは、参加者が同時にアクセスしても途切れない配信安定性が求められます。
他にも、自社ブランドに合わせてロゴやカラー、デザインをカスタマイズできれば、視聴者に統一感のある印象を与えられるでしょう。
また、申し込みページ作成やメール配信、アンケート機能などマーケティング支援機能が備わっていれば、顧客とのコミュニケーションもスムーズです。
ULIZA・PLAY VIDEO STORESの活用メリット
ULIZAは、社内研修やウェビナー、オンラインイベントなど幅広い用途に対応できるプラットフォームです。
ライブ配信とオンデマンド配信の両方に対応し、視聴分析機能やセキュリティ機能が充実しているため、企業での配信に安心して使えるでしょう。
一方、PLAY VIDEO STORESは動画販売に特化したサービスです。
自社ブランドの配信サイトを簡単に構築でき、サブスクリプション販売や単品販売、PPVチケット販売など多彩な課金形態に対応し、アナリティクス機能も充実しています。
HuluやTVerの開発実績を持つ技術力で、スポーツ配信やレッスン動画、エンタメコンテンツなど、収益化を目指す企業に適しています。
動画配信プラットフォームはそれぞれで特徴や機能が違うため、下記記事を参考にして自社に合うサービスを慎重に検討しましょう。
動画配信プラットフォームとは?特徴や選び方、おすすめサービスを徹底解説!
まとめ
動画配信をビジネスで成功させるには、目的に合った配信形式やサービスを選ぶことが重要です。
ライブかオンデマンドか、社内向けか社外向けかによって、必要な機能やセキュリティレベルが変わります。
自社の課題を明らかにし、視聴管理、アクセス制限、決済など求める機能を整理してからサービスを比較検討しましょう。
企業向けプラットフォームとして、ULIZAやPLAY VIDEO STORESは安心して導入できるサービスです。
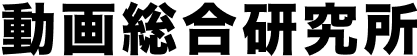
この記事の監修者: 動画総合研究所 編集部
動画総合研究所は、動画配信技術の活用による企業のDX推進をお手伝いするためのメディアです。
動画の収益化・動画制作・ライブ配信・セキュリティ・著作権など、動画配信に関わるのさまざまなコンテンツを提供いたします。













