2023.09.22
動画配信サービスとは?企業が利用する際に知っておきたい種類や特徴

動画配信サービスとは、インターネット回線を通じて動画が見られるサービスです。
スマートフォンや高速回線が普及したこと、コロナ禍で外出自粛が求められたことなどで、その市場は一気に拡大しました。
企業でもオンラインセミナーやオンラインレッスンの配信、社内の研修動画、マニュアル動画の配信など、動画配信サービスを利用する機会は増えています。
市場の拡大に応じて、多種多様な動画配信サービスが誕生しています。
個人利用の場合は、見たいジャンルの充実度や料金などでサービスを選びますが、企業が利用する場合は何を基準にすべきなのでしょうか。
今回は、動画配信サービスの種類や特徴のほか、企業が利用するときのサービスの選び方を紹介します。
市場拡大中の動画配信サービス
動画配信サービスとは、デバイスとインターネット環境があれば、いつでもどこでも視聴が可能な動画の配信サービスです。
VOD(Video On Demand)とも呼ばれ、視聴するユーザーは初期費用なしで安価に利用できるものが多いです。
新型コロナウイルス感染症の拡大で「おうち時間」が増えた結果、動画配信サービスのユーザー数は急増しています。
GEMPartners株式会社が2023年2月に発表した「動画配信(VOD)市場5年間予測(2023-2027年)レポート」によると、2022年の国内の動画配信サービス市場規模は推計値で5,305億円でした。
2027年には、7,487億円に達すると予測されています。
費用面における動画配信サービスの種類と特徴
動画配信サービスは、料金の支払方法で大きく「AVOD」「SVOD」「PPV」の3種類に分けられます。
それぞれの特徴をご紹介しましょう。
AVOD(広告掲載型)
AVOD(Advertising Video On Demand)は、広告掲載型の動画配信サービスを指します。
動画の中で流れる広告の掲載費用で運営されているため、ユーザーは無料で動画視聴が可能です。
ただし、広告を削除できる有料プランが用意されていることも多いです。
企業が利用する際は、動画コンテンツ自体を配信する場合と、広告動画を掲載する場合があるでしょう。配信自体は無料なことが多く、手軽に始められます。
ただし、広告で視聴が中断されることで離脱されるリスクはあるでしょう。
広告動画を掲載する場合も、何度も広告動画が流れてわずらわしく思われたり、視聴回数が増えて費用が高くなったりといったことに注意が必要です。
SVOD(定額制)
SVOD(Subscription Video On Demand)は、サブスクリプション(定額制)の動画配信サービスのことです。
ユーザーは定額の月額料金を支払うことで、動画が好きなだけ視聴できます。
一部、AVODのように広告掲載があるサービスも存在しています。
企業がSVODを利用する場合は、自社で動画配信プラットフォームを構築することが一般的でしょう。
自社に必要な機能を搭載でき、月額料金も自由に決められます。
しかし、構築は決して簡単ではなく、費用も手間も大きいです。
集客も自社で行う必要があり、収益化できるまでは時間がかかるかもしれません。
PPV(都度課金型)
PPVは(Pay Per View)は、都度課金型の動画配信サービスです。
ユーザーが動画を視聴するたびに料金が発生するもので、企業が利用する場合は、動画配信サービスに動画コンテンツを登録し、ユーザーに購入またはレンタルしてもらう方法があります。
PPVには、「EST」と「TVOD」の2つに分かれます。
・EST(購入型)
EST(Electric Sell-Through)は、ユーザーが作品ごとに料金を支払って購入するタイプの動画配信サービスです。
購入した動画はストレージなどに保存する場合と、購入先のサービスの中で無期限視聴できる場合があります。
・TVOD(レンタル型)
TVOD(Transactional Video On Demand)はユーザーが作品ごとに料金を支払って一定期間レンタルするタイプの動画配信サービスです。
ESTとの違いは、視聴できる期間に限りがあることでしょう。
ESTより料金は安価に設定されていますが、一定期間を過ぎれば視聴することはできません。
企業が動画配信サービスを利用して自社の動画やコンテンツを配信する場合、サービス自体の集客効果を利用できる可能があります。
しかし、手数料が高めであることと、同様のジャンルの動画に埋もれてしまうといったデメリットに注意が必要です。
動画配信サービスを利用する?構築する?

市場が拡大を続けていることもあり、昨今は非常に多くの動画配信サービスが存在しています。
企業が動画配信する場合は、何を利用すべきか迷う場合も多いのではないでしょうか。
企業が動画配信を行う場合は、配信に特化した動画配信サービスを利用するか、プラットフォームを構築するかを選ぶ必要があるでしょう。
ビジネス配信に特化したサービスを利用する
企業が手軽に動画配信を行ってみたいという場合は、ビジネス配信に特化したサービスの利用がおすすめです。
初期費用が低めで、データ配信流量やアカウント数など、視聴者数に応じて料金が変わる場合が多く、スモールスタートにぴったりでしょう。
社内の会議や研修動画の共有のほか、外部向けのeラーニングやセミナーの販売、会員向けのライブ配信など、利用シーンはさまざまです。
配信はサーバーに動画コンテンツをアップするだけで、視聴の際はパスワードや視聴コードなどを入力します。
資料をダウンロードできたり、動画コンテンツのコードをウェブサイトに埋め込んだりなど、サービスによってさまざまな機能が用意されています。
初期費用0円、月額7500円~
自社の動画配信プラットフォームを構築する
自社で一から動画配信プラットフォームを構築するのは、数千万~数億円の費用がかかり、時間もかかるので現実的ではありませんが、クラウド型やSaaS型の配信サイト構築サービスを利用することで比較的簡単に作成できます。
デザインにこだわったり、視聴者のデータをマーケティングに活かしたりすることもでき、動画配信をさまざまな形で活用可能です。
自社配信サイト構築サービス「PLAY VIDEO STORES」
動画配信サービスを利用して動画ビジネスを成功させよう
動画配信サービスのユーザーは増え続けており、動画配信サービスの市場も拡大を続けています。
この機に、動画配信サービスを始めてみたいと考える企業も多いでしょう。
動画配信する方法はさまざまで、どれを利用すべきか迷ってしまうかもしれません。
まずは動画配信を行ってみたいという場合は、動画配信サービスを利用してみてはいかがでしょうか
自社ならではの要望が出てきた場合は、動画プラットフォームの構築サービスを利用してみるのもひとつの手です。
動画配信プラットフォーム「ULIZA(ウリザ)」は、日本国内で開発されて10年以上の利用実績がある動画配信プラットフォームです。
動画配信をご検討の際には、ぜひお問い合わせください。
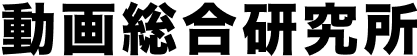
この記事の監修者: 動画総合研究所 編集部
動画総合研究所は、動画配信技術の活用による企業のDX推進をお手伝いするためのメディアです。
動画の収益化・動画制作・ライブ配信・セキュリティ・著作権など、動画配信に関わるのさまざまなコンテンツを提供いたします。






-45.jpg)








