2026.02.13
教育現場で動画配信を活用する方法は?運用のコツやメリット・デメリットを解説

学校や塾、企業研修の現場で、動画配信を導入する組織が急速に増えています。
遠隔地でも質の高い教育を届けられる、繰り返し視聴で理解を深められるなど、利点は豊富です。
一方で、どのサービス(システム)を選ぶべきか、運用をどう進めるべきかといった悩みを抱える担当者も少なくありません。
本記事では、教育現場における動画配信の導入目的、メリット・デメリット、選び方、運用のポイントまで解説します。
目次
教育現場で動画配信が求められる背景

遠隔地や多忙な学習者にも柔軟に教育を届けられる動画配信は、ICT技術の進化とともに急速に普及が進んでいます。
従来の対面授業から場所や時間を選ばない学習形態へと大きく変化する中、繰り返し視聴できる動画コンテンツは、学習効率を向上させる手段として注目を集めました。
本章では、近年の教育市場と、学習スタイル変革の中で果たす役割について整理します。
学習スタイルの多様化とオンライン化の加速
教育現場では学習スタイルの多様化が急速に進んでおり、従来の対面授業だけでは学習者のニーズに応えられない状況が増えてきています。
そこで、オンライン授業、対面とオンラインを組み合わせたハイブリッド授業、学習者のペースに合わせた個別学習など、多様な形態が選択肢として広がりました。
さらにネットワーク環境やデバイスの発達により、いつでもどこでも学べる環境が整ったことで、動画配信が教育手法の中核を担うようになっています。
特に社会人教育や企業研修では、忙しい学習者がスキマ時間に効率よく学べる仕組みが求められ、繰り返し視聴できる動画コンテンツへの需要が高まっている状況です。
教育の質向上と効率化を求めるニーズ
教育現場では、限られた人的リソースの中で質の高い教育を効率的に届けるのが大きな課題となっています。
動画配信を取り入れると、講師は同じ内容を何度も繰り返し教える必要がなくなり、業務負担の軽減につながるでしょう。
また、学習者にとっては理解できるまで繰り返し視聴できるため、自分のペースで確実に知識を習得できる点が魅力となっています。
さらに、全員が同じ動画教材で学ぶことで、講師による説明のばらつきがなくなり、教育の質を均一に保てるのも大きな利点です。
教育コストを抑えながら多くの学習者に画一的な教育を届けられる仕組みとして、動画配信は教育効率化の有力な手段となっています。
動画配信を教育に取り入れるメリットとデメリット

教育現場への動画配信導入には、学習効率向上や教育の均一化といった大きな利点がある一方で、運用面での課題や初期投資への懸念も存在します。
導入を成功させるには、メリットとデメリットの両面を正しく理解し、自組織の教育方針や予算規模に合った判断を下す必要があるでしょう。
本章では、動画配信がもたらす具体的な効果と、導入時に注意すべきポイントを整理していきます。
教育向け動画配信のメリット
教育向け動画配信には、従来の対面授業では実現しにくかった複数の利点があります。
まず、学習者が自分のペースで繰り返し視聴できるため、理解が不十分な箇所を何度も確認でき、知識の定着が促進されるでしょう。
また、病気や所用で欠席した学習者も後から同じ内容を学べるため、学習機会の公平性が保たれます。
講師にとっても、同じ内容を何度も説明する負担が軽減され、質問対応や個別指導に時間を割けるようになる点が利点です。
さらに、全員が同一の動画教材で学ぶことで、講師による説明のばらつきがなくなり、組織全体で教育の質を均一に保てる効果も期待できます。
教育向け動画配信のデメリット・課題点
教育向け動画配信の導入には、いくつかの課題も存在します。
まず、撮影用の機材やシステムの準備に初期投資が必要となり、予算確保が難しい組織もあるでしょう。
また、動画教材の作成には、講師が撮影や編集作業に慣れるまで時間がかかり、通常業務に加えて新たな負担が生じる可能性があります。
学習者の視聴状況を把握し、未視聴者への対応を行う管理体制の構築も欠かせません。
さらに、通信環境が整っていない場所では動画が再生できず、学習者によって視聴環境に格差が生まれる懸念もあるでしょう。
以上の課題を導入前に十分に検討し、対策を講じておく必要があります。
教育で使われる動画配信の種類
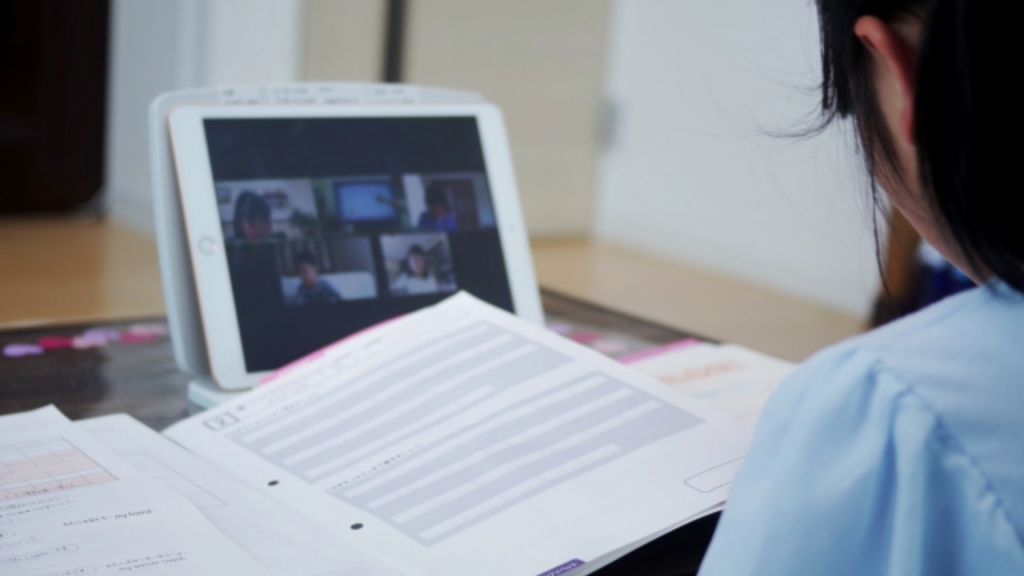
教育現場で利用される動画配信には、複数の配信形態が存在します。
リアルタイムで授業を届けるライブ配信、録画した動画をいつでも視聴できるオンデマンド配信など、それぞれに異なる特性があります。
教育効果を高めるには、学習内容や対象者の状況に応じて、配信方法を使い分けるのが重要です。
本章では、代表的な配信形態を整理し、選択のポイントを解説していきます。
ライブ型(オンライン授業・双方向授業)
ライブ型の動画配信は、リアルタイムで授業を配信し、講師と学習者が同時に参加する形式です。
双方向のコミュニケーションが可能なため、学習者からの質問にその場で回答でき、疑問をすぐに解消できる点が大きな魅力となっています。
また、参加者同士でディスカッションを行ったり、グループワークを実施したりと、対面授業に近い学習体験を実現できるでしょう。
講師も学習者の反応をリアルタイムで確認できるため、理解度に応じて説明を調整しやすくなります。
このようにライブ型配信は、ディスカッションが重要な科目や、議論を通じて理解を深める授業に向いており、臨場感を保ちながら遠隔地の学習者にも質の高い教育を届けられます。
オンデマンド型(講義録画・個別学習・課題動画)
オンデマンド型の動画配信は、録画した授業や教材をいつでも好きな時間に視聴できる形式です。
学習者が自分のペースで繰り返し視聴できるため、理解度に応じて学習スピードを調整でき、苦手な箇所を重点的に復習できます。
また、通勤時間や休憩時間など、スキマ時間を利用した学習にも向いており、忙しい社会人や多様な生活リズムを持つ学習者に適しているでしょう。
学習効率を高めるには、動画を10分程度の短い単位に分割し、集中力を維持しやすくする工夫が有効です。
さらに、視聴後に確認テストを設置すると、理解度を自己チェックでき、知識の定着を促進できます。
オンデマンド型配信は、講義録画や反復練習が必要な技術習得などに向いた配信形態といえるでしょう。
教育現場における動画配信コンテンツの設計と運用のコツ

教育動画を効果的に利用するには、コンテンツの質と運用体制の両面に配慮が必要です。
学習者が集中を切らさずに視聴できる構成、撮影時の注意点、理解を促す学習設計など、押さえるべきポイントは多岐にわたるでしょう。
また、継続的に動画を制作・更新していくには、担当者の負担を軽減する仕組みづくりも欠かせません。
本章では、教育動画の質を高める実践的なコツや運用方法の工夫を解説していきます。
わかりやすい動画を作るための構成設計
わかりやすい教育動画を作るには、体系的な構成設計が欠かせません。
まず導入部分で学習の目的やゴールを伝え、学習者の目標をはっきりさせるのが重要です。
次に本編で、核となる知識やスキルを丁寧に説明し、具体例やデモンストレーションを交えながら理解を促進しましょう。
可能であれば演習パートを設け、学んだ内容を実践する機会を用意すると、知識の定着を図れます。
最後に振り返りの時間を設け、重要ポイントを再確認させると学習効果が高まるでしょう。
また、動画を5〜10分程度の短い単位に分割し、テロップで要点をわかりやすく記載すると、学習者の集中力を維持しやすくなります。
撮影・編集で押さえるべき基礎
品質の高い教育動画を作るには、撮影と編集の基礎をしっかり押さえる必要があります。
まず音声は、クリアに聞き取れるよう外付けマイクを使用し、周囲の雑音が入らない環境で収録しましょう。
照明は動画の見やすさを大きく左右するため、講師の顔や資料が暗くならないよう十分な光量を確保するのが大切です。
教材やスライドを見せる際は、画面共有機能を使い、文字が読みやすいサイズで表示されているか確認しましょう。
編集では、複数のアングルから撮影した映像を切り替えたり、重要な箇所にテロップを入れたりすると、視聴者を飽きさせない工夫ができます。
また、スマートフォンでの視聴も考慮し、画面サイズに応じた見やすさを検証しておくことも重要です。
学習効果を高める運用方法
動画配信を導入しただけでは、学習効果は十分に高まりません。
視聴状況を管理する仕組みを整え、未視聴者や視聴途中で離脱した学習者へのフォローを行うことが大切です。
動画視聴後は課題やレポートを課すことで、学んだ知識を実践に結びつけられるでしょう。
また、確認テストを設置すれば、理解度を客観的に把握でき、苦手分野の洗い出しにもつながります。
さらに効果的なのは、動画による事前学習とグループディスカッションを組み合わせる反転学習の導入です。
基礎知識は動画で学び、対面授業では議論や実践に時間を使えるため、学習の質が向上します。
運用方法を工夫すると、動画配信は単なる知識伝達の手段を超え、深い学びを促す教育ツールとなるでしょう。
教育用途の動画配信に適したサービスの選び方

教育現場で動画配信を導入する際には、必要な機能を見極めてサービスを選ぶことが重要です。
教育用途のサービスでは、視聴管理や視聴分析、セキュリティ対策など、教育に特化した機能が求められるでしょう。
本章では、教育向け動画配信サービスの選定ポイントと、実践的な利用例を紹介していきます。
教育用途で求められる動画配信システムの必須要件
教育向けの動画配信システムには、学習効果を高め安全に運用するための複数の必須要件があります。
まずアクセス制限機能により、特定の学習者だけが視聴できる環境を整え、教材の不正利用を防ぐ必要があります。
また、視聴ログの記録は、学習者の進捗状況や理解度を把握するために欠かせません。
教材管理機能では、コンテンツを科目や単元ごとに整理し、学習者が必要な動画をすぐに見つけられる仕組みが求められます。
また、大人数が同時にアクセスしても遅延なく視聴できる安定した配信環境も重要となります。
さらに、個別学習に対応するため、視聴速度の変更や再生位置の記録、テスト機能の搭載なども必要です。
学校・塾・企業研修など用途別の配信活用例
教育現場では、それぞれの目的に応じて動画配信が役立ちます。
学校教育では、オンライン授業による遠隔地への教育機会の拡大や、予習復習用の教材として生徒の自主学習を促進できます。
学習塾では、通学が難しい地域の生徒にも授業を届けられ、市場を全国に広げられるでしょう。
また、人気講師の授業を録画して繰り返し配信すると、講師の負担軽減と質の高い教育の両立が可能です。
企業研修では、全国の拠点に同じ内容を配信でき、コンプライアンス研修や新入社員教育を効率化できます。
社員は空き時間に受講でき、管理者は視聴状況を把握して未受講者へのフォローも行えます。
ULIZA・PLAY VIDEO STORESを活用した教育向け動画配信のメリット
教育向けに高品質な動画配信を行いたい場合、ULIZAは有力な選択肢になります。
企業向けに安定した配信環境とセキュリティ機能を備え、大学のオンライン授業から企業研修まで幅広く対応しており、視聴制限や視聴分析機能も充実しています。
一方、動画教材を会員制で販売したい場合は、PLAY VIDEO STORESが便利でしょう。
レンタル販売や月額制に対応し、専門知識がなくてもオリジナルの動画配信サイトを簡単に構築できます。
また、売上や視聴状況をレポートで確認できるため、学習・セミナーコンテンツの収益化にぴったりです。
教育現場で動画配信を導入する際には、目的や運用形態に応じて、自組織に合ったサービスを選ぶことが成功への近道となります。
活用できる動画配信プラットフォームや動画販売プラットフォームについて、下記の2記事で詳しく解説していますので、ぜひチェックしてみてください。
動画配信プラットフォームとは?特徴や選び方、おすすめサービスを徹底解説!
動画販売プラットフォームとは?特徴・活用シーン・選び方を徹底解説!
まとめ
教育現場における動画配信は、学習効率の向上やコスト削減といった大きなメリットがある一方で、初期投資や運用体制の整備が必要です。
導入した際には、目的に応じてライブ配信とオンデマンド配信を使い分け、視聴管理やテスト機能を組み合わせることで学習効果を高められます。
システム選定では、セキュリティや視聴分析機能が重要となるでしょう。
初めてでどれを選べばいいかわからない、という方は、高品質配信に強いULIZAや教材販売に向いたPLAY VIDEO STORESなど、専門的なサービスの導入も検討してみてはいかがでしょうか。
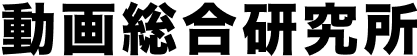
この記事の監修者: 動画総合研究所 編集部
動画総合研究所は、動画配信技術の活用による企業のDX推進をお手伝いするためのメディアです。
動画の収益化・動画制作・ライブ配信・セキュリティ・著作権など、動画配信に関わるのさまざまなコンテンツを提供いたします。






-45.jpg)








