2024.10.30
エンコードとは?知ると便利な動画配信ファイル生成の基礎知識

YouTubeをはじめTikTokやInstagramなど、いまやあらゆるメディアや利用用途で触れる機会の多い動画コンテンツ。個人だけではなく企業のマーケティング活動においても、動画の存在はますます大きくなってきています。
企業で動画を活用する際に、担当者が知っておくと便利な知識のひとつとして、動画ファイルのエンコードというものがあります。
動画におけるエンコードとは、動画のサイズを圧縮したり、テレビやインターネット上で視聴できる動画の仕様に変換する処理のことを指します。動画や映像制作に関わる方のみならず、動画を利用される立場の方であれば必ず知っておきたい基礎知識です。
今回は動画ファイルのエンコードとは何か、エンコードを行う際にはどんなコツがあるのかといった観点で解説します。
目次
動画ファイルのエンコードとは
エンコードとは、映像・文字・音声などのある形式のデータを一定の規則に従って、圧縮・暗号化を含む目的に応じた別の形式のデータに変換することを表す単語です。
もともとエンコードとは動画に限った専門用語ではなく、音声やテキストデータなどもエンコードの対象となります。
動画ファイルは映像と音声から構成されているため、「動画ファイルのエンコード」とは映像データと音声データを圧縮し、いろいろな端末から視聴が可能な動画形式に変換する処理のことを指します。
なぜ動画エンコードが必要となるのか
ではなぜ動画ファイルでエンコードがなくてはならないものなのでしょうか。
動画は1秒間に数十枚もの画像を高速で切り替えながら、パラパラ漫画のように画像が動いて見えるよう表示するデータ処理をしており、画像や音声などと比べてもデータ量が膨大となってしまいます。
この画像のコマ数のことをフレームレートと呼び、Frames Per Secondの頭文字を取って、fpsと表記されることもあります。例えば20fpsであれば、動画1秒間に20コマ含まれているという意味です。
ビデオカメラなどで撮影した動画をインターネット上で配信する際に、動画ファイルを撮影をした状態のまま用いるとデータ量が大きすぎて、ファイルのコピーや移動などを行う際にその取り扱いは非常に煩雑となり、再生する端末によっては動画を視聴することができません。特に動画の尺が長ければ長いほど、データ量は大きくなってしまいます。
また、動画ファイルには非常に多くの動画形式が存在します。インターネット上の動画をパソコンやスマートフォンで再生する場合にはブラウザ・ソフトウェア・端末などで決められた動画形式でなければ再生ができません。
そのため、インターネット上で動画を配信する際は撮影をした状態のままの動画ファイルを使用するのではなく、「動画の容量を圧縮する処理」と「視聴可能な動画形式に変換する処理」つまり動画ファイルのエンコードが必要となります。
インターネット上の動画配信でエンコードが重要な理由
さらにインターネットで動画配信を行う際に、データ量は極力小さくすることが好まれます。
その理由としては、
- 動画を視聴する際に途切れたり止まったりせず、快適に再生できるようにするため
- 動画視聴に必要以上のデータをダウンロードしなくて済むようにするため
- 動画を配信するためのサーバ負荷、回線負荷をなるべく減らすため
といったことが挙げられます。
動画視聴を行う際に膨大な動画ファイルデータを受信すると、回線状況によっては途中で再生が止まってしまったり、スマートフォンのデータ利用量に制限がかかってしまうことも考えられるため好ましくありません。
また、自社のサーバ負荷も増えてしまうため、インフラコストの増加や他システムに与える影響も考えられます。社内で同じ回線のインフラやサーバを利用していた場合、動画データが重いために経理システムに影響があって決算業務に支障が出てしまう、といったことも起こりえます。
以上の理由から、動画エンコードは「動画データを視聴者側に最適なファイルサイズと変換形式でお届けすること」「配信側のコストやインフラ負荷を減らすこと」の両面から重要な意味合いを持つのです。
▼あわせて読みたい「CDNとは?よく分かる!負荷分散と高速化の仕組み」
動画エンコードの仕組みとは
前述の通り動画は「映像データ」と「音声データ」から構成されています。
この2つのデータは「コンテナ」または「フォーマット」と呼ばれる場所にまとめられます。この、コンテナやフォーマットに映像データと音声データをコンパクトにまとめる処理が、動画ファイルの圧縮処理です。
また、動画ファイルを圧縮する際のデータ方式は「動画コーデック」と呼ばれ、以下のような種類が存在します。
- MPEG-4
- MPEG-2
- H.264/MPEG-4 AVC
- H.265/MPEG-H HEVC
- VP9 など
上記のようなコーデックの種類によって圧縮率や用途が異なります。
例えば地上デジタルやBS、CS、CATVなどはMPEG-2の映像方式と音声方式を利用しています。
また、「映像データ」と「音声データ」をまとめる際は、コンテナの種類を選択してファイルが変換されます。2つのファイルをまとめるために選択するコンテナは「動画ファイル形式」と呼ばれ、例えば以下のものが存在します。
- mp4
- wmv
- flv
- avi
- mov
- ts
- mpg など
エンコード方法の種類とは
エンコードには大きく分けて「ソフトウェアエンコード」と「ハードウェアエンコード」の2種類のエンコード方法があります。
ソフトウェアエンコード
ソフトウェアエンコードとは、コンピュータを用いてソフトウェア上でエンコードを行う方法です。
エンコーダとしては、Adobe Premiere Proなどの動画編集ソフトに対応したAdobe Media Encoderが有名です。
メリットとしてはソフトウェアの設定を変更したり、拡張したり、他のものに切り替えたりすることで様々な形式のエンコードに対応することが可能な点があります。
また、ソフトウェアは比較的安価に手に入れることが可能です。
一方デメリットとしては、使用するパソコンのCPU性能が必ずしも高いわけではないので、ハードウェアエンコードと比較すると処理速度が劣る場合があります。
ハードウェアエンコード
ハードウェアエンコードとは、特定のエンコード処理に特化したICチップを搭載した外部機器を用いてエンコードを行う方法です。
メリットとしては、CPUに負荷がかからずパソコンの状況にあまり左右されないという点が挙げられます。
デメリットとしては、設計時に組み込まれた特定のデータ形式にのみ対応し、後から他の形式の処理に対応することができない点があります。
また、ソフトウェアエンコードと比べて、エンコーダが高額であるため導入が容易ではないということもあります。
ハードウェアエンコードは、あらかじめ決められた特定の形式にのみエンコードすれば済むデジタル家電などの機器に用いられることが多いです。
動画ファイルのエンコードを行う際にファイルサイズへ影響する要因
動画ファイルのエンコードを行う際に、ファイルサイズへ影響する要因とはどのようなものがあるのでしょうか。以下4つについてご紹介いたします。
動画のフレームレート
フレームレートは、1秒間に何枚のフレーム(動画に使われる画像のコマ)が使われているかというものです。フレームレートが多くなれば映像はなめらかになりますが、エンコードしてもファイルサイズは大きくなります。
例えば、セミナーなどのビジネス系動画のようにあまり動きのない動画に関してはフレームレートを低めに設定して、ファイルサイズを小さくするということができます。
動画の解像度
動画の解像度とは、動画のフレームに含まれるピクセルと呼ばれる画素の数を指し、一般的に横×縦のピクセル数で表記されます。よく写真でも利用されるのでご存知の方も多いのではないでしょうか。代表的な例では以下の解像度があります。
・8K:4320p(7,680×4,320)
・4K:2160p(3,840×2,160)
・HD:1080p(1,920×1,080)
・HD: 720p(1,280×720)
・SD: 480p(640×480)
・SD: 360p(720×360)
解像度が高いとその分ファイルサイズも大きくなります。またYouTubeなど、最近の横長プレーヤーの場合には概ね16:9の縦横比率が使用されていますので、横が切れたりしないように予めサイズを合わせておく必要があります。
昨今では、スマートフォンでの視聴の増加やTikTokのようなSNS動画サービスなどの背景もあり、「スクエア動画」や「縦長動画」など従来にはない縦横比率での動画も出始め、プレイヤー側も対応するようになってきています。
動画のビットレート
動画のビットレートとは1秒間に送受信できるデータ量を表し、ビットレートが高ければ高いほど、画質や音質が向上します。Bits Per Secondの頭文字を取ってbpsと表記されることもあります。
500kbpsや1Mbpsなどの表記があり、ビットレートが高いほどファイルサイズも大きくなりますので、高画質にする必要がある動画の内容かどうかを考えてビットレートを変更してみてはいかがでしょうか。
動画の長さ
動画の尺が長くなれば長くなるほど動画ファイルのデータは必然的に大きくなります。こうした長いファイルを軽くする手段として解像度やビットレートを下げてファイルの容量を小さくすることはできますが、どうしても画質が低下してしまいます。
画質にある程度こだわりたい場合は、不要な部分を削除することや動画ファイルを分割して1本あたりの長さを短くすることがおすすめです。
動画ファイルのエンコードを行う際の注意点
実際に動画ファイルのエンコードを行う際に、気をつけておかなければいけないことがあります。
動画のエンコードを行うとファイルが劣化する
エンコード処理を行うと動画ファイルのデータは軽くなるものの、動画の画質や音質は劣化してしまいます。
また、エンコードによって劣化したファイルは元の品質に戻すことができません。したがって、エンコードを行えば行うほど画質・音質は落ちていきます。このように、劣化を伴う圧縮は「不可逆圧縮」と呼ばれます。
そのため、同じ動画に対し繰り返しエンコードを行うのはなるべく避けたほうがよいでしょう 。エンコードを行う際には、元データとエンコードを行うためのデータを別々に用意しておき、いざという時のために元データを保存しておくことをおすすめいたします。
エンコードには時間がかかる
エンコードを行うのには比較的時間がかかるので注意しましょう。
例えば、10分の動画をエンコードを行う処理に30分程度の時間が掛かる場合もあります。
エンコードに要する時間はさまざまな要素により決定されており、フレームレートや映像に使用されているエフェクトやエンコーダ、コンピュータのCPU性能などによってエンコード時間が左右されます。
予め配信する時間が決められている動画ファイルの場合には、余裕を持って事前にエンコードを行なっておいたほうが安全です。
動画の長さに注意する
動画の尺が長くなれば長くなるほど動画ファイルのデータが大きくなるとご紹介しましたが、エンコードの時間にも影響があります。
そのため可能であれば長い動画の場合、ファイルを分割して扱うことでエンコード時間を短く分散化させることもできますし、視聴者側も一度に大量のデータを受信しなくてもすむことに繋がりますので、制作の際に注意しておきましょう。
ビットレートは1秒間に送受信できるデータ量を表し、動画に関しては高ければ高いほど、画質や音質が向上します。エンコード時にはビットレートの設定が重要です。
動画ファイルエンコードの最低限おさえておきたいコツ
動画配信を行う際に最低限おさえておきたいことは、動画をインターネット上で配信する際には容量を圧縮したり、視聴が可能な動画形式に変換を行うエンコード処理が必要になるということ、そしてエンコードにはソフトウエアエンコードとハードウエアエンコードの2種類の方法があり、それぞれメリットとデメリットがあるということです。
また、エンコードを行う際にファイルサイズへ影響する要因を頭に入れておくことで、動画品質とファイルサイズのバランスをとることにもつながるはずです。
ぜひお手元の動画ファイルを使って試してみてください。
便利にエンコードを行うためには
動画ファイルのエンコードを行うには、上述のように比較的手間と時間がかかってしまいます。
元動画のファイルサイズにもよるのですが、YouTubeなどの無料動画サイトをはじめ、企業向けの動画配信プラットフォームにはエンコード機能はもちろん、視聴者側の回線状況に合わせた画質に調整して配信できるマルチビットレート機能を兼ね備えたものも存在します。
動画制作が専門の会社や担当者の方がいない場合には、効率よい動画の運用が求められることが多いかと思います。そのためにもなるべく手間を削減できるようなサービスを利用するのもひとつの手段としてよいのではないでしょうか。
動画配信の専門知識を持った配信プラットフォーム会社にまず相談してみましょう。
動画配信プラットフォーム「ULIZA」についてのお問い合わせはこちらから!
▼あわせて読みたい「エンコードを利用した動画配信の流れ」
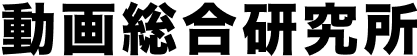
この記事の監修者: 動画総合研究所 編集部
動画総合研究所は、動画配信技術の活用による企業のDX推進をお手伝いするためのメディアです。
動画の収益化・動画制作・ライブ配信・セキュリティ・著作権など、動画配信に関わるのさまざまなコンテンツを提供いたします。














