2025.04.15
授業をライブ配信する方法は?メリットやサービスの選び方について詳しく解説します

近年、オンライン教育の需要が増加し、学校や企業研修、個人レッスンなどで授業のライブ配信が行われることが増えています。
特に、遠隔地の生徒や働きながら学ぶ人々にとって、オンラインでリアルタイム授業を受けられる環境は非常に便利です。
授業をライブ配信するためには、プラットフォーム選びや必要な機材の準備、円滑な運用方法が重要です。
どのサービスを利用するべきか?必要な機材は?トラブルにどう対応するか?こうした疑問を解消するために、本記事では授業のライブ配信のメリットや具体的な方法、プラットフォーム選びについて詳しく解説します。
授業のライブ配信を始めたい方や、より効果的な方法を探している方は、ぜひ参考にしてください。
授業のライブ配信を行うサービスの選び方は?

授業のライブ配信を成功させるためには、配信サービスの選定が重要です。
ライブ配信サービスには多くの選択肢があり、それぞれ特徴や機能が異なります。
例えば、双方向のやり取りができるもの、録画機能が充実しているもの、特定のデバイスに対応しているものなど、用途に応じて選ぶ必要があります。
そこで、授業配信に適したサービスを選ぶ際に考慮すべきポイントを詳しく解説します。
使いやすさやサポート体制、コミュニケーション機能、デバイス対応状況、導入方法など、重要な点を確認し、自分の授業スタイルに合ったサービスを見つけましょう。
サービスの使いやすさやサポート体制は十分か
ライブ配信サービスを選ぶ際は、誰でも簡単に操作できることが重要です。
特に、ITに詳しくない教師や講師が利用する場合、設定や操作が複雑なサービスでは運用が難しくなります。
そのため、ユーザーインターフェースが直感的で、必要な機能がシンプルに使えるかを確認しましょう。
また、トラブル発生時のサポート体制も重要です。
ライブ配信中に技術的な問題が起こると、授業の進行に影響を与え、受講者の満足度にも関わります。
そのため、サポート体制がしっかりしているプラットフォームを選ぶことで、問題が発生した際もすぐに対応できます。
特に、チャットや電話での問い合わせが可能か、日本語対応があるか、マニュアルやFAQが充実しているかを事前に確認すると安心です。
機能の豊富さだけでなく、直感的に操作できるか、トラブル時にすぐに対応できる環境が整っているかを確認し、スムーズな配信ができるサービスを選びましょう。
双方向コミュニケーションは可能か
授業のライブ配信をうまく進めるためには、受講者とリアルタイムでコミュニケーションが取れる環境を整えることが重要です。
特に、質問に即座に対応したり、ディスカッションを活発に行うためには、チャット機能や音声通話機能、リアクション機能があるかを確認することが必要です。
さらに、ZoomやMicrosoft Teamsのように、画面共有機能を使って資料を視覚的に見せることができるプラットフォームでは、より理解しやすい授業が実現できるでしょう。
また、ブレイクアウトルーム機能を使うことで、クラスを小さなグループに分けて討論やグループワークを行うことができ、受講者同士の交流も促進されます。
こうした機能を活用すれば、一方的な配信ではなく、受講者が積極的に参加できるインタラクティブな授業を作り出すことができます。
さらに、ホワイトボード機能や挙手機能があると、発言のタイミングを調整しやすく、スムーズに進行することができます。
またリアクション機能を使えば、受講者の理解度や意欲をすぐに把握することができ、講師はその情報を元に授業の進め方を調整することができます。
双方向のコミュニケーションを強化して、充実したライブ配信授業を作りましょう。
マルチデバイス対応か
受講者が授業を視聴する環境はさまざまで、PC、スマートフォン、タブレットのいずれでも快適に視聴できるかは重要なポイントです。
授業の質を高めるためには、受講者がストレスなくコンテンツにアクセスできる環境を整えることが不可欠です。
特にスマートフォンで視聴する場合、専用アプリが必要か、またはブラウザでスムーズに視聴できるかを確認しましょう。
アプリを使用する場合は、インストールの手間や対応端末に配慮し、学習の障壁を低くすることが大切です。
さらに、配信者側の環境も考慮する必要があります。
PCだけで配信できるサービスもあれば、タブレットやスマートフォンから簡単に配信できるサービスもあります。
配信者の利便性にも大きく影響するため、移動中や外出先からでも配信できる環境が求められる場合は、スマートフォンからの配信が可能なプラットフォームを選ぶことで、より柔軟な運用ができるでしょう。
このように、どのデバイスでもスムーズに視聴できるか、アプリが必要かどうか、また配信者が柔軟にデバイスを選べるかを事前に確認し、自分の授業スタイルに合ったプラットフォームを選ぶことが重要です。
オンプレミス型かクラウド型か
ライブ配信サービスには、「オンプレミス型」と「クラウド型」の2つのタイプがあります。
それぞれに特徴があり、導入を決める際は慎重に検討しましょう。
オンプレミス型は、自社や学校のサーバーを使ってシステムを構築し、独自に運用する方法です。
この方式では、データ管理がしやすく、セキュリティ面でも安心感がありますが、初期費用が高額で、システムの管理や運用に負担がかかる点が課題です。
一方クラウド型は、インターネット上のサービスを利用して、手軽にライブ配信ができる方法です。
初期コストが低く、導入までの時間も短縮できるため、手軽に配信を始めたい場合に向いています。
ただし、セキュリティ管理はサービス提供者に依存するため、自社の要件に合ったサービスを選ぶことが重要です。
一般的には、配信の手軽さを重視する場合はクラウド型、情報管理やセキュリティを重視する場合はオンプレミス型が良いとされています。
導入コストや運用のしやすさを考慮し、ITに詳しくない場合でも管理できるかどうかを確認した上で、自社に合った選択をしましょう。
授業のライブ配信を行う手順は?

授業のライブ配信をスムーズに進めるためには、事前準備が重要です。
配信者の運用だけでなく、受講者の視聴環境にも影響を与えるため、事前に確認をしっかり行うことで、トラブルを防ぐことができます。
ここでは、授業のライブ配信に必要な準備、インターネット環境の確認、具体的な配信手順について説明します。
配信前に準備するもの
ライブ配信をスムーズに進めるためには、必要な機材とソフトウェアの準備が欠かせません。
まず、授業を行うために使用する端末として、PCまたはタブレットを選びます。
高いスペックの端末を使うことで、安定した配信が期待できます。
また、映像の質を向上させるためには、内蔵カメラよりも外付けの高画質Webカメラを使うと、よりクリアな映像が配信できます。
さらに音声も重要なポイントのため、ヘッドセットや外付けマイクを使って、視聴者に聞きやすい音声を届けることが大切です。
暗い場所での配信の場合は、リングライトなどの照明機材を使うと、映像の見やすさがアップします。
次に、配信をサポートするソフトウェアも準備が必要です。
ライブ配信をするためには、ZoomやGoogle Meet、Microsoft Teams、YouTube Liveなどのプラットフォームを選び、配信の目的に合ったツールを使います。
また、PowerPointやGoogleスライドを準備してスライドや資料を共有し、視覚的に分かりやすくすることが大切です。
さらに、OBS Studioなどのストリーミングソフトを使えば、画面のカスタマイズやエフェクトを追加でき、より魅力的な配信が可能になります。
機材やソフトを整えた後は、テスト配信を行って動作を確認しておくことが、安定したライブ配信を実現するためには不可欠です。
準備を万全にして、本番中のトラブルを防ぎ、スムーズな配信を目指しましょう。
受講者側のインターネット環境を確認する
ライブ配信の品質は、インターネット接続の状態に左右されるため、事前に受講者の環境をできる限り確認することが重要です。
安定した視聴のためには、ダウンロード10Mbps以上、アップロード3Mbps以上の通信速度がおすすめです。
Wi-Fiを利用する場合は、接続が安定しているか確認し、必要に応じて4Gや5Gのモバイルデータ通信を活用できるかも確認しておきましょう。
また、受講者が使用するデバイス(PC・タブレット・スマートフォン)に応じた視聴方法を案内することも大切です。
ブラウザで視聴できるか、専用アプリが必要かを確認し、事前にアクセス手順を共有しておきましょう。
また音声の聞き取りやすさを向上させるために、イヤホンやヘッドセットを使用すると、快適な学習環境を確保しやすくなります。
さらに、トラブル防止のためにテスト配信を実施し、受講者が問題なく視聴できるか事前にチェックしておくと安心です。
万が一接続が不安定な場合に備え、録画データの配布や補助資料の作成を検討しておくとよいでしょう。
また、トラブル時の連絡手段を事前に案内し、メールやチャットを通じて即座に対応できる体制を整えることも、スムーズな授業進行につながります。
授業のライブ配信の手順
授業をライブ配信する際は、準備・進行・フォローアップをスムーズに行うことが重要です。
まず、PC・カメラ・マイクを接続し、配信ソフトを立ち上げてテストを実施しておきます。
スライドや教材を事前に準備したら、ZoomやGoogle Meetの配信URLを受講者に共有し、開始時間やルールを周知します。
配信開始後は、音声や映像が正常に配信されているか確認し、視聴環境をチェックします。
授業中は画面共有機能を活用し、スライドや教材を表示して受講者の理解を深めます。
また、チャット機能を使ってリアルタイムで質問を受け付けたり、質問タイムを設けることで、双方向のやり取りがしやすくなります。
配信後は録画データを保存し、受講者が復習できる環境を整えます。
YouTubeやLMS(学習管理システム)を活用すると、アクセスしやすく便利でしょう。
さらに、アンケートやチャットでフィードバックを集め、授業の改善につなげることも重要です。
次回の配信に向けては、回線や機材を再確認し、受講者の理解度に応じて授業内容を調整することで、より効果的な授業を実現できます。
授業をライブ配信で行うメリット・デメリットは?

オンライン教育の普及に伴い、授業のライブ配信を導入する教育機関や個人講師が増えています。
リアルタイムで授業を行うことで、受講者とのインタラクションが生まれ、対面授業に近い環境を再現できるという点で注目されています。
しかし、ライブ配信には利便性がある一方で、技術的な課題や運用上のデメリットも存在します。
ここでは、授業をライブ配信することのメリット・デメリットについて詳しく解説し、導入時の参考になるポイントを紹介します。
授業をライブ配信するメリット
ライブ配信授業の大きな魅力は、受講者とリアルタイムでやり取りができる点です。
チャットや音声通話を使えば、受講者が質問しやすく、講師も理解度を確認しながら進められます。
また、インターネット環境があれば場所を問わず受講でき、地方や海外の人も同じ授業を受けられます。
移動時間や交通費も不要になるため、時間を有効活用でき、運営コストも削減できます。
さらにライブ配信には録画機能があり、復習しやすく、欠席した場合も授業を見直すことが可能です。
また、対面授業では教室の収容人数に制限がありますが、オンラインなら大人数でも受講できます。
特にウェビナー形式では、多くの人が同時に参加し、効率的な授業運営が可能です。
このように、ライブ配信を活用することで、学習環境を充実させながら、運営面の負担も軽減できます。
授業をライブ配信するデメリット
ライブ配信授業は、インターネット環境の影響を受けやすい点が課題です。
回線が不安定だと、映像や音声が途切れ、視聴しづらくなることがあります。
特に、受講者ごとに通信環境が異なるため、接続テストを事前に行い、トラブルを防ぐことが重要です。
また高品質な配信には、高性能のカメラやマイク、配信ソフトウェアの準備が必要で、初期費用の確保や運用の知識が求められます。
さらに、受講者の集中力が低下しやすい点も課題です。
自宅などの環境では気が散りやすく、学習効果が下がる可能性があります。
これを防ぐには、質問を投げかけたり、クイズやディスカッションを取り入れる工夫が必要です。
また、講師が一方的に話し続ける形式になりやすく、受講者全体の理解度を測りにくい点も挙げられます。
特に、受講者がカメラやマイクをオフにしたまま視聴する場合、講師がフィードバックしづらくなります。
さらに、配信プラットフォームによっては双方向のやり取りが制限されることもあります。
チャット機能が限られていたり、音声での質問が難しい場合、受講者が疑問を解決しにくくなります。
授業の目的や受講環境に合わせ、適した配信方法を選ぶことがポイントです。
授業のライブ配信をするなら「ULIZA」がおすすめ

授業のライブ配信を行う際、どの配信サービスを選ぶべきか迷うこともあるでしょう。
特に、安定した配信環境や高品質な映像、双方向のやり取りを重視する場合、適したプラットフォームを選ぶことが重要です。
そこで紹介したいのが、「ULIZA(ウリザ)」という動画配信サービスです。
ULIZAは、多くの教育機関や企業研修で導入されており、授業のライブ配信にも活用されています。
本記事では、ULIZAの特長や魅力について詳しく解説します。
「ULIZA」とは?
ULIZA(ウリザ)は、企業や教育機関向けの動画配信プラットフォームで、ビジネス向けの動画配信に特化して開発され、安定したストリーミング技術を備えています。
その技術を生かし、授業のライブ配信にも幅広く利用されています。
ULIZAでは、リアルタイム配信だけでなく、録画したコンテンツを管理・配信できるため、オンデマンド学習にも適しています。
セキュリティ対策も充実しており、教育機関でも安心して導入できます。
また、高品質な映像を安定して配信でき、遅延が少ないため、快適な学習環境を届けられます。
ユーザー管理機能を利用すれば、受講者ごとのアクセス制限を設定でき、コンテンツの安全性を高められます。
さらに、PC・スマートフォン・タブレットなど、多様なデバイスに対応しており、受講者は好きな端末で視聴できます。
視聴データの分析機能も備えているため、受講者の学習状況を把握しやすく、教育の質を向上させられます。
このように、ULIZAは単なる配信ツールではなく、教育機関のさまざまなニーズに応える動画配信システムとして、多くの学校や企業で活用されています。
「ULIZA」のおすすめポイント
ULIZAは、大手メディアや企業の動画配信にも使われている信頼性の高いプラットフォームで、安定したライブ配信を実現できます。
映像や音声の遅延が少なく、スムーズな授業運営が可能な点が大きな特長です。
またCDN(コンテンツ配信ネットワーク)を利用しているため、大人数が同時に視聴しても、通信の負荷が分散され、安定した配信を維持できます。
セキュリティ面も充実しており、不正アクセスやデータ漏洩を防ぐ機能が備わっています。
またユーザーごとの視聴制限や特定のドメインのみアクセスを許可する設定により、コンテンツを安全に管理できます。
ブラウザ経由で利用でき、アプリのインストールが不要なのも便利な点です。
さらに、回線速度に応じて自動で画質を調整する機能があり、通信環境が安定しない場所でも比較的スムーズに授業を視聴できるでしょう。
まとめ
授業をライブ配信する際は、目的に合った配信サービスを選び、視聴環境を整えることが重要です。
配信サービスを選ぶ際は、操作のしやすさやサポートの充実度を確認し、ITに不慣れな講師でも扱いやすいものを選びましょう。
また、受講者とのやり取りを活発にするため、チャット機能やグループ分けが可能かも考慮が必要です。
PC・スマートフォン・タブレットなど、さまざまなデバイスで快適に視聴できるかも事前に確認し、配信者も柔軟に機器を選べる環境が便利です。
さらに、オンプレミス型とクラウド型の違いを理解し、セキュリティやコストを考慮した選択も重要です。
スムーズな配信には、機材やソフトウェアの準備、安定したインターネット環境の確保が欠かせません。
ライブ配信はインターネット接続の影響を受けやすいため、事前のテスト配信でトラブルを防ぎましょう。
授業の内容としては、講師が一方的に話すだけでなく、クイズやディスカッションを取り入れると、受講者の集中力を維持しやすくなります。
授業のライブ配信では、「ULIZA」のような配信サービスを利用するのも有効です。
ULIZAは、安定したストリーミング技術と高いセキュリティを備え、教育機関向けに設計されているため、授業のライブ配信にぴったりです。
授業にライブ配信を導入することで、教育の幅が広がり、より多くの人に質の高い授業を届けることができます。授業のライブ配信に適した環境を整え、効果的な授業を実現しましょう。
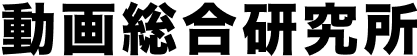
この記事の監修者: 動画総合研究所 編集部
動画総合研究所は、動画配信技術の活用による企業のDX推進をお手伝いするためのメディアです。
動画の収益化・動画制作・ライブ配信・セキュリティ・著作権など、動画配信に関わるのさまざまなコンテンツを提供いたします。














