2025.05.27
動画配信サービスを活用したコンテンツマーケティング戦略とは?

近年、コンテンツマーケティングに動画を活用する企業が増えています。
動画にはテキストベースでは実現できない訴求力があり、認知拡大から収益化まで、あらゆるフェーズで効果を発揮します。
この記事では、動画コンテンツを軸にしたマーケティングの設計方法から、配信サービスの活用法や収益モデル、運用の実践ポイントまでを体系的に解説します。
目次
動画コンテンツマーケティングとは

動画コンテンツマーケティングとは、動画を用いて見込み顧客との接点を築き、購買や契約などの行動へと導くマーケティング手法です。
動画は、視覚と聴覚の両面から情報を伝えられることから、理解や共感を得やすいという特徴を持っています。
また、SNSなど拡散性の高い媒体との相性が良く、検索エンジンでも上位表示されやすいため、コンテンツマーケティングの中でも中心的な手法として注目されています。
動画コンテンツマーケティングが注目されている理由
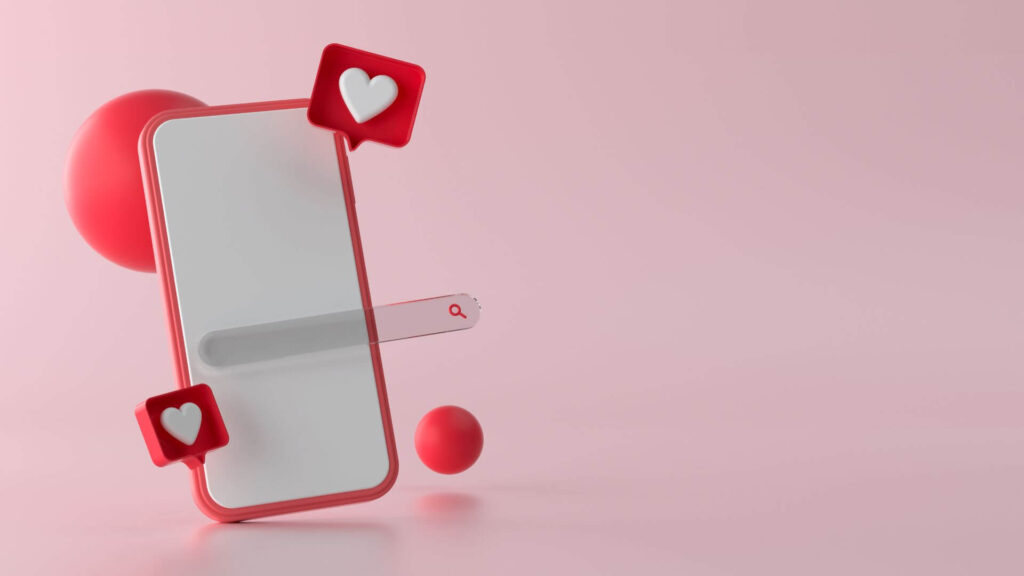
コンテンツマーケティングにおいてなぜ動画がこれほど注目されているのでしょうか。
ここでは、代表的な理由を4つ解説します。
顧客エンゲージメントが高い
動画は、ユーザーの共感や理解を得られやすいという特徴があります。
製品やサービスを映像化することで、ユーザーが利用シーンをイメージしやすくなり、自分事として認識されやすくなるからです。
共感や理解が深まることで、資料請求や問い合わせといった行動への移行率が高まります。
ブランディングに役立つ
動画は、企業の価値観や姿勢を伝えるブランディングツールとしての役割も持っています。
例えば動画全体の色使いやBGM、語り口調などを統一することで、視聴者に一貫したブランドイメージを届けられます。
また、動画は短時間で感情に訴える力が強く、理念やビジョンといった、言葉だけでは伝わりにくい抽象的なメッセージも表現できます。
企業の個性を感覚的に届ける手段として、動画は他のコンテンツより優位性があります。
集客につながる
YouTubeや各種SNS、動画配信プラットフォームは、集客チャネルとして大きな存在感を放っています。
こうした媒体を通じて動画を配信することで、自然検索とSNS拡散の両方から流入を獲得しやすくなります。
さらにユーザーの興味にマッチしていれば、シェアによる拡散効果が期待できます。
YouTubeショートやInstagramリールなどに簡潔なテーマで投稿すれば、認知拡大からWebサイトへの流入までをスムーズに導けます。
また、動画内や説明欄にリンクを設置すれば、視聴後に自社サイトやランディングページへ移動してもらいやすくなり、コンバージョンへの導線として機能します。
コスト削減と費用対効果の向上
一度動画を制作すれば、さまざまな場面で利用できます。
例えば、製品紹介動画を営業資料として活用したり、メルマガに埋め込んでクリック率の向上を図ったりするなど、1本のコンテンツが複数の施策に貢献します。
結果として、マーケティング施策全体のコスト効率を高められるでしょう。
導入手順や操作方法の説明を動画に置き換えれば、問い合わせ対応の負荷も減り、サポート工数の削減や業務効率化にもつながります。
動画コンテンツ制作のポイント

動画コンテンツマーケティングを進めていくためには、ただ漠然と動画を作るだけでは不十分です。
ここでは、動画制作で重要となる基本的な視点を3つ紹介します。
ターゲットとニーズの把握
動画制作の出発点は、誰に向けて、どのような価値を届けたいのかを明確にすることです。
訴求対象があいまいなまま進めてしまうと、伝えたい内容が分散し、意図が伝わらない動画になってしまいます。
視聴者の属性や行動傾向をもとにセグメント(区分)を行い、具体的なペルソナを設定しましょう。
その上で、どんな課題や関心を持っているのかを導き出します。
視聴者の目線から逆算して設計することで、共感を得られやすい動画が生まれます。
動画コンテンツの企画・構成
動画の目的が明確になったら、次は構成の設計に入ります。
例えば、サービスの販売を目的とする動画では、「課題の提示→解決策の紹介→行動喚起」という構成が基本です。
視聴者の関心を引きつけながら自然な流れで訴求できるため、コンバージョンにもつながりやすくなります。
ユーザーは、冒頭の数秒で視聴を続けるかどうかを決めるため、序盤に問題提起を盛り込む工夫も求められます。
動画内に行動喚起(CTA)を設ける場合は、「資料請求」や「問い合わせ」など、誘導するアクションを絞って明確に提示しましょう。
複数の選択肢を与えると判断が先送りされやすくなるため、目的に沿った行動を一つだけ示すと、成果につながりやすくなります。
動画制作
企画と構成が固まった段階で、いよいよ制作フェーズに移ります。
効果的な動画に仕上げるためには、正確な情報伝達とわかりやすさの両立が求められます。
過剰な演出に頼るのではなく、伝える内容を論理的に整理し、場面の流れに一貫性を持たせることが重要です。
情報が整理されていれば、集中を妨げずに最後まで見てもらいやすくなります。
さらにナレーションに加えて字幕を入れておけば、音声が出せない環境でも視聴できます。
また、字幕があることで情報が視覚的に補強され、理解を助ける効果もあります。
撮影や編集を内製する場合でも、照明・音声・構図といった基本的な品質には配慮が必要です。
社内にノウハウがない場合は、信頼できる制作会社に依頼するのもひとつの選択肢です。
動画コンテンツの収益化モデル

動画コンテンツは、情報提供やブランディングにとどまらず、直接的な売上を生み出す手段としても活用できます。
特に動画配信サービスの多様化によって、個人・法人問わず、収益化しやすい環境が整っています。
ここでは代表的な4つの収益化モデルを紹介します。
広告付き動画配信
YouTubeをはじめとする広告型の動画配信プラットフォームでは、動画の再生回数に応じて広告収入を得るモデルが一般的です。
視聴者にとっては無料で動画を視聴できるメリットがあり、認知拡大やトラフィックの増加にもつながります。
ただし、安定した収益を得るためには、継続的に再生数を伸ばし続けることや、一定数以上のチャンネル登録者の獲得が必要です。
そのためには、動画を定期的に投稿し、コンテンツの質を維持・向上させる取り組みが不可欠となります。
広告収入のみで大きな利益を出すのは難しいため、ブランド認知の向上や他の収益モデルへの導線としての活用が基本的な戦略となるでしょう。
有料会員制 (サブスクリプション)
一定期間ごとに課金が発生するサブスクリプションモデルは、安定した収益基盤を築きやすい仕組みとして、多くの分野で活用されています。
BtoBでは業界特化型のナレッジ提供、BtoCでは学習コンテンツやエンタメ系動画などが主な例です。
会員制にすることで、顧客との関係を長期的に維持しやすくなり、LTV(顧客生涯価値)の最大化につながります。
ただし、継続課金に見合う価値提供のためには、定期的なコンテンツ更新による鮮度維持が求められます。
レンタル
視聴期間を限定するレンタル形式は、一度見れば理解できるタイプのコンテンツに適しています。
例えば、単発のウェビナーや時事性の高い解説動画などです。
「7日間視聴可能」「1週間で自動失効」などの形式で提供すると、初めてのユーザーでも気軽に利用しやすくなります。
また販売側としても、視聴期間を制限することで、URLの使い回しや無断共有といった不正利用を抑制できます。
ダウンロード販売・ストリーミング販売
動画コンテンツを商品として提供する場合、ファイルをダウンロードさせる形式と、オンライン上で視聴のみを許可するストリーミング形式があります。
ダウンロード形式は、購入者がデバイスに保存できるため、オフライン環境でも繰り返し視聴できる点が強みです。
ストリーミング形式は、著作権保護や視聴状況の可視化がしやすく、視聴制限や不正対策、利用状況の分析にも対応できるため、販売側にとって運用しやすい形式といえます。
動画コンテンツマーケティングの注意点

動画コンテンツマーケティングは、集客やブランディングに高い効果を発揮する一方で、戦略設計が曖昧なまま進めてしまうと、期待する成果を得られないケースも少なくありません。
ここでは、実践の中で見落とされがちな注意点を紹介します。
テーマを1つに絞る
1本の動画に複数のメッセージや情報を盛り込みすぎると、視聴者の理解が分散し、結局どの要素も印象に残らない可能性があります。
視聴者にどんな行動を促したいのかを明確に定めた上で、各動画は1テーマに絞って構成することが重要です。
動画の長さ
視聴完了率を左右する要素のひとつとして、動画の長さがあります。
目的によって、最適な動画の尺は異なります。
例えば、認知拡大を目的とするのなら、短時間で印象を残せる短尺動画が効果的です。
製品説明や導入事例、教育コンテンツなど詳細な理解を促すことが目的であれば、長尺動画の方が適しています。
ただし、長尺動画は最後まで視聴されにくいという難点があります。
特に解説系の動画は情報量が多くなりやすいので、構成が不明瞭なまま進行すると、途中で離脱される可能性が高くなります。
10分を超える動画を制作する場合は、チャプターを設定したり、内容を分割したりして視聴しやすくする工夫をしましょう。
運用方法
動画は制作して終わりではなく、運用までを見据えた設計が重要です。
どの順番で視聴してもらうか、視聴後にどのような行動につなげるかなど、あらかじめシナリオを設計しておく必要があります。
動画単体で完結させず、記事やメール、セミナー、SNS投稿といった他のコンテンツと連動させることで、顧客との接点を広げやすくなります。
動画をマーケティング全体の中で機能させるためには、こうした連携を前提とした運用が欠かせません。
リスク管理
動画を公開する際には、情報漏洩や権利侵害といったリスクへの配慮が欠かせません。
個人情報が含まれる資料の映り込みや、使用するBGM・画像素材のライセンス違反などはトラブルの原因になりやすいため、慎重な確認、判断が必要です。
また、不特定多数が視聴するコンテンツでは、不正利用を防ぐ仕組みの導入も重要です。
特に有料コンテンツを配信する場合には、利用するプラットフォームにどのようなセキュリティ機能が備わっているかを把握しておきましょう。
動画コンテンツマーケティングにおすすめの動画配信サービス

配信プラットフォームの選定は、動画コンテンツマーケティングの成否を分けるポイントになります。
「PLAY VIDEO STORES(プレイビデオストアーズ)」は、機能性・操作性・セキュリティの3点をバランスよく備えた動画配信サービスとして、多くの企業で活用されています。
PLAY VIDEO STORESは、動画のアップロードから販売設定、視聴者ごとのアカウント管理までを一つの管理画面で完結できます。
配信形式も柔軟で、無料配信・有料販売・登録制・期間限定公開など、マーケティング施策に合わせて自在に組み合わせられます。
無料動画でリードを集め、その後に有料コンテンツへと導く導線設計も可能です。
さらにセキュリティ対策も充実しており、機密性の高いセミナー動画や限定配信コンテンツにも安心して使用できます。
PLAY VIDEO STORESは、初期費用が不要で導入できるため、小規模なスタートでもリスクを抑えながら動画コンテンツマーケティングを始められます。
まとめ
動画コンテンツマーケティングは、情報の伝達力や拡散性、そして収益化のしやすさという点で非常に優れた手法です。
信頼関係を築きながら顧客との接点を広げられるため、今や多くの企業にとって欠かせない取り組みとなっています。
動画コンテンツマーケティングで成果を上げるためには、ターゲットに合った企画と設計、そして継続的な運用と改善が欠かせません。
また、配信プラットフォームの選定も戦略の一部として位置付けられます。
これから動画コンテンツマーケティングを始めたいとお考えなら、セキュリティ機能や運用性に優れた「PLAY VIDEO STORES」の活用をぜひご検討ください。
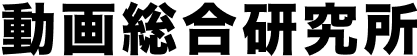
この記事の監修者: 動画総合研究所 編集部
動画総合研究所は、動画配信技術の活用による企業のDX推進をお手伝いするためのメディアです。
動画の収益化・動画制作・ライブ配信・セキュリティ・著作権など、動画配信に関わるのさまざまなコンテンツを提供いたします。














