2025.11.19
オンデマンド研修のやり方を徹底解説|導入準備から設計・配信方法までわかりやすく解説

社員研修のオンライン化が進むなか、「オンデマンド研修を導入したいが、どこから始めればよいのかわからない」と感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、人事・教育担当者の方に向けて、オンデマンド研修の始め方を基礎から丁寧に解説します。
導入準備からコンテンツの設計、配信システムの選び方、運用の進め方までを段階ごとに紹介。
読み進めることで、すぐに実践できる具体的な手順と工夫が理解できるでしょう。
目次
オンデマンド研修とは?基本の考え方とメリット

オンデマンド研修とは、受講者が好きな時間・場所で学べる映像型の研修スタイルです。
従来の集合研修と異なり、インターネット環境があればいつでも視聴できるため、業務の隙間時間を利用した学習が可能になります。
近年、働き方の多様化や地方拠点の増加に伴い、多くの企業が導入を進めています。
ここでは、オンデマンド研修の仕組みと導入による具体的な効果について解説します。
オンデマンド研修の仕組みとは?
オンデマンド研修とは、事前に録画された映像コンテンツを配信する形式の研修を指します。
受講者は学習管理システム(LMS)などのプラットフォームにアクセスし、自分の都合に合わせて動画を視聴しながら学習を進めていきます。
一般的な仕組みとしては、企業が研修動画を作成または購入し、専用のシステムにアップロードします。
受講者には視聴用のIDとパスワードが発行され、パソコンやスマートフォンから24時間いつでもアクセスできる環境が整います。
途中で一時停止したり、繰り返し見直したりすることも可能なため、理解度に応じた柔軟な学習が実現できるでしょう。
また、管理者側では受講状況や進捗率をリアルタイムで把握でき、効果測定もスムーズに行えます。
導入によるメリットと効果
オンデマンド研修の最大のメリットは、時間と場所の制約から解放され、学習の効率が大幅に向上する点にあります。
集合研修では会場の手配や講師のスケジュール調整が必要ですが、オンデマンド形式なら一度コンテンツを作成すれば繰り返し利用できるため、運営コストを大きく削減できるでしょう。
受講者は通勤時間や休憩時間など自分のペースで学べるため、業務への影響を最小限に抑えられます。
また、地方拠点や在宅勤務の社員も同じ内容を受講でき、教育の質を全社的に統一できる点も見逃せません。
さらに、理解が難しい部分は何度でも見直せるため、個々の習熟度に応じた深い学習が実現できるでしょう。
オンデマンド研修の導入準備

オンデマンド研修を成功させるには、導入前の準備が何より重要です。
目的が曖昧なまま始めると、コンテンツの方向性がぶれて、受講者の学習意欲も高まりません。
ここでは、研修を導入する前に整理すべきポイントを順番に見ていきましょう。
具体的には、研修の目的や対象者の整理、達成すべきゴールの設定、構成やスケジュールの計画など、オンデマンド研修を行うための土台を固めていきます。
こうした項目をしっかり準備することで、その後の設計や運用がスムーズに進むでしょう。
研修目的と対象者の整理
オンデマンド研修を設計する第一歩は、研修の目的と対象者をはっきり定義することです。
「新入社員のビジネスマナーを身につけさせたい」「管理職のマネジメントスキルを強化したい」など、具体的なゴールを設定しましょう。
その際、対象者の現在のスキルレベルや業務内容を把握することも欠かせません。
また、対象者が抱える課題や学習ニーズを事前にヒアリングすると、より実践的なコンテンツが作れるでしょう。
目的がはっきりすれば、その後のカリキュラム設計や教材選定もスムーズに進みます。
一方で、目的が曖昧なままでは時間とコストが無駄になりかねません。
最初の段階でしっかり整理することが、成功への重要なポイントです。
コンテンツ内容とスケジュール設計
目的と対象者が定まったら、次は具体的な研修テーマと配信スケジュールを設計します。
学習内容を細分化し、段階的に理解できるカリキュラムを組むことが重要です。
例えば、営業研修なら「基礎知識→商談スキル→クロージング技術」といった流れで、無理なく習得できる構成を心がけましょう。
各テーマの学習時間は10〜20分程度に区切ると、集中力が維持しやすくなります。
配信スケジュールでは、受講期限や目安となるペースを記載することで、計画的な学習を促せます。
また、業務の繁忙期を避けた日程設定や、週1本ずつ配信するなど、受講者が無理なく取り組める工夫も必要です。
事前にテスト受講を実施し、ボリュームや難易度が妥当かを確認しておくと安心でしょう。
オンデマンド研修のコンテンツ制作と注意点

コンテンツの質は、オンデマンド研修の効果を左右する非常に重要なポイントです。
いくら配信環境が整っていても、内容が分かりにくかったり、集中力が続かない構成だったりすれば、学習効果は期待できません。
ここでは、受講者が最後まで学び続けたくなる動画コンテンツの作り方について解説します。
自社で制作する場合の撮影のコツから受講者の理解を深めるための工夫まで、実践的な方法をお伝えしていきます。
また、コンテンツ制作時に押さえるべき注意点も併せて確認しておきましょう。
動画コンテンツの制作ポイント
効果的な研修動画を作るには、視聴者が飽きずに最後まで見られる工夫が欠かせません。
まず撮影では、講師が画面に映る場合は明るい照明と静かな環境を確保し、音声が明瞭に聞こえるよう外付けマイクの使用をおすすめします。
スライド資料は文字を詰め込みすぎず、1枚につき1つのポイントに絞ると理解しやすくなるでしょう。
編集段階では、冗長な部分をカットし、重要な箇所にテロップや図解を入れると視覚的にわかりやすくなります。
1本の動画は10〜20分程度にまとめ、長い内容は複数の動画に分割することで集中力が続きやすくなります。
また、章立てや目次を設けることで、見たい部分をすぐに探せる親切な設計になるでしょう。
テストや資料の組み合わせ
動画視聴だけでなく、理解度を確認するテストや補助資料を組み合わせることで、学習効果が大きく高まります。
各章の終わりに選択式の確認テストを設けると、受講者が内容をどこまで理解できたかを把握できます。
不正解の箇所は再視聴を促すなど、フィードバックの仕組みも重要です。
また、動画の内容をまとめたPDF資料や用語集をダウンロードできるようにすると、後から見返す際に便利になります。
実務で使えるチェックリストやテンプレートを用意すれば、学んだ知識をすぐに業務で使えるでしょう。
さらに、受講後にアンケートを実施することで、コンテンツの改善点も見えてきます。
このように多角的な学習支援を整えることが、研修の質を高める重要なポイントです。
コンテンツ制作時に見落としがちな注意点
オンデマンド研修では、配信環境が整っていてもコンテンツ内容そのものに不備があると学習効果が下がります。
まず注意すべきは、著作権や利用許諾の確認です。
外部の画像・音楽・資料を使う場合は必ず権利を確認しましょう。
また、長時間の収録や複雑な編集を盛り込みすぎると制作コストが膨らみ、継続的な運用が難しくなります。
受講者側の視聴環境にも差があるため、高解像度すぎる映像は再生に負担がかかることもあります。
さらに、講師の話し方や表情が硬すぎると受講者の集中力が途切れやすくなるため、練習やリハーサルを重ねることも重要です。
このように、コンテンツの中身・制作体制・受講環境を常に意識することで、失敗を防ぎながら質の高い研修を提供できるでしょう。
オンデマンド研修の配信・運用の方法と効果測定

コンテンツが完成したら、次は実際に配信し運用していく段階に入ります。
どのプラットフォームで配信するか、受講者への案内をどう行うかといった実務面を整理しましょう。
また、研修を実施して終わりではなく、その効果をしっかり測定し、次回の改善につなげることが継続的な成長を生みます。
ここでは、配信システムの選び方から運用のポイント、効果測定の具体的な方法まで、実践的な手順を解説していきます。
配信システムの選び方
オンデマンド研修を配信するには、自社のニーズに合った学習管理システム(LMS)やプラットフォームを選ぶことが重要です。
選定時には、まず想定する受講者数や同時アクセス数に対応できる容量があるかを確認しましょう。
また、受講履歴や進捗状況を管理者側で把握できる機能があると、運用がスムーズになります。
動画の画質やスムーズな再生環境も欠かせないポイントです。
他にも、スマートフォンやタブレットからもアクセスできるマルチデバイス対応であれば、受講者の利便性が高まるでしょう。
さらに、テスト機能やアンケート機能が標準搭載されているか、既存の人事システムと連携できるかも確認しておくと安心です。
選ぶ際には、無料トライアルで実際の操作感を試してから導入を決めることをおすすめします。
効果測定とフィードバック収集
研修の効果を最大化するには、受講データの分析とフィードバック収集を継続的に行うことが不可欠です。
LMSの管理画面では、受講者ごとの視聴完了率やテストの正答率、学習時間などを確認できます。
こうしたデータから、つまずきやすい箇所や理解度の低い項目を特定し、コンテンツの改善に活かしましょう。
また、研修終了後には受講者アンケートを実施し、内容のわかりやすさや業務でどの程度使えたかなどを尋ねることで、数値だけでは見えない課題が浮かび上がります。
さらに、受講後の行動変容や業績への影響を追跡すれば、研修の真の効果が測定できるでしょう。
定期的にデータを振り返り、PDCAサイクルを回すことで、研修の質は着実に向上し、組織全体の成長に役立ちます。
継続的な改善の進め方
研修は一度実施して終わりではなく、効果測定の結果をもとに継続的に改善を重ねる仕組みが成功の重要な条件になります。
まず、収集したデータやフィードバックを定期的に分析し、改善が必要なポイントを洗い出しましょう。
例えば、特定の動画で離脱率が高い場合は、内容の短縮や説明の補足といった対応が考えられます。
テストの正答率が低い項目があれば、その部分の解説を強化する必要があるでしょう。
また、受講者から「実務での使い方のイメージが湧かない」という声があれば、事例紹介や演習を追加することで実践性が高まります。
改善後は再度効果を測定し、PDCAサイクルを回し続けることで、研修の質が着実に向上するでしょう。
オンデマンド研修におすすめの配信プラットフォームを紹介
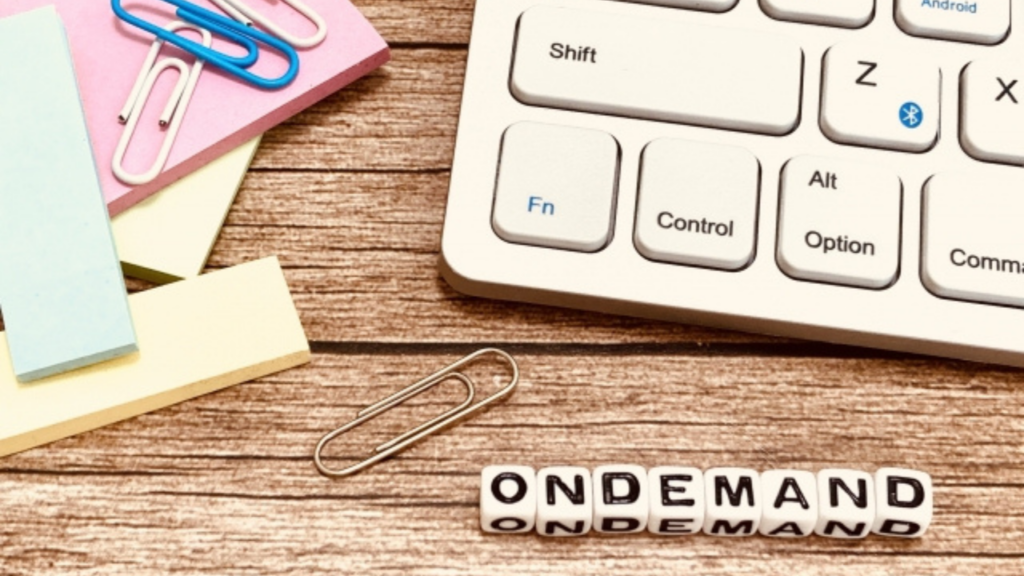
オンデマンド研修を効果的に運用するには、信頼できる配信プラットフォームの選定が欠かせません。
高画質で安定した配信、受講者ごとの視聴管理、セキュリティ対策など、研修の質を支える機能はプラットフォームによって大きく異なります。
ここでは、企業研修で実際に活用されている代表的なサービスを取り上げ、特徴や強みを解説します。
自社の研修スタイルに合ったプラットフォームを見つける参考にしてください。
効果的な運用を支える外部サービス活用
自社だけでオンデマンド研修を構築・運用するのが難しい場合、外部の研修サービスやプラットフォームを利用することで、専門知識がなくてもスムーズに導入できます。
例えば、既製のコンテンツライブラリを用意しているサービスを利用すれば、制作の手間を大幅に削減できるでしょう。
LMS機能が充実したプラットフォームなら、受講管理や効果測定まで一元化でき、運用負担が軽くなります。
技術サポートが付いているサービスであれば、トラブル発生時にもすばやく対応してもらえるため安心です。
さらに、定期的なシステムアップデートや最新の学習トレンドを反映したコンテンツが追加されるサービスもあり、常に質の高い研修環境を維持できます。
初めての導入なら、まずは外部サービスを使って経験を積むのも賢い選択でしょう。
動画配信プラットフォームの特徴やメリットについて詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
動画配信プラットフォームとは?特徴や選び方、おすすめサービスを徹底解説!
ULIZA
ULIZAは、企業の動画配信に特化した高機能プラットフォームとして、多くの企業研修で利用されています。
セキュリティ面に優れており、限定公開や視聴権限の細かな設定が可能なため、社内研修でも安心して利用できます。
また、高品質な動画をスムーズに配信できる技術力があり、大人数が同時にアクセスしても安定した視聴環境を実現可能です。
管理画面では視聴データの詳細な分析ができ、誰がいつ、どこまで視聴したかを把握できるため、受講管理が効率的に行えます。
自社のLMSとの連携も柔軟に行えるため、既存の環境を活かしながら、効率的な学習管理と受講者の利便性向上を実現できます。
さらに、サポート体制も充実しており、初めて動画配信を行う企業でも安心して運用を始められる点も魅力です。
またカスタマイズ性も高く、自社のニーズに合わせた柔軟な設定が可能なため、長期的な活用にも適しています。
PLAY VIDEO STORES
PLAY VIDEO STORESは、動画コンテンツの販売や配信を手軽に始められるプラットフォームとして注目されています。
研修動画を有料または無料で公開でき、受講者ごとに購入や視聴の管理ができる仕組みが整っています。
特に、社外向けの研修コンテンツを展開したい企業や、パートナー企業へ教育プログラムを届ける際に便利でしょう。
決済機能が標準で組み込まれているため、別途システムを用意する必要がなく、スムーズに運用を開始できます。
また、視聴期限の設定やダウンロード制限など、柔軟なコントロールが可能です。
さらに、シンプルな操作画面で専門知識がなくても扱いやすく、小規模から始めて徐々に拡大していくスタイルにも対応しています。
PLAY VIDEO STORESは、動画を資産として使い、新たな収益源や教育機会の創出を目指す企業におすすめのサービスです。
まとめ
オンデマンド研修を効果的に進めるには、目的をはっきりさせることから、設計、配信、そして改善までを一貫して計画することが大切です。
対象者に合わせて内容を構成し、わかりやすいコンテンツを作成することで、受講者の理解度と満足度が高まります。
配信後もデータ分析やアンケートを通じて改善を続ければ、研修の質は確実に向上していくでしょう。
さらに、ULIZAやPLAY VIDEO STORESのような専門プラットフォームを利用すれば、技術面の負担を抑えながら安定した運用が可能です。
本記事で紹介した流れを参考に、自社に合ったオンデマンド研修の仕組みを整えてみてください。
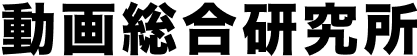
この記事の監修者: 動画総合研究所 編集部
動画総合研究所は、動画配信技術の活用による企業のDX推進をお手伝いするためのメディアです。
動画の収益化・動画制作・ライブ配信・セキュリティ・著作権など、動画配信に関わるのさまざまなコンテンツを提供いたします。















