2023.11.02
動画配信システムの構築方法は?配信方式や必要な機能も解説

動画配信システムの構築は、どの方法を選ぶかによって費用や流れは異なります。
本記事では、動画配信システムの構築方法別の特徴や、構築の手順などを解説します。
併せて、動画配信システムの配信方式や必要な機能などについても見ていきましょう。
目次
視聴者に動画を届ける動画配信システム
動画配信というと、Youtubeやニコニコ動画などの無料動画配信サービスが思い浮かぶ人も多いでしょう。
これらは基本的にtoCの動画配信プラットフォームで、商用利用できないものが多く、ビジネス用途で企業が利用する場合は法人向け動画配信プラットフォームを利用する必要があります。
法人向け動画配信プラットフォームでは、特定の人や企業などを限定して動画を配信することが可能です。
研修動画の配信や有料の教育コンテンツ販売など、多くは法人利用を目的として利用されています。
動画は文章よりも正確に情報を伝えやすく、理解もされやすいことから、従業員へのビジョンや情報の共有、教育、ノウハウの継承などで動画配信システムはよく利用されています。
また、取引先や顧客、会員などに動画を提供する場合に利用されます。
動画配信方式の違い
動画配信システムでは、動画コンテンツの配信方式が複数あり、目的に応じて配信方式を選ぶことができます。
動画配信システムの主な配信方式は、下記の4つです。
・ストリーミング配信
ストリーミング配信は、端末に配信された動画コンテンツのデータを、ダウンロードしながら順次再生する方式です。
ストレージの空き容量が不要で、ダウンロードの待ち時間もなく、長時間の動画コンテンツに向いています。
端末にデータが残らないため、機密性の高い動画コンテンツの配信でも安心できるでしょう。
ただし、通信環境が不安定だと、視聴に影響することがあります。
・ダウンロード配信
ダウンロード配信は、端末に動画コンテンツのデータを完全にダウンロードして視聴する方式です。
一度ダウンロードすれば、オフラインの環境でも何度でも視聴が可能になります。
ただし、ダウンロードが完了しないと視聴できず、ファイル容量の大きい動画コンテンツには向いていません。
端末に動画コンテンツデータが保存されることになるため、視聴権限や著作権などのコンテンツ保護が難しいという注意もあります。
・プログレッシブダウンロード配信
プログレッシブダウンロード配信は、ストリーミング配信と同様にダウンロードしながら動画コンテンツを再生しますが、視聴後のデータは一時ファイルとして端末に保存されます。
そのため、保存が完了していてキャッシュが残っていれば、通信環境がなくても配信可能です。
ストリーミング配信とダウンロード配信の特徴を併せ持ち、さまざまな動画配信システムで利用されています。
ただし、コピーや保存がしやすいため、機密性の高い動画コンテンツの配信は注意が必要です。
動画配信システムの導入方法

動画配信システムを導入するには、スクラッチ開発での構築、パッケージ利用での構築、クラウド型の動画配信システムの利用と大きく3つに分けられます。
それぞれの特徴やメリット・デメリットを見ていきましょう。
スクラッチ開発
スクラッチ開発は、オーダーメイドで動画配信システムを構築する方法です。
デザインや機能面で、既存システムにはないオリジナリティを追求でき、競合他社との差別化が図れるでしょう。
自社にとって使いやすいシステムが構築でき、長期にわたって運用できます。
ただし、ゼロからシステムを構築する分、費用は高額になり、リリースまでの時間もかかります。
また、リリース後の運用や保守も考えておかなければなりません。
スクラッチ開発の費用は構築の内容や制作会社にもよりますが、数千万〜数億円となる場合もあります。
ある程度予算を確保した大規模サービスの立ち上げや、既存のパッケージではどうしても不足がある場合に向いている構築方法です。
パッケージ利用
パッケージ開発とは、基本機能が実装されたパッケージ型のCMSを利用し、カスタマイズや機能の追加をする構築方法です。
すでに基本機能が備わっているため、あまり開発の必要がなく低コストで構築でき、短期間でリリースできます。
その分グロースや収益化も早くなるでしょう。
ただし、どれだけカスタマイズできるかはパッケージの特性に左右され、オリジナリティを出したい場合は物足りなさを感じるかもしれません。
構築費用は、制作会社はもちろん、パッケージの費用によっても変わり、数百万~数千万円までと幅広いです。
開発にかかるコストや期間を抑えたい、既存システムで機能は十分といった場合に向いています。
クラウド型
自社システムを持たずに、オンラインで提供されている、クラウド型の動画配信システムを利用する方法もあります。
開発を行わず既存のシステムを利用するため、導入のコストは大きく抑えられるでしょう。
初期費用は無料のケースも多いです。
プランによって複数の月額料金プランが用意されており、数千円程度から予算に合わせて動画配信システムを利用できます。
構築の必要がないため、リリースまでの期間も短いです。
ただし、既存サービスをそのまま利用するため、機能やデザイン面のカスタマイズ性は高くありません。
他社との差別化が図りにくい点は考えておく必要があります。
動画配信システムを構築する流れ
動画配信システムを構築する場合は、ある程度開発が必要になります。
動画配信システムを構築する流れを、5つのステップで見ていきましょう。
1. コンセプトを決定する
まずは、動画配信システムのコンセプトを明確にします。
すでにさまざまな動画配信システムが存在していますから、どう差別化を図るかは重要です。
コンセプトをはっきりさせることで、必要な機能や設定が要件定義としてまとめやすくなります。
2. 要件定義する
コンセプトが決まったら、動画配信システムに必要な機能や設定を要件定義としてまとめます。
外注する場合も、事前にまとめておけば認識にずれが生じにくく、イメージに近いシステムを構築できます。
要件定義は文章や画像などで、できるだけ具体的にまとめます。
参考にしたい既存の動画配信サービスも挙げておきましょう。
3. 開発会社を決める
要件を定義したら、開発会社を探します。
得意ジャンルや過去の制作実績なども加味し、要件定義した動画配信システムの構築が可能な会社を選んでください。
いくつか会社をピックアップしたら、要件定義の内容やリリース希望日、構築の目的などを詳しく伝えた上で見積もりをもらい、比較検討します。
開発だけでなく、リリース後の運用やサポートも踏まえて見積もりを取ることがポイントです。
4. 実装する
開発会社に発注したら、構築を待って実装します。
実装までの期間は、スクラッチ開発の場合は半年~数年、パッケージ開発の場合は2ヵ月程度が目安です。
実装は開発会のエンジニアが行うため、依頼した企業は待機するだけですが、都度動作テストや確認は必要です。
開発された動画配信システムが要件定義どおりになっているか、使いにくい部分がないかなどはしっかり確認しましょう。
5. リリースする
実装して動作テストが完了したら、リリースです。リリースの際はまずはβ版で運用する方法もあります。
β版は、ユーザーに免責をした上で運用をスタートするものです。
一定期間β版で運用して、問題ないと確認できたら正式版をリリースします。
動画配信システムの運用形態

動画配信システムを構築・導入したら運用していくことになりますが、運用形態は2種類に分けられます。
それぞれの運用形態の特徴や、どのような企業におすすめなのかご紹介します。
オンプレミス
オンプレミスとは、自社専用の動画配信サーバーを用意して、動画配信を行う方法です。
ローカル環境でシステムの構築・運用ができるため、データの送受信をインターネット経由で行うクラウドよりもセキュリティ性が高いとされています。
一度導入すれば、月額料金がかからない点もメリットです。
初期費用は高額の傾向があり、運用開始までには時間がかかる点には注意してください。
自社でシステムを保有するため、運用や保守を行うためのリソースも必要です。
オンプレミスはセキュリティを優先したい、ある程度の導入コストの高さやリソースが必要な点は許容できるといった企業に向いています。
クラウド
クラウドは、サービス提供会社であるベンダーの用意したインターネットサーバーを借りて動画を配信する方法です。
サーバーを借りるため毎月の利用料金がかかります。
クラウドの場合、提供されたサーバーを利用するだけなので、すぐに運用を開始できます。
初期費用は無料か低額で、初期のコストを抑えられるのはメリットです。自社でシステムを保有する必要がないため、運用や管理のリソースは不要ですが、月額の利用料はかかります。
また、インターネットを介する分、オンプレミスよりセキュリティが弱いとされるため、自社でも対策を考える必要があります。
クラウドは、初期費用を抑えて短期間で動画配信システムをリリースしたい、管理・運用のリソースが不足しているといった企業に向いています。
動画配信システムで備えておきたい機能
動画配信システムを構築する場合、どのような構築方法や運用方法だとしても、搭載しておきたい最低限の機能があります。
ここでは、動画配信システムで必要な基本的な機能をご紹介します。
クラウドの動画配信システムを利用する場合は、必要な機能が搭載されているかチェックしておきましょう。
会員管理・視聴制限
会員管理機能は、動画配信サイトへアクセスするユーザーを管理する機能です。
また、視聴制限機能は、特定のユーザーだけ動画視聴を許可する機能です。
動画配信システムで「社内だけに視聴を限定したい」「特定のユーザーだけ視聴を許可したい」といったニーズを満たしたい場合に欠かせない機能といえます。
会員ごとにID・パスワードを配布して限定公開する機能や、一人ひとりに独自のURLを配布する機能など、どのように会員管理・視聴制限をしたいかを考え、機能を選ぶことが必要です。
セキュリティ対策機能
法人が動画配信システムを構築する場合、機密情報を含む動画コンテンツを扱うことも多く、セキュリティ対策は必須です。
サーバーやインフラのセキュリティ環境を整えることはもちろん、動画配信形式やDRM(デジタルコンテンツの著作権を守る仕組み)への対応なども考えておかなければなりません。
動画を社内利用する場合には社内限定の機密情報を配信する場合もあるので、セキュリティは必須です。
例えば、アクセス元のIPアドレスや参照元ドメインの制限、国外からの視聴制限なども検討する必要があるでしょう。
他システムとの連携機能
動画配信システムが自社の既存システムと連携できると、費用を抑え、慣れたUIで運用することが可能になります。
動画配信システムにAPI連携できる機能があるかどうかも重要な要素でしょう。
ライブ配信機能
リアルタイムのイベントやセミナーなどで、ライブ動画配信を行いたい場合もあるかもしれません。
今後必要になるかもしれないと考える場合は、ライブ配信機能をつけておくといいでしょう。
擬似ライブ配信機能もあると便利です。
擬似ライブ配信は、収録した動画を指定の時間にライブ配信する機能。
収録した動画を用意して配信予約を行えばいいだけなので、運営のコストを削減でき、収録した動画でもライブ配信のように視聴時間を限定した配信が可能です。
動画配信システムを構築するなら目的を明確に
ビジネスでの動画配信の活用の幅は年々広がっており、それだけ動画配信システムの重要性も高まりました。
動画配信でどのようなビジネスを展開するかによって、かけられる費用や必要な機能は変わってきます。
動画配信システムに求めることを明確にした上で、自社に最適な導入方法を選びましょう。
動画配信システム「ULIZA(ウリザ)」は、日本国内で開発されて10年以上の利用実績がある動画配信システムです。
社内外へのプロモーション活動や情報発信など、さまざまな用途の動画配信ができ、セキュリティ機能も豊富なので、自社サイトへ動画配信プレイヤーを埋め込む場合などにも最適です。
動画配信を検討する際には、ぜひお問い合わせください。
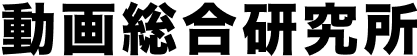
この記事の監修者: 動画総合研究所 編集部
動画総合研究所は、動画配信技術の活用による企業のDX推進をお手伝いするためのメディアです。
動画の収益化・動画制作・ライブ配信・セキュリティ・著作権など、動画配信に関わるのさまざまなコンテンツを提供いたします。





-45.jpg)








