2023.11.02
ライブ配信システムの構築方法は?選び方についても解説
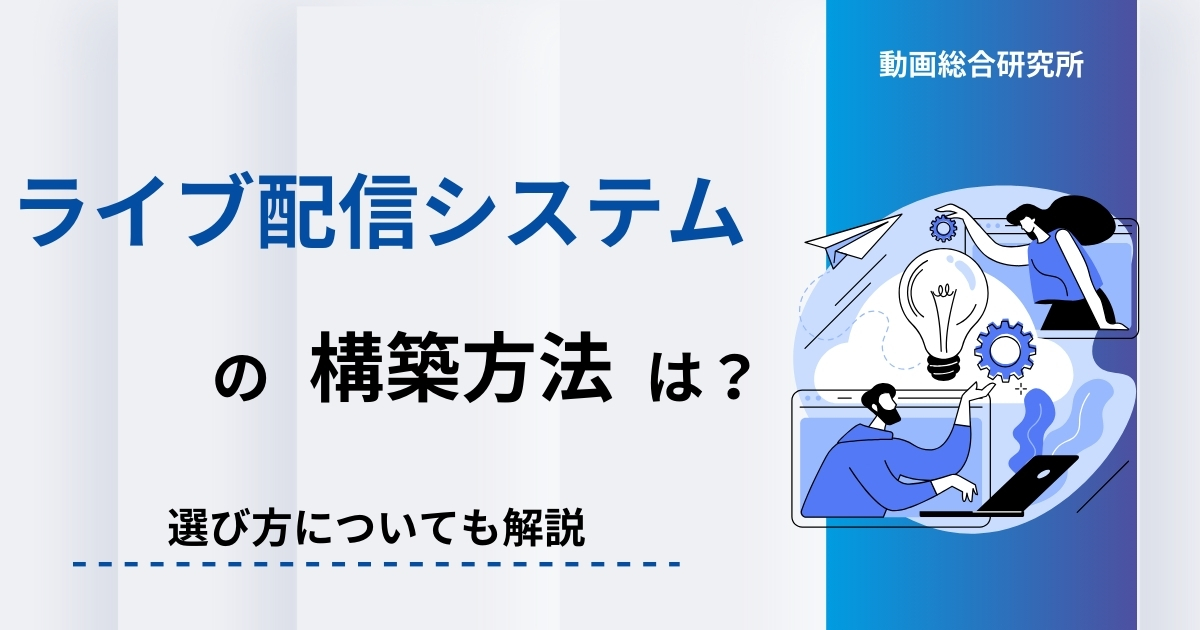
ライブ配信システムとは、特定の視聴者に向けて、リアルタイムで映像を配信する仕組みを指します。以前は音楽ライブや演劇の鑑賞用などで使われるイメージがありましたが、最近は有料のセミナーやオンラインレッスンなど、ビジネス用途でも利用されるようになりました。それに伴って、自社でライブ配信システムを構築する需要も高まっています。企業がライブ配信システムを構築する場合、どのような方法があるのでしょうか。
本記事では、ライブ配信システムの構築方法や選び方、必要な機能などについて解説します。
目次
リアルタイムで映像を配信できるライブ配信システム
ライブ配信システムは、インターネットを利用して特定の視聴者に向けて、映像をリアルタイムで配信できるシステムです。
チャットツールなどを活用することで配信中にコミュニケーションをとることができ、オンラインでも視聴者参加型のイベントが開催できます。一方的に情報を届けるのではなく、セミナーや講演会で質疑応答を行うことも可能です。ZoomやMicrosoft Teamsなどを使った双方向の映像配信は、同時に参加できる人数に制限がありますが、ライブ配信システムは多くの人に映像を届けるところに強みがあります。
ライブ配信システムを使用する目的
ライブ配信システムを使う目的は、企業によって異なります。ここでは、主な目的について見ていきましょう。
社内の情報共有
社内の情報共有を目的にライブ配信システムを使う企業があります。例えば、社内講演会や月例会の動画、経営者からのメッセージ動画、大規模な式典などが挙げられます。これらをライブ配信することは、周知事項の迅速な伝達や社員の意思統一、モチベーションアップなどにも役立つため、効果的といえるでしょう。
社内教育、研修
ライブ配信システムを使う目的のひとつに、社内教育や研修が挙げられます。社内教育や研修動画をライブ配信で行えば、移動にかかる時間や費用を気にすることなく受講できるため、より多くの従業員が参加しやすくなります。また、従業員のスキル平準化や研修担当者の負担軽減につながることもメリットです。視覚的に伝えるほうが理解しやすい業務マニュアルなどにも、ライブ配信が活用されます。
顧客への動画コンテンツ提供
ライブ配信システムは、取引先や会員などの顧客に向けて、講習やセミナーを実施する目的にも使用されます。例として、ビジネスセミナーや教育コンテンツの有料配信などが挙げられます。こうした社外向けのコンテンツは、社内向けよりも視聴者数が多くなり、画質にこだわった大容量の動画データを扱う可能性も高いため、安定稼働が可能なライブ配信システムを選ぶ企業が多いでしょう。
ライブ配信システムの仕組み
ライブ配信システムは、ストリーミング配信という配信方式が使われることが一般的です。そのため、ライブ配信を「ライブストリーミング」と呼ぶこともあります。
ストリーミング配信の特徴は、動画や音声などのデータをダウンロードしながら同時に再生するため、再生開始が早いことです。また、ストリーミング配信には、視聴する端末にデータが保存されず、キャッシュも残らないという特徴もあります。そのため、端末のストレージ容量を圧迫しません。著作権管理が必要だったり、機密情報を含んでいたりする動画コンテンツでも、安心して利用できるでしょう。
ストリーミング配信はライブ配信のほか、オンデマンド配信でも利用可能です。そのため、ライブ配信を録画した動画をアーカイブ配信するときも利用できます。
企業のライブ配信システムに必要な機能

どのようなライブ配信を行う目的ごとに、ライブ配信システムに必要な機能は異なります。また、実装する機能によって、開発の費用や期間は変わってきます。
ここでは、企業のライブ配信システムで最低限実装しておきたい機能について見ていきましょう。
会員登録・視聴制限機能
企業が社内に対してライブ配信を行う場合は、アクセスする視聴者を管理する会員管理機能と、特定の視聴者のみに配信を行う視聴制限機能が必要です。
この機能があれば、社内の機密情報を含んだライブ配信(社内向け研修や社内表彰式など)を安全に行うことができます。
コメント・チャット機能
コメントやチャットの機能は、ライブ配信の双方向でコミュニケーションができるというメリットを活かすために欠かせない機能です。ライブ配信の内容によっては、リアクション機能もあるといいでしょう。
課金・決済機能
ライブ配信でのマネタイズを行う場合は、課金や決済機能は必須となります。単発の購入、連続複数回の購入、月額課金、会員課金、投げ銭など、ライブ配信の内容に応じてさまざまな決済に対応できることが必要です。
セキュリティ機能
企業が運用するライブ配信システムなら、著作権や機密情報を含むライブ配信を行うことも考えられます。情報漏洩を防ぐために、セキュリティ機能は必須です。
また、課金・決済機能があるライブ配信システムなら、視聴者に決済情報や個人情報を入力してもらうことになるため、そういった面からもセキュリティの確保は重要でしょう。
既存システムとの連携機能
ライブ配信システムと、自社で導入しているシステムやサービス、Webサイトなどと連携できる機能も必要です。APIを利用できればAD(Active Directory)などと連携をして、視聴者の分析や管理などを行うシステムも利用でき便利です。
ライブ配信システムの運用方法の違い
ライブ配信システムの運用方法は、システムの構築を行うサーバーによって、オンプレミスとクラウドに分けられます。
一概にどちらが良いとはいえないため、費用や運用のコストなどを考慮して選んでください。ここでは、それぞれの特徴をご紹介します。
オンプレミスの特徴
オンプレミスとは、ライブ配信システムの運用に必要なサーバーや環境を、自社で管理・運用する方式です。自社でサーバー本体や周辺機器を調達し、サーバー構築も行うため初期費用は高くなりますが、システム利用料はかからず、長期間利用することでコストメリットがある場合もあります。ライブ配信システムに追加したい機能があれば自由にカスタマイズでき、自社内で管理しているシステムとも連携しやすいでしょう。
ただし、オンプレミスは保守や運用、障害対応を自社で行う必要がある点には注意しなければなりません。また、構築に時間がかかるため、運用開始までに数ヵ月かかる可能性もあります。
クラウドの特徴
クラウドは、インターネット上のサーバーにライブ配信システムを構築する方式です。クラウドサーバーの提供事業者が保有するサーバーを利用するため、オンプレミスよりも初期費用は抑えられ、運用開始後はシステム利用料を月額または年額で支払うことになります。
クラウドの場合は、申込みをしてからすぐに利用できるというメリットがあります。また、保守や運用や障害対応は、サーバー提供会社が行うため不要です。
デメリットとしては、システムに合わせたカスタマイズはしにくく、データの送受信がオンライン上で行われるため、オンプレミスと比べてセキュリティリスクがある点が挙げられます。10年単位の長期間利用の場合は、総費用がオンプレミスを上回る可能性もあるでしょう。
ライブ配信システムの3つのタイプ
ライブ配信システムは、サービス内容によって主に3つのタイプに分けられます。それぞれの特徴を見ていきましょう。
ソリューション提供タイプ
ソリューション提供タイプは、必要な要素を細かくカスタマイズできるため、自社特有の課題やニーズがある場合におすすめです。動画の不正ダウンロード対策などのセキュアな運用や、撮影・編集のサポートなど幅広い機能やサービスに対応しており、自社のニーズにあったシステムを構築できます。
例えば、ULIZA(ウリザ)なら、導入時にコンサルタントがヒアリングを行い、希望に沿った最適なプランを提案します。運用開始後も専門スタッフによるテクニカルサポートが受けられるので、ライブ配信の知識に不安があっても、安心して導入可能です。
ポータルサイト構築タイプ
ライブ配信に加え、動画視聴の入り口となるポータルサイトの構築も行いたい場合は、ポータルサイト構築タイプがおすすめです。一方的にライブ配信を行うだけでなく、視聴した人から動画にコメントをもらったり、視聴者がスマートフォンホアプリで撮影した動画をそのまま投稿したりできる機能を備えており、動画をコミュニケーションツールとして活用したい場合に向いています。
ランキング表示・新着コンテンツ表示によって、ユーザー間の動画コミュニケーションを促進できる機能を備えている場合もあります。
配信特化タイプ
ライブ配信システムの中には、シンプルにライブ配信をメインとした配信特化タイプもあります。機能は最小限でもいいので、その分コストを抑えてライブ配信を行いたい場合に向いています。
配信特化タイプは、社内向けのトップメッセージ動画の配信や、取引先や会員に向けたセミナー・講習動画の配信など、自社で用意したコンテンツを安全に配信したい場合に選ばれることが多くあります。
ライブ配信システムの選び方

ライブ配信システムのタイプの中にも、数多くのサービスがあり、どれを選べばいいのか迷ってしまうことも少なくありません。ライブ配信システムを選ぶ際のポイントを解説します。
目的に合っているかどうか
自社に合ったライブ配信システムを選ぶためには、事前に目的をしっかり把握しておくことが大切です。目的に応じた機能が備わっているかどうかを確認します。
また、目的と併せて、配信回数や動画の再生時間、視聴者数の目安についてもあらかじめ押さえておきましょう。
ライブ配信システムは、動画をストレージに保存できる容量や月間転送量、配信規模(視聴可能なアカウントID数)、各動画の再生時間・ファイル容量などによって、料金が変動することが一般的です。そのため、ライブ配信システムを使う目的、データ量等の目安は事前に明確にしておくことをおすすめします。
API連携ができるかどうか
API連携ができるかどうかも、ライブ配信システム選びの際に確認しておきたいポイントです。API連携とは、APIを使って外部のソフトウェアやプログラムなどとデータを連携し、利用できる機能を拡張することです。自社のシステムと連携すれば、アカウントを効率的に管理したり、顧客に対し動画をスムーズに提供したりすることが可能になり、ライブ配信システムがより使いやすくなります。
例えば、eラーニングを実施する際のベースとなる学習管理システム(LMS)との連携ができれば、学習管理システム上からの動画アップロードや、ユーザーの動画閲覧状況の管理などが可能になります。
自社に合ったライブ配信システムを構築しよう
ライブ配信はさまざまな用途で活用されており、ビジネスとしてライブ配信を利用する企業も多くあります。そのため、ライブ配信システムを構築したいという企業も増えていますが、どのように構築するかで費用やリリース後の運用は大きく変わります。自社にどの方法が合っているのか、よく検討して選んでみてください。
動画配信サービス「ULIZA(ウリザ)」は、日本国内で開発されて10年以上の利用実績や同時視聴者数が10万人以上のライブ配信の実績がある動画配信サービスです。ライブ配信システムをご検討の際は、ぜひお問い合わせください。
また、ライブ配信システムの構築を検討している際は、自社配信サイト構築サービス「PLAY VIDEO STORES」をご利用いただけます。ライブ配信・販売・分析に必要な機能をオールインワンでご提供いたします。















