2023.11.30
動画コンテンツとは?種類やメリット、活用の方法を解説

近年、YouTubeやInstagramといったSNSなどで動画コンテンツを視聴することが一般的になっています。
動画コンテンツはテキストや画像より情報量が多く、直感的に理解しやすいことから、企業が認知拡大や営業ツールとして利用することも珍しくありません。
本記事では、動画コンテンツの基本情報やメリット・デメリットのほか、活用のポイントなどについてご紹介します。
動画コンテンツは情報提供を目的とした動画のこと
動画コンテンツとは、情報発信のために制作された動画のことです。
エンターテイメントだけでなく、企業のマーケティングやブランディング、採用活動などでも多く活用されています。
インターネット環境やスマートフォンなどの端末の普及により、動画はいつでもどこでも視聴できるようになりました。
動画コンテンツは、テキストや画像に比べて多くの情報をユーザーに届けられることから、企業にとって情報発信の有効なツールのひとつとして利用されています。
動画コンテンツの種類
動画コンテンツは、大きく下記の3つに分けられます。それぞれの特徴について詳しくご紹介します。
■動画コンテンツの種類
| 動画の種類 | 例 |
| マーケティング・PR動画 | ・企業紹介(採用、取引先向け)・セミナー・商品・サービス紹介・マニュアル動画・お客様の声(インタビュー)・動画広告 |
| 教育系動画 | ・オンライン授業・レッスン動画・新人研修・社内セミナー |
| エンタメ動画 | ・バラエティ・音楽 ・ハウツー |
活動周知動画
企業紹介や商品・サービス紹介など、営業やマーケティングのために動画コンテンツを活用する企業が増えています。
動画で伝えることで、商品の使い方や特徴などをより具体的に紹介したり、企業の雰囲気を伝えたることが可能です。
社内向け動画
研修や社内セミナー、ノウハウ共有など、社内向けの動画は社内の資産として活用・蓄積できます。
特に、研修を動画コンテンツにすると、遠方からでも参加しやすく、いつでも均質の研修を受講可能です。
ただし、社内向けの動画コンテンツの多くは社外秘の内容となるため、公開時にはセキュリティへの配慮が必要です。
エンタメ動画
エンタメ動画は多くの視聴者の関心を惹きつけやすく、SNSで拡散されやすいコンテンツです。
企業がエンタメ動画を公開すると、ブランドイメージの定着や認知度の向上につながります。
より好感度の上がる動画を公開することでファンの構築などにもつながります。
動画コンテンツ活用のメリット
動画コンテンツにはさまざまな活用シーンがありますが、どのようなメリットがあるのでしょうか。
動画コンテンツを活用する主なメリットには、下記の4つがあります。
届けられる情報量が多い
動画コンテンツは、テキストや画像、音声のみのコンテンツに比べて、臨場感や雰囲気、人・商品の魅力といった多くの情報を届けられることがメリットです。
動画には、「言語情報」「聴覚情報」「視覚情報」と3つの情報がすべて含まれており、アメリカのリサーチ会社「フォレスター・リサーチ」のジェームス・マッキヴィー博士によると、1分間の動画にはWebページ3,600ページ分の情報量があるそうです。
Webページを3,600ページ閲覧するには膨大な時間がかかりますから、動画の情報量がいかに多いかがわかります。
現代に適している
動画視聴は、現代の生活の一部になったといえます。
総務省情報通信政策研究所が2022年に発表した「令和3年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」によると、平日の1日あたりに動画投稿・共有サービスを見る時間は、下記のようになりました。
幅広い世代が日常的に動画を視聴していることがわかります。
■平日に動画投稿・共有サービスを見る時間
| 年代 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 |
| 時間 | 89.3分 | 83.2分 | 43.0分 | 35.7分 | 25.0分 | 17.3分 |
また、高速大容量通信が可能な5Gが整備されたことから、いつでもどこでも動画を閲覧しやすくなりました。
近年は、ショート動画といわれる短い動画コンテンツが好まれ、隙間時間でよく視聴されています。
SNSの拡散力が高い
YouTubeやInstagramなどのSNSは拡散力があり、動画コンテンツを投稿することで大きな効果が期待できるでしょう。
フォロワーの視聴はもちろん、「リポスト」などのシェア機能によってフォロワー外の視聴者を取り込めます。話題性の高い動画コンテンツであるほどシェアされ、認知の拡大に効果的です。
また、自社サイトやECサイトなどに動画コンテンツを掲載すると、検索エンジンからの評価が高くなり、検索結果で上位表示されやすいといわれています。
そのためSEO(検索エンジン最適化)として、サイトに動画コンテンツを掲載することも有効です。
コストが低い
SNSの自社アカウントで動画コンテンツ公開することに、広告費用はかかりません。
そのため、フォロワーが多いほど、低コストで広く情報を届けられるでしょう。
SNSのメリットはフォロワーが少なくても、効果が期待できることです。
SNSは拡散性が高いため、フォロワーが少なくてもフォロワー外の多くの人に情報が届けられる可能性があります。
動画コンテンツの制作に関しても、用途や媒体に合わせた動画テンプレートが多く出回っており、低コストでの制作が可能です。
テンプレートを利用すると、自社でも動画コンテンツを簡単に制作できるだけでなく、クオリティも担保できます。
動画コンテンツ活用のデメリット
動画コンテンツの活用には多くのメリットがありますが、デメリットもあります。
デメリットも理解した上で、動画コンテンツを活用してください。
見てもらえるとは限らない
高品質な動画コンテンツを制作しても、ユーザーに見てもらえるとは限りません。
動画コンテンツは制作・公開して終わりではなく、公開後の集客導線を作ることが重要です。
自社サイトやSNSアカウント、メールマガジンなどで動画コンテンツ公開の告知を定期的に行うなど、集客策を検討する必要があります。
炎上やクレームにつながるおそれ
「多くの人に見てもらいたい」という想いから、誇張したサムネイルや過激な動画コンテンツを制作すると、クレームや炎上につながるおそれがあるので注意が必要です。
下記のような内容だと炎上しやすいため、特に企業の動画コンテンツでは、制作すべきではありません。
<動画コンテンツで炎上しやすい内容>
・特定の人種や性別などを差別する内容
・性的指向を否定する内容
・宗教や思想を否定する内容
・災害や非常事態など、時世的にそぐわない内容
動画コンテンツはSNSで拡散されやすく、低評価の動画は企業のイメージダウンにつながります。
また、炎上してすぐに動画の投稿を取り下げても、スクリーンショットなどにより拡散し続けることもあります。
公開前に炎上リスクをしっかりチェックすることが重要です。
時間とコストがかかる可能性
動画制作には「企画」「撮影」「編集」の工程があり、完成までに数週間~数ヵ月かかることもあります。
動画制作会社に制作を依頼すると、撮影や編集の時間は短縮できますが、当然コストがかかります。
また、社内には動画制作会社に的確に指示を出したり、完成した動画をチェックしたりする人材も必要です。
動画コンテンツを制作するには、あらかじめスケジュールや人材、予算を調整する必要があります。
動画コンテンツ活用のポイント
動画コンテンツは制作・公開するだけで効果が出るものではありません。
ここでは、効果的に動画コンテンツを活用するためのポイントを4つご紹介します。
自社の強みを理解して内容を決める
会社紹介や商品のマーケティング動画は、自社の強みを分析した上で動画コンテンツの内容を検討することが重要です。
SWOT分析などのフレームワークで分析することはもちろん、SNS上でのユーザー評価を確認すると強みの把握に役立ちます。
強みを動画で訴求することで、より動画コンテンツの効果が期待できるでしょう。
競合のコンテンツ内容をチェックする
競合の動画コンテンツをチェックすることも欠かせません。
これは、競合と似た動画コンテンツになるのを避けるためです。
リサーチしないまま競合と似た動画を公開すると、視聴者からの評価が下がるだけでなく、動画自体を見てもらえないおそれがあります。
競合の動画コンテンツをチェックし分析することで、他社にはないオリジナルの動画を制作できるでしょう。
継続的に動画を投稿する仕組みを作る
継続的に動画を投稿しなければ、マーケティング効果は実感しにくくなります。
そのため、定期的に動画を投稿する仕組みを社内に構築することが重要です。
例えば、月1回動画コンテンツを公開する場合は、下記のようにあらかじめスケジュールを組むのがおすすめです。
<月1回動画コンテンツを配信するスケジュール例>
・1週目:企画
・2~3週目:撮影・編集
・4週目:公開
また、企画から公開まで複数人で分担することで、スケジュール遅延を起こしにくくなります。
社内で内製するのが難しい場合は、外注するのもひとつの方法です。
無理なく、継続的に動画コンテンツを公開するために必要なコストを算出し、社内で調整しましょう。
制作・配信後は分析と改善を行う
動画コンテンツを配信したら定期的に分析し、動画の内容を改善することが重要です。
分析することで、マーケティング効果を高められるだけでなく、次の動画コンテンツの制作にも役立てられます。
分析する項目は下記のとおりです。
<動画コンテンツを分析する項目例>
・動画(サムネイル)のクリック率
・再生回数
・視聴維持率(動画コンテンツがどこまで再生されたか)
・流入チャネル(どこから動画コンテンツにたどり着いたか)
・動画から資料請求・特定サイトなどへの誘導率
視聴維持率は、動画がどこまで再生されたかを確認できる指標です。
どのタイミングでユーザーが視聴をやめたのかを知ることで、改善策を検討できるでしょう。
配信システムを厳選する
動画コンテンツを活用するためには、配信するシステム選びが重要です。
SNSで利用するなら必要ありませんが、自社サイトに動画を埋め込んだり、動画をマーケティングで活用したりといった場合は、動画配信システムの利用がおすすめです。
動画配信システムを利用することで限定公開などのセキュリティ面を強化することができることや視聴者の分析など、さまざまな機能が利用できるメリットがあります。
利用料はかかることが多いですが、商用利用の展開もしやすく、動画コンテンツを活用する幅が広がるでしょう。
企業こそ動画コンテンツを活用しよう
一度に多くの情報を届けられる動画コンテンツにはさまざまなメリットがあり、企業でも活用することが増えています。
注意点を踏まえた上で、効果的な動画コンテンツの制作や配信を行いましょう。
日本国内で開発されて10年以上の利用実績がある動画配信サービス「ULIZA(ウリザ)」は、自社サイトへの動画の埋め込みや、マーケティングに最適な動画配信サービスです。
動画配信を検討している人は、ぜひお問い合わせください。
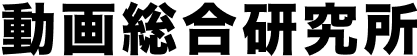
この記事の監修者: 動画総合研究所 編集部
動画総合研究所は、動画配信技術の活用による企業のDX推進をお手伝いするためのメディアです。
動画の収益化・動画制作・ライブ配信・セキュリティ・著作権など、動画配信に関わるのさまざまなコンテンツを提供いたします。





-45.jpg)








