2023.12.19
授業を動画配信する方法とそれぞれのメリット・デメリット

オンライン授業は感染症予防の観点から市場が拡大し、その利便性の高さから広く普及しました。
学校や塾だけでなく、企業の研修などでも、動画配信で授業を行う機会が増えています。
初期はリアルタイムで授業を動画配信することが主流でしたが、最近ではさまざまな形式が取り入れられるようになっています。
今回は、授業を動画配信する種類やそれぞれのメリット・デメリット、授業を動画配信する流れなどをご紹介しましょう。
授業の動画配信とは
授業の動画配信とは、オンラインで授業を行うことを指し、学校や塾、ビジネススクールなど、さまざまな場所で取り入れられています。
遠方に住んでいても授業を受けやすい、移動の必要がない、好きな時間に受講することができるといったメリットがあり、授業のスタイルのひとつとして普及しました。
教室のような会場がなくても授業を行うことが可能で、生徒も自宅にいながら受講できることで、人気が高まっています。
授業の動画配信の種類
授業の動画配信の種類には、「オンデマンド(録画)配信」と「ライブ配信」があります。
普段の授業はライブ配信で行い、復習用に単元別の授業動画をオンデマンド配信するなど、複数を取り入れることも多いようです。
また、対面で授業を行いつつ、その様子をライブ配信し、生徒は都合に合わせてどちらで受講するか選ぶハイフレックス型を採用するケースもあります。
授業を動画配信する際の種類別メリット・デメリット
授業を動画配信する場合の方法は大きくオンデマンド配信とライブ配信の2種類です。
どちらにもメリット・デメリットがあるため、理解した上で使い分けることが重要でしょう。
ここではそれぞれの方法で授業を動画配信する場合の、メリット・デメリットをご紹介します。
ライブ配信で授業を行うメリット・デメリット
ライブ配信で授業の動画を配信する場合、リアルタイムで映像が見られるため、対面の授業のような臨場感があります。
双方向でコミュニケーションをとることができ、生徒側から発言することも可能ですし、チャットなどを使って質疑応答することも可能です。
生徒の反応を見て、理解度によって内容を変更することも可能でしょう。
録画しておけば、復習用や欠席者用にアーカイブ配信で活用することもできます。
通信環境に授業の質が左右される可能性がある点は、ライブ配信のデメリットです。
画質が乱れたり音声が途切れたりといった場合、授業の内容がわかりづらくなってしまいます。
突発的なトラブルがあった場合などの対応が必要となり、授業を中断せざるをえません。
また、対面の授業と同じですが、ライブ配信の時間内に予定された授業を完了させる、時間配分が必要です。
オンデマンド配信で授業を行うメリット・デメリット
すべての生徒に同じクオリティの授業を届けられる点は、オンデマンド配信のメリットです。
講師の体調や環境などで授業の質が変わってしまうことなく、編集によってベストな授業を制作した上で配信できます。
一度制作すれば何度でも利用できるため、授業を行うためのタイムマネジメントも必要ありません。
生徒側も再生速度を好みに合わせて変更したり、わからない点を静止したり巻き戻したりできるメリットがあるでしょう。
オンデマンド配信の場合、動画の制作に手間がかかる点は考慮しておくべきです。
わかりやすい授業動画にするためには編集の技術が必要ですし、一方的な情報提供になるため生徒の理解度が把握しにくい、飽きて離脱の可能性があるというデメリットもあります。
授業を動画配信する流れ

授業を動画配信する方法の種類や、それぞれのメリット・デメリットがわかったら、実際に授業を動画配信する流れをご紹介します。
動画配信サービスを決める
授業の動画配信を行う場合、まずは利用する動画配信サービスを決める必要があります。
導入にかかる費用や月額料金のほか、行う授業の形式や配信したい人数、機能などで選んでください
資料の投影がスムーズにできるか、離脱箇所やよく見られる箇所の分析機能はあるか、LMS(学習管理システム)と連携できるかなど、必要な機能を洗い出して検討しましょう。
内容によって使い分けられることが理想のため、オンデマンド配信だけでなく、ライブ配信にも対応している動画配信サービスがおすすめです。
撮影の準備を行う
動画配信サービスを選んだら、画面投影用の資料や撮影機材を用意するなど、撮影の準備をします。
PCやスマートフォンでも撮影は可能ですが、より質を高めるなら、カメラやマイク、照明なども用意するといいでしょう。
授業のおおまかな流れを台本としてまとめておき、ライブ配信を行う場合は、リハーサルを行って、流れを確認しておくことも重要です。
動画撮影
授業を行い、その様子を撮影します。オンデマンド配信の場合は編集も行いましょう。
生徒からどう見えるかを考えて、画面を考えることが重要です。
音声が聞き取りづらかったり、資料が見えづらかったりする箇所はないか、確認しながら撮影した動画をチェックしてください。
動画配信
動画を撮影したら、利用するサービスの手順に沿って配信します。
ライブ配信の場合でも、動画は録画しておき、振り返ることで次回以降の授業に活かせるでしょう。
配信して終わりにせず、どのように視聴されているか分析したり、必要に応じてブラッシュアップしたりすることが重要です。
授業を動画配信する場合の注意点
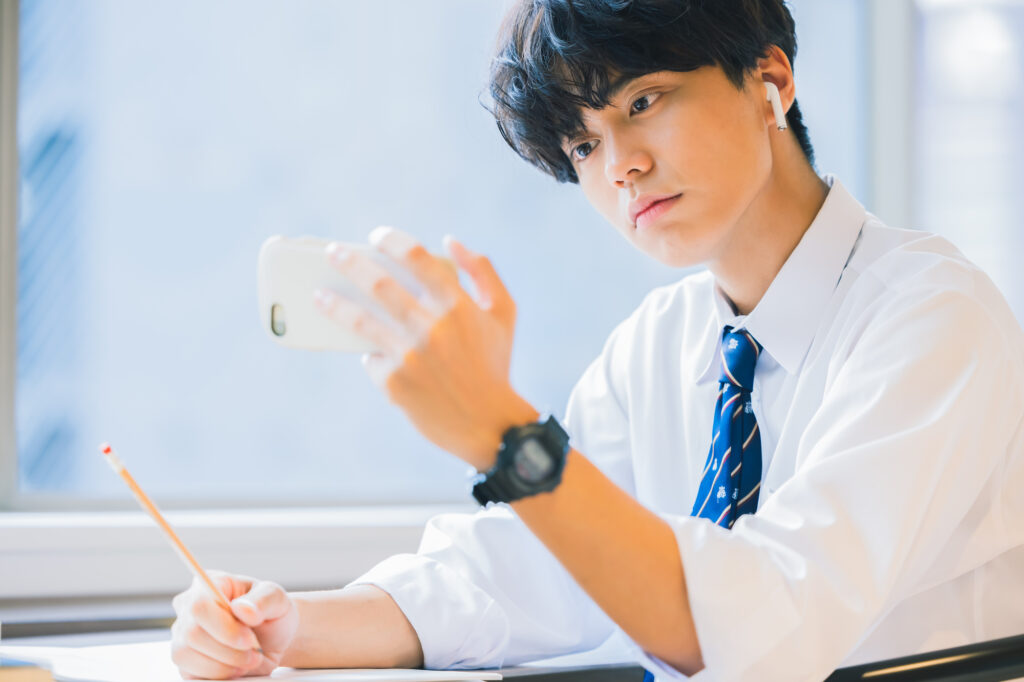
授業を動画配信する前に、知っておきたいことがあります。
ここでは、授業を動画配信する場合の注意点をご紹介しましょう。
著作権を侵害していないか確認
授業の動画を制作する場合、音楽や資料が著作権を侵害していないか確認してください。
BGMとして音楽を使用したい場合は、音源を管理するJASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)などに申請し、使用料金を払わなければならない可能性があります。
市販の教材などを資料として投影する際も、注意が必要です。
限られた範囲であれば許諾なしで利用できることが多いですが、YouTubeなどで不特定多数に公開する場合は、著作者の許諾を得なければ著作権侵害となる可能性があるため、注意してください。
不正アクセスへの防止
授業を動画配信する上で、不正アクセスには注意してください。
不正なダウンロードや生徒以外のアクセスを防ぐセキュリティ対策が必要です。
動画配信サービスを選ぶ場合は、どのようなセキュリティ対策をとっているかも確認しましょう。
動画の暗号化やアクセス制限、DRM(デジタル著作権管理)の利用などもチェックしてください。
通信環境の確認
授業の動画配信は、配信側の通信環境の整備も重要ですが、生徒側の通信環境が整っていないと、やはりスムーズに視聴ができません。
さまざまな環境で視聴されることを考えて、スマートフォンでも見やすいか、ファイルサイズは大きすぎないかなどを意識して制作するといいでしょう。
授業の動画配信にチャレンジしよう
授業の動画配信は、配信する講師側にも生徒側にもメリットがあり、広く利用されています。
活用することでビジネスの幅も広げられるでしょう。
実施にあたってはセキュリティや著作権といった注意点もあるため、配信したい授業の内容に合う機能を備えた動画配信サービスを利用しましょう。
動画配信サービス「ULIZA(ウリザ)」は、日本国内で開発されて10年以上の利用実績があり、授業の動画配信でも広く利用されています。
オンデマンド配信はもちろん、ライブ配信やアーカイブ配信にも対応していますので、授業動画の配信を検討している場合には、ぜひお問い合わせください。
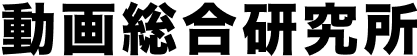
この記事の監修者: 動画総合研究所 編集部
動画総合研究所は、動画配信技術の活用による企業のDX推進をお手伝いするためのメディアです。
動画の収益化・動画制作・ライブ配信・セキュリティ・著作権など、動画配信に関わるのさまざまなコンテンツを提供いたします。





-45.jpg)








