2024.02.01
ハイブリッド配信とは?メリット・デメリットや配信の手順などを紹介
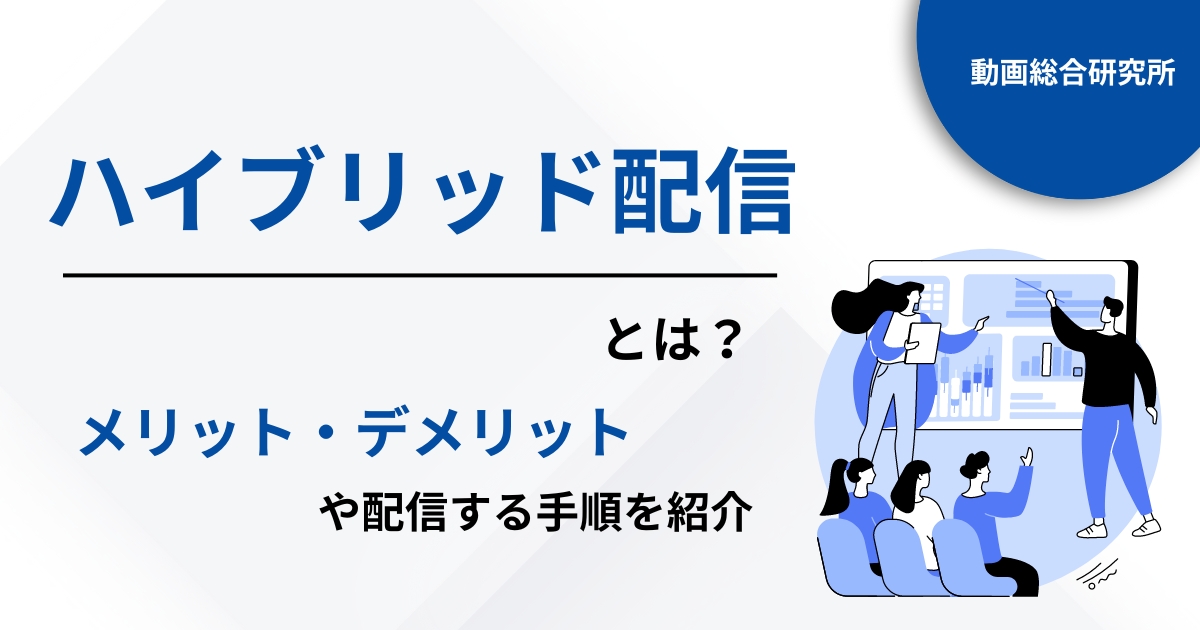
ハイブリッド配信は、2021年後半頃から普及し始めた配信方法です。オフラインとオンラインの利点を兼ね備えた配信方法であることから、企業の株主総会や展示会、PR、教育機関によるオンラインセミナーなど、さまざまなイベントで活用されており、注目を集めています。
ここでは、ハイブリッド配信のメリットとデメリット、具体的な配信方法や必要となる機材についてご紹介します。
目次
ハイブリッド配信とは、オフラインのイベントとオンライン配信を融合した配信方法

ハイブリッド配信とは、会議室や会場などでのオフラインイベントを行いながらオンライン配信も行う方法を指します。オフラインイベントと同時にライブ配信を行う場合が多く、オフラインとオンラインの双方向でのコミュニケーションを図ることができる点が特徴です。
ハイブリッド配信が普及し始めたのは、2021年後半頃からです。2020年頃は、新型コロナウイルス感染症対策として、あらゆるイベントや会議がオンライン配信に切り替わりました。その後、密を避けつつも参加者の満足度が高い配信方法として注目を集めたのが、オフラインとオンラインの利点を兼ね備えたハイブリッド配信です。
現在では、企業の社内会議や商品・サービス紹介、株主総会、スポーツイベント、コンサート、教育系のセミナーなど、多種多様なハイブリッド配信が行われています。
ハイブリッド配信のメリット
リアルなイベントとオンライン配信を融合したハイブリッド配信は、イベント開催だけを行う場合に比べて多くのメリットがあります。代表的なメリットをご紹介します。
集客しやすい
ハイブリッド配信は、参加人数に限りがある会場でのイベント開催だけよりも、多くの集客が期待できます。「リアルで臨場感を味わいたい」「会場での一体感を楽しみたい」といったオフラインを選ぶ層と、「会場に赴くのは難しいが参加はしたい」「自宅などから気楽に楽しみたい」といったオンラインを選ぶ層の両方を取り込むことが可能です。特にオンラインでは、参加すること自体のハードルが下がるので、集客しやすいといえます。
また、ただ集客できるだけではなく、自分に合った参加方法を選べるため、参加者の満足度が高まることも期待できるでしょう。
参加者枠の調整ができる
参加者枠を調整しやすいことも、ハイブリッド配信のメリットといえます。イベント開催のみの場合、集客見込み数と会場規模やコストなどの予測が立てにくく、想定集客数を下回ると赤字になりかねません。しかし、ハイブリッド配信の場合は、会場の収容人数を超える参加希望者がいても、オンライン配信に誘導、振り替えることが可能です。
また、感染症の拡大などで会場の参加人数に制限が課せられるような事態になった場合、ハイブリッド配信ならイベント中止を回避することができます。
コストを削減できる
ハイブリッド配信は、イベント開催のみよりもコストを削減できます。イベント開催のみで多くの人を集客しようとすると広い会場を手配する必要があり、その分、費用はかさみます。しかし、ハイブリッド配信なら、オンラインでも集客ができるため、広い会場を手配する必要はありません。
また、参加者側からすると、オンラインに参加すれば交通費などがかからないため、移動コストが削減できることもメリットといえます。
ハイブリッド配信のデメリット
メリットが多い一方で、ハイブリッド配信にはデメリットもあります。ハイブリッド配信を行う前に下記を確認しておきましょう。
機材設置のハードルが高い
ハイブリッド配信は、配信用機材を設置するハードルが高いことがデメリットです。
特にライブ配信を行う場合は、主催者側が画面の向こうに一方的にメッセージを発信するような従来のオンライン配信と異なり、オフラインとオンラインのどちらにも映像や音声を届ける必要があります。
会場の音声や映像をオンライン参加者に届けるためのマイクと撮影機材のほか、オンライン参加者の音声や映像を会場で視聴するためのスピーカーや投影モニターの設置も必要です。
また、安定した配信を行うためにインターネット環境についてもしっかり確認しておきましょう。
参加者対応が煩雑になる
参加者対応が煩雑になることもハイブリッド配信のデメリットといえます。会場でのイベントとライブ配信を同時に行うハイブリッド配信の場合、オフラインの会場とオンラインとでは参加方法が異なるため、両者にストレスなく参加してもらう配慮が必要です。
例えば、オフラインの会場では発表者や参加者がわかりやすい位置にスクリーンや撮影機材を配置しますが、オンライン参加者側の見え方にも注意しなくてはなりません。カメラのアングルだけでなく、オフライン参加者の通行の邪魔にならないように、会場の動線にも配慮が必要です。また、会場に配布した資料について説明するシーンでは、オフライン参加者に向けて資料を投影する画像に切り替えるといった工夫も求められるでしょう。
ハイブリッド配信のパターン
ハイブリッド配信にはさまざまなパターンがあります。ここでは、主な配信パターンについて詳しく見ていきましょう。
会場イベントとライブ配信を行う
会場でイベントを行い、同時にオンライン配信を行う方法は、最も一般的なハイブリッド配信のパターンです。会場がメインでプレゼンテーションなどを行うあいだ、オンライン配信では質問やアンケート、チャットなどを活用し、双方向のコミュニケーションがとれるよう進行するケースが多くあります。
イベントの進行に併せて、映像や音声をどう切り替えるかなど、事前に入念なリハーサルが必須で、特に機材トラブル発生時のシミュレーションはしっかり対策をしておく必要があります。
複数の会場イベントとライブ配信を行う
ハイブリッド配信には、複数の会場でイベントを行いながら、ライブ配信を行うパターンもあります。例えば、メイン会場とサブ会場を分ける、東京会場と大阪会場といったロケーションを分けるなどの場合です。
会場間の連携が必要なため、単独の会場とのライブ配信に比べて運営の難易度は高くなりますが、展開に変化を持たせやすくイベントの盛り上がりが期待できます。
会場イベントとオンデマンド配信を行う
会場で開催したイベントを収録し、オンデマンド配信を行うパターンも、ハイブリッド配信のひとつです。オンデマンド配信はイベント後に動画配信用のサーバーに動画をアップロードするため、イベント中は配信トラブルなど気にせず会場の運営に集中できます。また、録画した動画を見やすく編集して公開が可能なため、クオリティの高い動画配信ができることも特徴です。
オンデマンド配信の参加者側からすると、都合のいいタイミングで視聴できるというメリットがありますが、双方向のコミュニケーションはとりにくく、会場との一体感は感じにくくなります。
ハイブリッド配信に必要な機材

ハイブリッド配信を行うためには多くの機材が必要です。下記に一般的な機材をご紹介します。
なお、自社で機材やリソースの都合がつかない場合は、貸会議室やホテルの宴会場などでレンタルしたり、外部業者にオペレーションを委託したりすることも可能です。
配信用PC
配信用PCは、カメラ映像やマイク音声などの配信コンテンツをネットワークに送るために使います。映像を送信するので、相応のマシンスペックを必要とします。
音声ミキサー
音声ミキサーは、会場で使用するマイクや動画コンテンツの音声・BGMなど、それぞれの音を聞き取りやすいように適正なレベル、バランスに調整します。
カメラ
カメラは、会場の様子を撮影するために必要です。イベントでは通常、ビデオカメラを使用しますが、映像は切り替わりがないと単調に映るので、2台またはそれ以上を使用するケースが多くあります。
マイク
マイクは用途によって、手持ちのハンドマイクや、服などに装着して使う小型のピンマイク、特定の方向の音声を捉えやすいグースネックマイクを使い分けます。身振り手振りを交えてのプレゼンテーションならピンマイク、登壇者が講演する場合はハンドマイク、演台で発言するならグースネックマイクを使用することが一般的です。
プロジェクター
プロジェクターは、会場の参加者向けにスライドや動画などのコンテンツを投影するために使用します。大画面に投影することで、参加者の意識が会場の正面に向きやすくなり、一体感のあるイベントが開催できます。
ビデオスイッチャー
ビデオスイッチャーは、動画やスライド資料などのPC上のコンテンツや、カメラ映像から任意に選んで、出力することができる機器です。同時に複数の入力映像を表示させることも可能です。
スタンド照明
スタンド照明は、三脚で設置する照明で、主に発表者を明るく照らして顔周りの映りを良くします。被写体が暗いと動画にノイズが入りやすくなりますが、照明をあてることにより動画の画質を高めることができます。
スピーカー
スピーカーは小規模の会場であっても必要です。発表者や質問者の発言、コンテンツの音声など、聞き取りやすいように参加者に届けます。
HDMIケーブル
HDMIケーブルは、ビデオカメラ、コンテンツを格納したPCと、映像ミキサーを接続するために使用します。接続したい機器によってコネクタの形状や必要な長さが異なるほか、HDMIケーブルのバージョンによっても伝送速度や解像度が異なるため、事前にスペックの確認が必要です。
有線LANケーブル
有線LANケーブルは、インターネットの接続不良を回避するために使用します。Wi-Fiに比べて安定しているため、配信には有線LANケーブルで接続するのが一般的です。
ハイブリッド配信の成功の秘訣
ハイブリッド配信を成功させるためには、どのようなポイントがあるのでしょうか。ここでは、事前に知っておきたいハイブリッド配信の成功の秘訣をご紹介します
配信の目的・進行を考える
ハイブリッド配信を成功させるためには、まず配信の目的や進行をしっかり考えておくことが大切です。ハイブリッド配信は、会場でのイベントとオンライン配信の両方を行うため、コストや人的リソースなどの負担がかかります。イベントの目的やターゲット層をしっかりと確認した上で、本当にハイブリッド配信にする必要があるのかどうかを検討しましょう。
ハイブリッド配信を行う場合は、オフラインとオンラインのどちらに比重を置くのかを決め、最適な配信構成や演出を考えます。
参加方法の区別なく楽しめる仕掛けを加える
ハイブリッド配信は、オフラインとオンラインのそれぞれ参加者がいるため、どちらにも区別なく楽しめる仕掛けを加えることが成功の秘訣です。
特にオフラインイベントとライブ配信を行う場合、オフライン参加者だけが盛り上がってしまう傾向があります。リアルタイムチャットやアンケート、クイズなど双方向のコミュニケーションがとれるツールを活用して、オンライン参加者がイベント会場と一体感を味わえるような仕掛けがあるとよいでしょう。
また、進行役は積極的にオンラインの声を拾うなど、参加者全員を巻き込む意識をもつことも大切です。
ハイブリッド配信を行うなら、動画配信プラットフォーム「ULIZA(ウリザ)」がおすすめ
ハイブリッド配信はメリットが豊富な一方で、機材や配信環境の準備、参加者への配慮など、事前に準備すべきことが数多くあります。また、配信トラブルを防ぐためにも、配信規模や内容に合うシステムを導入し、事前準備を念入りに行う必要があるでしょう。
動画配信サービス「ULIZA(ウリザ)」は、日本国内で開発されて10年以上の利用実績がある動画配信プラットフォームです。規模感やニーズに合わせたプランニングが可能で、自社のブランドイメージや配信サイトのテーマに合わせた、柔軟なカスタマイズにも対応しています。
ハイブリッド配信が初めての方でも、動画配信技術に精通しているエンジニアのサポートもあるため、安心してご利用いただけます。ハイブリッド配信を行うなら、「ULIZA(ウリザ)」をご検討ください。
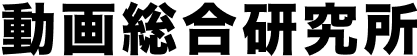
この記事の監修者: 動画総合研究所 編集部
動画総合研究所は、動画配信技術の活用による企業のDX推進をお手伝いするためのメディアです。
動画の収益化・動画制作・ライブ配信・セキュリティ・著作権など、動画配信に関わるのさまざまなコンテンツを提供いたします。














