2024.03.13
社内研修を動画配信するメリット・デメリットは?配信方法を解説
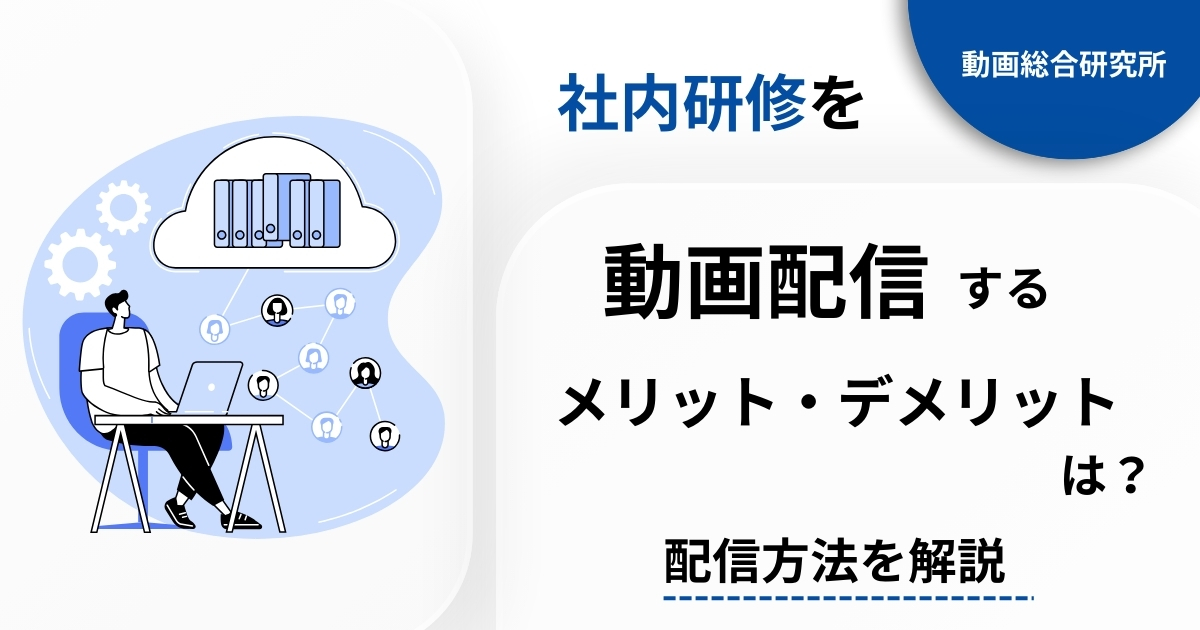
近年、従業員の効率的な育成やコスト削減などの目的で、社内研修を動画配信で行う企業が増えています。対面研修の場合、交通費や宿泊費、移動時間が必要ですが、動画配信であれば場所を選ばずに参加することができ、配信方法によっては個人の都合の良いタイミングでの視聴が可能です。また、働き方の改善や合理化を進めることもできるため、社内研修を動画配信する企業は今後も増加するでしょう。
本記事では、社内研修を動画配信するメリットやデメリット、配信の形式や動画制作におけるポイントについて解説します。
目次
社内研修を動画配信するメリット
社内研修を動画で配信するメリットは企業によってさまざまです。動画配信の代表的なメリットをご紹介します。
受講率向上が期待できる
研修を動画配信する場合、インターネット環境があれば、いつでもどこでも視聴することができるため、受講率の向上が見込めます。対面研修では、受講できる日時や場所が限られてしまいますが、動画配信すれば、好きなタイミングで受講できるため、気軽に参加できるでしょう。
近年は、テレワークや短時間勤務などの多様な働き方を実施している企業が増えています。場所を選ばない動画配信は勤務形態を問わずに視聴できるため、多くの企業で受講率の向上が期待できます。
受講者の理解度を高められる
社内研修の動画配信は、繰り返し視聴できるため、受講者の理解度を高められるという利点があります。対面式の研修では、同じ箇所を何度も説明してもらうことは難しいですが、動画配信は自分のわからないところを繰り返し再生できるので、理解度を高めることが可能です。
疲れたら一時停止して、リフレッシュしてから再開できるのも動画配信のメリットのひとつです。
コストを削減できる
対面で行われる研修は、会場までの交通費や宿泊費、会場や機材のレンタル代、運営スタッフの人件費などが発生しますが、動画配信であればこれらの費用を減らすことができます。動画撮影などのイニシャルコストは必要ですが、中長期的には大きなコスト削減が見込めるでしょう。
繰り返し使用できる
研修のため制作した動画は繰り返し使用することができます。そのため、講師や運営が何度も研修を行う必要がなくなり、研修に費やしていた労力をほかの業務に活かすことが可能です。また、講師によってわかりやすい・わかりにくいといったばらつきが発生することもなく、一定の研修品質を保つことができるでしょう。
社内研修を動画配信するデメリット
メリットがある一方で、動画配信にはデメリットもあります。社内研修を動画で配信する場合のデメリットをご紹介します。
時間や手間がかかる
研修動画の制作には、相応の時間と手間がかかります。動画編集・加工にも一定の知識や技術が必要です。もちろん編集や加工を行わず、撮影した動画をそのまま使うことで手間を省くこともできますが、動画のクオリティは下がってしまうでしょう。
撮影動画で研修の効果を高めたいのであれば、編集や加工を行って、クオリティの高い動画を作ることをおすすめします。
コミュニケーションが取りづらい
動画配信による研修は、受講者が任意のタイミングで参加退出できるので、受講者を巻き込んだアプローチが難しいといったデメリットがあります。また、会場のように一人ひとりの表情を確認できないので、反応がわかりづらいのも難点です。
受講者の反応や研修の成果を知りたい場合は、チャットなどのコミュニケーションツールを活用したり、研修後にアンケートを実施して効果を確認したりするなどの工夫が必要です。
また、受講者同士や講師とのコミュニケーションが希薄になるのも、オンライン研修の特徴です。参加者同士の交流による学習効果や気づきを与えたい場合は、オフライン研修を実施するか、研修の様子をリアルタイムで配信し、積極的に参加者同士が関係構築できる機会を作りましょう。
社内研修の動画配信形式はオンデマンド配信とライブ配信がある

社内研修の動画配信形式にはオンデマンド配信とライブ配信の2通りがあります。目的に応じて使い分けましょう。
オンデマンド配信
オンデマンド配信とは、あらかじめ収録した動画を配信サーバーにアップロードし、配信する方法です。何度でも撮り直しができるため、クオリティの高い動画コンテンツを制作することができます。サーバーへのアップロード後は、インターネット環境さえあればいつでもどこでも視聴できるので、全国の従業員に研修を受講してもらうことができます。
そのため、オンデマンド配信は、すべての従業員に理解してもらいたいコンプライアンスやメンタルヘルスなどの基礎プログラムに向いています。
ライブ配信
ライブ配信とは、リアルタイムで動画を配信する方法です。あらかじめ撮影した動画を配信するオンデマンド配信とは異なり、その場で開催されている研修を撮影し、そのまま配信します。
講師と受講者がリアルタイムでチャットや質疑応答ができるといった双方向のコミュニケーションが可能なので、理解を促進することができるでしょう。また、受講者の反応やリクエストによって、臨機応変に配信内容を変えられるメリットもあります。
これらの特徴から、ライブ配信はコミュニケーションに重点を置いた研修や、個別に講師からの指摘やフィードバックが必要なプログラムと相性の良い配信方法です。ただし、オンデマンド配信のように動画を編集、加工することができないので、事前の準備やリハーサル、運営ノウハウが必要になります。
社内研修の動画配信はオープン型とクローズド型、どちらがいい?
動画配信は、オープン型とクローズド型に分かれます。社内研修の場合は、主にクローズド型を選択することが一般的です。オープン型とクローズド型のそれぞれの配信方法について解説します。
オープン型配信
オープン型配信は、会社説明会やセミナー、商品・サービスの販売促進ウェビナーなど、自社の研修を社外の不特定多数に向けてアピールする場に向いている配信方法です。
YouTubeなどで簡単に公開できる反面、誰もが視聴できるため、機密情報の取り扱いや配信アカウントのセキュリティ対策などの注意が必要です。また、企業のブランディングに影響するため、公序良俗に反する発言が含まれていないかなどの表現チェックも重要です。
クローズド型配信
社内研修やタウンホールミーティングなど、特定の対象者に向けた配信方法をクローズド型配信といいます。部外者は参加できないので、機密情報が含まれた情報共有を行うのに適しています。
クローズド型配信は、主催者より配布されたURLから動画にアクセスします。URLの流出に備えて、ログインするためのアカウントやパスワードを設定するのが一般的です。また、アカウントに紐づいた動画の視聴履歴や再生回数などを管理することもできます。社内研修の場合は、クローズド型配信が向いているでしょう。
社内研修の動画制作手順

社内研修の動画を制作する場合は、4つのステップで進めるといいでしょう。それぞれのステップを解説します。
1 研修の目的を明確にする
動画を制作する際は、まず「研修の目的を明確にする」ことから始めましょう。どのような従業員を対象として、ゴールはどこなのかといったことをはっきりさせないと、動画の構成を作ることができません。また、内容も曖昧になってしまうため、効果が出ない研修になる可能性があります。
2 オンデマンド配信かライブ配信かを決める
続いては、研修の目的や意図に応じて、配信方法を決めましょう。新入社員研修であれば、参加者同士の一体感やモチベーション向上のために、リアルタイム性を重視したライブ配信が適しているかもしれません。一方、研修内容が均一なコンプライアンスやセキュリティなどの研修は、従業員の好きなタイミングで受講できるオンデマンド配信のほうが向いています。
3 配信システム・プラットフォームを決める
オンデマンド配信かライブ配信かを決めたら、配信システム・プラットフォームを決めます。社内研修であれば自社のイントラネットを用いることができますが、漏洩防止やパスワード認証などのセキュリティ対策ができる外部の動画配信サービスを利用するケースが一般的です。
ビジネス向けの動画配信サービスを活用すれば、自社でシステム構築をする必要がなく、研修素材をそのまま配信できる手軽さがあるからです。また、動画の再生回数やたくさん視聴されているシーンの抽出、受講者一人ひとりの視聴分析などの機能もあると、研修の振り返りや今後のプランニングにも役立つでしょう。
4 動画を作成し、配信を行う
配信システム・プラットフォームを決めたら、研修内容の作り込みを行います。オンデマンド配信であれば、撮影した動画を編集・加工して完成度を高めます。ライブ配信であれば、事前に研修の流れを確認し、リハーサルを行った上で本番に挑むことが望ましいでしょう。
動画制作のノウハウやリソースがない場合は、動画制作会社に依頼するのもひとつの方法です。
社内研修の動画配信を成功させるポイント
社内研修の動画配信を成功させるためには、受講者目線に立った事前準備や配慮が大切です。
社内研修の目的はいうまでもなく、従業員の知識やスキルの向上です。ただし、動画配信形式での研修が初めての場合は、操作に慣れず戸惑う従業員もいるかもしれません。また、全従業員に受けてもらいたい研修なのに、腰が重く受講が進まなかったり、受講は進んでいてもコンテンツが長く複雑で途中で離脱してしまったりするケースも考えられます。
社内研修の動画配信を始める場合は、操作方法のマニュアルやガイダンスを設けましょう。そして、研修コンテンツを従業員に案内する際は、具体的な内容や目的、視聴することで何が得られるのかを明記します。
視聴の日程や締め切りがある場合は、何度かリマインドを送るなどして未受講や不参加が生じないようにしましょう。長い動画は飽きやすいため、テーマごとにコンテンツを複数に分けて、理解度をチェックするテストを実施すると効果的です。
社内研修の動画配信なら、セキュリティの充実した「ULIZA(ウリザ)」がおすすめ
社内研修を動画で配信することで、従業員の知識やスキルの向上とコスト削減、業務の効率化などが期待できます。ただし、社内研修は機密情報が含まれるケースが多いため、セキュリティ対策が重要です。
「ULIZA(ウリザ)」は、社員番号などに紐づけるIDやパスワード形式のセキュリティや、IPアドレスでのアクセス制限などの情報漏洩を防ぐ機能を搭載しています。また、さまざまな分析機能があり、研修コンテンツごとの再生回数はもちろん、1つの研修動画の中で多く視聴されているシーンや離脱率の高いシーンなどを確認することもできます。受講者一人ひとりの視聴状況や分析も可能なので、研修コンテンツのブラッシュアップや今後の研修プランニングにも役立つでしょう。
「ULIZA(ウリザ)」は、無料トライアルも行っています。研修動画の配信に向けて、セキュリティが充実した動画配信プラットフォームをお探しの方は、ぜひ導入をご検討ください。
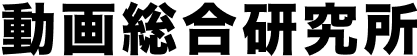
この記事の監修者: 動画総合研究所 編集部
動画総合研究所は、動画配信技術の活用による企業のDX推進をお手伝いするためのメディアです。
動画の収益化・動画制作・ライブ配信・セキュリティ・著作権など、動画配信に関わるのさまざまなコンテンツを提供いたします。














