2025.05.27
動画配信におけるセキュリティリスクと対策の重要性
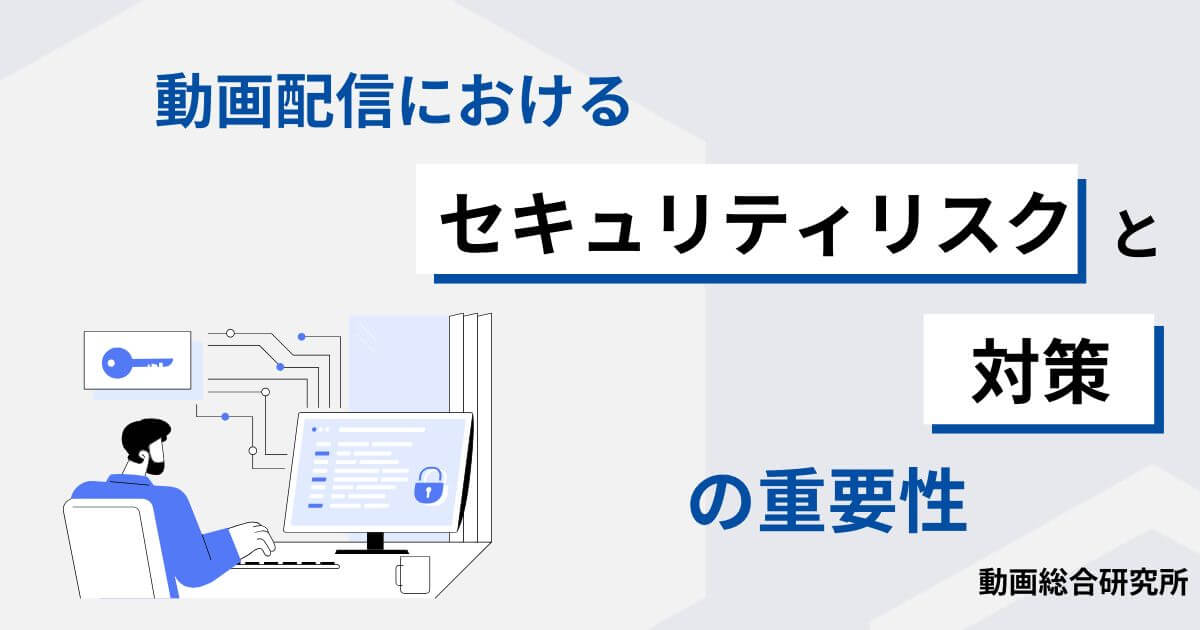
ビジネス活動の一環として動画配信に取り組む企業が増えていますが、セキュリティリスクについて十分に意識できているでしょうか。
安全に動画を運用するためには、どのようなリスクが潜んでいるのかを把握し、事前に必要な対策を講じておくことが欠かせません。
対策が不十分なままでは、大きな問題に発展するおそれがあります。
この記事では、動画配信に関連する主なセキュリティリスクと対策について解説します。
動画配信で起こり得るセキュリティリスク

動画配信は、情報発信の手段として優れているため、様々な場面で広く活用されています。
ただ、インターネットを通じて公開・視聴される仕組みである以上、セキュリティ上のリスクが常につきまといます。
ここでは、動画配信において実際に起こり得る代表的なリスクを紹介します。
不正アクセス・アカウント乗っ取り
動画配信の運用では、アカウントへの不正ログインによる被害が起こる可能性があります。
IDやパスワードが流出すると、第三者によってアカウントに侵入され、機密情報の漏洩やコンテンツの不正利用につながるおそれがあります。
動画配信プラットフォームなどでは、乗っ取られたアカウントから支払い情報が閲覧されたり、有料動画が無断で視聴されたりするケースも想定されます。
コンテンツの不正コピー・違法配信
インターネット上では、画面録画ソフトやキャプチャ機能によって動画がコピーされ、SNSや動画投稿サイトに無断で公開されるケースが後を絶ちません。
特にノウハウ系の解説動画や講義形式のコンテンツは、情報の利用価値が高く、不正コピーの対象になりやすい傾向があります。
違法配信されることにより、正規の購入者との信頼関係が損なわれるおそれがあるほか、収益機会の損失にもつながります。
個人情報の流出
動画配信を通じて顧客情報を取得する場合、氏名やメールアドレスなどの個人情報を扱うことになります。
こうした情報は、サーバーの脆弱性や設定ミス、外部からの攻撃によって漏洩するリスクがあり、常に慎重な取り扱いが求められます。
さらに、動画視聴時には、アクセスログや視聴履歴といった行動データも記録されます。
これらは一見無害に見えるものの、閲覧傾向や利用状況を通じて個人を特定しやすくなるため、適切な管理が欠かせません。
DDoS攻撃
DDoS(分散型サービス妨害)攻撃とは、大量のアクセスを複数の端末から同時に送りつけ、サーバーに過負荷をかけることでサービスを停止させるサイバー攻撃です。
特に、ライブ配信やセミナーの開催などアクセスが集中する時間帯は標的にされやすく、被害が発生した場合の影響も大きくなります。
管理画面やAPIにも接続できなくなると、配信の中止や緊急対応に追われることになります。
セキュリティ対策を怠ることで発生する問題

ここでは、セキュリティ対策を怠ったことで実際に起こり得る問題について解説します。
不正利用による収益の損失
有料動画が無断でコピー・共有されると、正規に購入されるべき視聴が低減し、本来得られるはずの収益が削られてしまいます。
特に、アカウントの不正共有や外部サイトへの違法アップロードが長期間にわたり放置されると、購入を検討していた層が離脱し、収益モデルそのものに悪影響が及びます。
不正利用は一時的な被害にとどまらず、継続的な売上減少の要因となりえます。
ブランドイメージ低下による顧客離れ
情報漏洩や不正アクセスが発生すると、セキュリティ対策に不備がある組織として見なされ、信頼を損なうおそれがあります。
特に、顧客情報や業務データが関係する場合は、社会的な注目も高まるため要注意です。
事態の深刻度によっては、社内体制の見直しや外部監査の受け入れといった対応を迫られることもあります。
一度失った信頼は短期間では回復せず、再発防止策を講じても顧客離れが続いてしまいます。
法的リスク
個人情報の漏洩や著作権の侵害が発生すると、状況によっては法的な責任を問われることがあります。
例えば、適切な管理を怠った結果として個人情報が流出した場合、個人情報保護法に違反するおそれがあります。
また、不正にコピーされた動画が第三者によって無断で公開され、その背景に著作権の管理不備があると判断されれば、著作権者であっても責任を問われる可能性があります。
こうした問題が発生すれば、訴訟対応や再発防止策の策定、関係先への説明対応などに追われることになり、時間的・金銭的な負担は避けられません。
動画配信を継続的にビジネスとして成立させるためには、法的リスクを見据えた対策が不可欠です。
業務への影響
DDoS攻撃や不正侵入によって動画が視聴できない状態が続くと、利用者からの問い合わせが急増します。
その結果、顧客対応に追われ通常業務が滞ってしまいます。
社内の混乱が長引けば、ワークフロー全体が乱れ、計画していた業務の進行にも支障が出るおそれがあります。
外部顧客や関係先を巻き込む配信の場合は、信頼の低下や対応の遅れによる損失にもつながるため、注意が必要です。
再発を防ぐためには、教育体制の見直しやマニュアルの改訂、監視体制の強化など、継続的な改善が欠かせません。
情報共有の仕組みや復旧手順の整備も含めて、社内リソースの再投入が必要になるケースもあります。
動画配信におけるセキュリティ対策の基本

動画配信におけるリスクに備えるためには、動画配信に適した技術的対策を講じることが重要です。
ここでは代表的なセキュリティ対策を6つ取り上げ、それぞれの特徴と導入のポイントを解説します。
DRM (デジタル著作権管理)
DRM(Digital Rights Management)は、動画コンテンツを暗号化し、再生時にライセンス認証を行うことで、正規の視聴者だけにコンテンツを提供する仕組みです。
AppleのFairPlayやGoogleのWidevineなどが代表的な技術として知られており、多くのブラウザで標準的にサポートされています。
DRMによって、配信データの複製や保存を制限できるため、不正ダウンロードの防止に高い効果があります。
特に、有料動画や外部に漏らせない研修資料など、コンテンツの管理が厳しく求められる場面では必須の対策といえるでしょう。
動画配信プラットフォームがDRMに対応しているかどうかは、セキュリティ意識の高い運用がなされているかを判断する指標になります。
再生ドメイン制限
再生ドメイン制限は、動画の埋め込み先を特定のドメインに限定し、意図しないページでの再生を防ぐ設定です。
たとえ動画のURLが外部に出回ったとしても、指定したWebページ以外では再生されないため、第三者による不正利用を抑制します。
企業内ポータルや会員向けサービスなど、視聴環境を制御したいケースに向いており、無断転載の対策としても有効です。
IPアドレス制限
IPアドレス制限は、あらかじめ指定したIPアドレスやIPレンジに絞ってアクセスを許可する仕組みです。
社内ネットワークや特定の拠点に限定して視聴できるようにすることで、アクセス元を明確に管理できます。
例えば、社内研修用の動画を社外から再生できないようにしたり、契約企業のIPアドレスに限定して顧客専用コンテンツとして提供したりといった運用が可能です。
意図しない拡散や不正視聴を防ぐために有効な対策です。
時限付きトークン認証
時限付きトークン認証は、有効期限付きの一時的な認証情報(トークン)を発行し、そのトークンを持つユーザーだけに動画の視聴を許可する仕組みです。
動画URLに期限を設定することで、不正利用を防げます。
例えば、視聴ページのリンクに1時間の有効期限を設ければ、URLが拡散された場合でも指定時間を過ぎると無効になり、アクセスできなくなります。
さらにログイン情報と連携させることで、ユーザーごとに視聴制限をする運用も可能です。
アカウント単位での管理と組み合わせるなど、細かな制御が行えます。
HLS暗号化
HLS(HTTP Live Streaming)は、動画を複数のセグメントに分割して順次配信する方式です。
通信経路に暗号化を施すことで、盗聴や中間者攻撃への対策となり、視聴中のデータを第三者に読み取られるリスクを抑制できます。
暗号化されたHLS動画は、復号鍵にアクセスできる再生環境でなければ視聴できないため、配信全体のセキュリティを高める手段として有効です。
外部漏洩を避けたい教育用コンテンツや、アクセスを制限した有料配信などにも幅広く利用されています。
ユーザー認証
視聴者ごとにアカウントを発行し、ログイン後に動画を再生させる方式は、動画配信における基本的なセキュリティ対策です。
有料コンテンツや社外秘の社内動画など、限られた対象にのみ配信したい場合に適しています。
ユーザー単位で視聴履歴を記録できるため、再生回数や利用端末の制限といった細かな管理にも対応しやすくなります。
さらにアカウント情報とアクセスログを紐づけることで、不正利用の発見や対象ユーザーの特定がしやすくなり、トラブル発生時の対応スピードも上がります。
セキュリティ対策に強い動画配信サービス「ULIZA」

動画配信では、コンテンツの不正利用や視聴者情報の漏洩といったリスクに備え、堅実なセキュリティ対策が求められます。
「ULIZA」は、こうしたニーズに応えるための多彩な機能を備えた動画配信プラットフォームとして、多くの企業や教育機関に導入されています。
ULIZAでは、一つのIDを複数人で同時に利用する行為を防ぐための視聴制限や、IDとパスワードによる基本認証の設定が可能です。
さらにアクセス元を特定のIPアドレスやドメインに絞ることで、外部からの不正な接続を遮断できます。
リンクの無断共有を防ぎたい場合には、ワンタイムURLを使います。
期限を過ぎると自動的に無効になるため、想定外の視聴を防止できます。
加えて、管理者アカウントには2段階認証やIPアドレス制限を適用でき、システム運用面の安全性も確保されています。
ULIZAは、HuluやTVerといった大手サービスの技術支援を担ってきた実績があります。
医療系セミナーや社内研修のように、高い秘匿性が求められる場面でも採用されており、セキュリティに強い配信サービスとして高い評価を受けています。
このようにセキュリティ対策と運用実績を兼ね備えたULIZAは、動画配信の信頼性を高めたい組織にとって、導入価値のあるサービスです。
まとめ
動画配信は、情報発信や収益化の手段として、ビジネス・教育・マーケティングなど幅広い場面で導入が進んでいます。
ただし、アカウントの不正利用やコンテンツの無断転載、個人情報の漏洩といったセキュリティリスクも無視できません。
トラブルが発生すれば、信頼の低下や売上減少といった実害に直結するおそれがあります。
こうしたリスクに対応するには、単一の施策ではなく、複数の技術的対策を組み合わせて導入することが重要です。
例えば、DRMや再生ドメイン制限、トークン認証などを組み合わせれば、不正アクセスや情報漏洩のリスクを大幅に抑えられます。
動画配信の安全性を担保したいときは、セキュリティ機能が充実した動画配信サービスの導入をおすすめします。
安全に動画配信を開始して、ビジネスにつなげていきましょう。
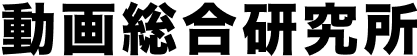
この記事の監修者: 動画総合研究所 編集部
動画総合研究所は、動画配信技術の活用による企業のDX推進をお手伝いするためのメディアです。
動画の収益化・動画制作・ライブ配信・セキュリティ・著作権など、動画配信に関わるのさまざまなコンテンツを提供いたします。














