2025.09.22
動画エンコードとは?仕組み・種類・設定のコツまで初心者向けに徹底解説

動画配信や編集を行う際、必ず耳にする言葉が「動画エンコード」です。
とはいえ、実際にどんな処理が行われているのか、なぜ必要なのかを正しく理解していない方も多いのではないでしょうか。
動画エンコードとは、元の動画ファイルを圧縮し、配信や保存に適した形式へ変換するための重要な技術です。
本記事では、動画エンコードの基本的な仕組みから代表的な種類、設定時に押さえておきたいポイントまで、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。
動画エンコードの基礎知識

動画配信や保存において、エンコードは欠かせない技術の一つです。
動画の容量を小さくしたり、再生機器に合わせて形式を変換したりする際に必要になります。
エンコードを行うことで、ファイルサイズの削減や高速なデータ転送が可能になり、動画配信サービスでもスムーズな再生体験を実現できます。
エンコードとは何か
動画エンコードとは、映像と音声のデータを一定の規則に基づいて変換する処理のことです。
より具体的に説明すると、動画の容量を小さく圧縮したり、再生機器に対応した形式に変換したりする作業になります。
動画は連続する静止画で構成されており、パラパラ漫画のように再生されるのが特徴です。
膨大な情報を持ったままでは、編集・保存・再生をしようとした時にデータ量が大きくなりすぎて、まともに動画データを取り扱うことが難しくなります。
エンコード技術により、コンテナと呼ばれる収納ケースに映像と音声をぎゅっと詰め込んで効率よく管理できるようになります。
エンコードとデコードの違い
エンコードとデコードは、動画処理において対となる存在です。
エンコードは、元の動画データを圧縮・変換して配信や保存に向いた形式にする処理です。
一方でデコードは、エンコードされた動画データを元に戻して再生可能な状態にする処理になります。
例えば、YouTubeに動画をアップロードする際はエンコードが行われ、視聴者が動画を再生する時にはデコードが行われます。
エンコードでは大容量の動画ファイルを効率よく圧縮し、デコードでは圧縮されたデータを解凍して映像と音声を復元するのが基本的な流れです。
つまり、エンコードは「まとめる」作業、デコードは「ほどく」作業となります。
どちらも動画配信において欠かせない技術で、視聴者が快適に動画を楽しむために重要な役割を担っています。
コーデックとは
コーデックとは、動画のエンコードとデコードを実行するソフトウェアやアルゴリズムのことです。
「Coder-Decoder」の略称で、動画データの圧縮と展開を担当する重要な役割を担っています。
代表的なコーデックは、汎用性が高く多くの機器で再生可能なH.264や、より高効率な圧縮を実現するH.265(HEVC)です。
また、古くから使われているMPEG-2や、Googleが開発したVP9なども広く利用されています。
コーデックによって圧縮効率や画質、処理速度が大きく異なるため、用途に応じて選択することが重要です。
用途に応じたコーデックを選ぶことで、ファイルサイズと画質のバランスを両立できます。
動画エンコードの仕組み
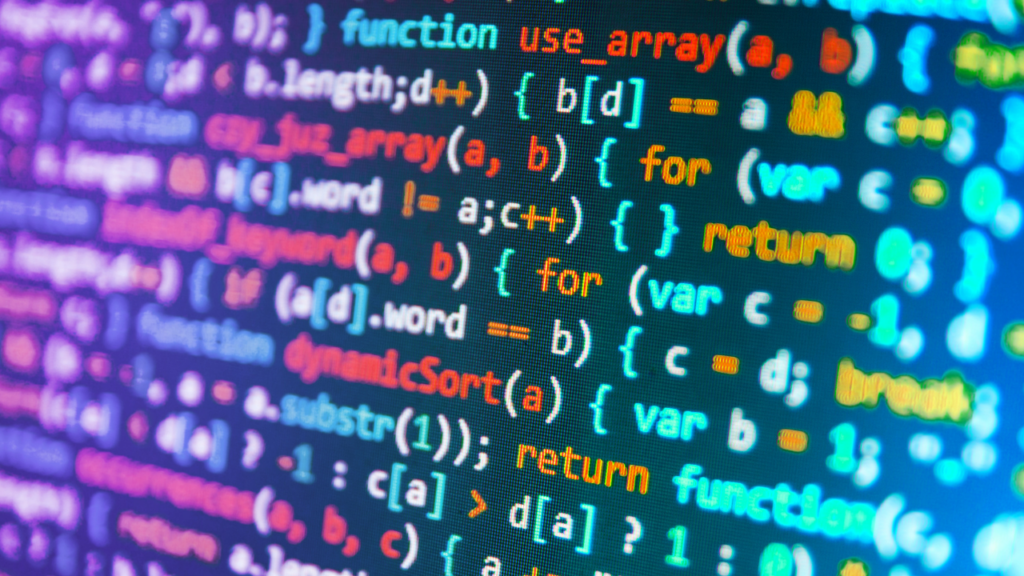
動画エンコードの仕組みを理解すると、映像がどのような技術的な処理を経て最終的な形式に変換されるのかが把握できます。
動画は大量のデータで構成されているため、そのままでは容量が大きすぎて配信や保存に向きません。
エンコードでは、フレーム内予測やフレーム間予測といった圧縮技術を駆使して、画質を維持しながらファイルサイズを削減していきます。
ここからはエンコードの仕組みを詳しく見ていきましょう。
圧縮アルゴリズムの仕組み
動画の圧縮アルゴリズムは、膨大なデータ量を効率的に削減する技術で、主な仕組みとしてフレーム内予測とフレーム間予測の2つの手法があります。
フレーム内予測は、1枚の画像内で似た色の部分をまとめて処理してデータ量を圧縮していく仕組みです。
例えば、類似した色調をまとめて処理することで、視覚的な違和感を抑えつつデータ量を削減できます。
一方、フレーム間予測は連続する画像の動きに注目した圧縮方法です。
パラパラ漫画のように、前後のフレームで変化がない部分は「同じ」という情報だけを記録し、動きがある部分のみ差分データを保存する仕組みです。
圧縮アルゴリズムにより、画質を保ちながら大幅なファイルサイズの削減を実現しています。
ビットレートの考え方
ビットレートとは、動画1秒間に使用されるデータ量を表す重要な指標です。
単位は「bps(bits per second)」で表され、数値が高いほど画質が向上しますが、同時にファイルサイズも大きくなります。
ビットレートの設定は、映像品質とファイル容量のバランスを決める重要なポイントです。
高いビットレートを設定すると細かな映像の変化まで記録できるため、美しい画質を実現できます。
しかし、ファイルサイズが大きくなりすぎると、インターネット配信時の読み込み速度が遅くなったり、ストレージ容量を圧迫したりする問題が発生するでしょう。
そのため、配信プラットフォームに合わせて調整するのが重要になります。
フレームレートの影響
フレームレートとは、1秒間に表示される静止画の枚数を表す単位で、「fps(framespersecond)」で表します。
動画は連続した静止画を高速で切り替えて動いているように見せており、フレームレートが高いほど滑らかな映像になります。
一般的な動画では30fpsが使われる場合が多く、ゲーム実況やスポーツ映像では60fpsが選ばれることが多いでしょう。
フレームレートが低すぎると映像が滑らかに見えず、高すぎるとファイルサイズが大きくなってしまいます。
エンコード時には、編集時のフレームレートと同じ値を設定するのが重要で、例えば30fpsで編集した動画を60fpsでエンコードすると、映像が不自然になってしまうため注意が必要です。
エンコード形式の種類と特徴

動画エンコードにはさまざまな形式が存在し、用途や目的に応じて選択する必要があります。
主要なエンコード形式には、MP4、AVI、MOV、FLV、MKVなどがあり、それぞれ異なる特徴を持っています。
配信プラットフォームや視聴環境に合わせた形式選択により、視聴者にとって快適な動画体験を実現できるでしょう。
動画エンコード形式を理解すると、目的に応じた設定が可能になります。
動画エンコードの種類と特徴について詳しく見ていきましょう。
H.264/H.265の特徴
H.264は優れた圧縮効率と高い互換性が特徴で、多くの再生機器やプラットフォームに対応し、Web配信からテレビ放送まで幅広く利用されています。
一方、H.265(HEVC)はH.264の後継として開発されたコーデックで、H.264と比較して約50%のビットレート削減を実現しながら、同等の画質を維持できる圧縮技術です。
特に4K動画配信において威力を発揮し、限られた帯域でも高品質な映像配信が可能な半面、処理負荷が高く、古い機器では再生できない場合があるため注意が必要です。
VP9・AV1など新しい規格
VP9はGoogleが開発したオープンソースのコーデックで、H.264と比較して約40%のデータ削減を実現し、ライセンス料が不要なため多くのWebサービスで採用されています。
AV1は、VP9の後継として業界団体が開発したコーデックで、H.265と同等以上の圧縮効率を持ちながら、ライセンス料不要なのが特徴です。
ストリーミング配信において高い効果を発揮し、帯域制限のある環境でも高品質な動画配信が可能です。
ただし、エンコード処理時間が長いため、実用化には課題も残されています。
音声コーデックとの関係
エンコードは映像だけでなく、音声コーデックの選択も重要です。
代表的な音声コーデックには、高い互換性を持つAACや、高品質な圧縮を実現するAC-3(DolbyDigital)があります。
AACは幅広い機器で再生可能で、Web配信やモバイル視聴に適しており、AC-3は映画やテレビ放送で使われる場合が多く、5.1chサラウンドなどの多チャンネル音声に対応しています。
音声コーデックの選択は、配信環境や視聴者の再生機器に合わせるのが大切です。
エンコード設定のポイント

動画エンコードは、配信環境や視聴者のニーズに合わせた設定が重要です。
解像度、フレームレート、ビットレートなどの基本パラメータを調整すると、画質とファイルサイズのバランスが取れます。
配信プラットフォームが対応している形式や設定を事前に確認し、元データの保管やエンコード時間の確保といった作業上の注意点も押さえておくことで、トラブルを避けながら効率的なエンコードが実現できます。
画質と容量のバランス
動画エンコードにおいて、画質と容量のバランスが重要です。
高画質を追求するとファイルサイズが大きくなって読み込み時間が増え、通信の影響も発生します。
一方容量を優先しすぎると画質が劣化し、視聴者の満足度が低下するでしょう。
そこで配信プラットフォームや視聴環境に応じたビットレート設定が大切で、例えば、モバイル視聴が多い場合は軽量化を重視し、大画面での視聴を想定する場合は高画質を優先するといった調整が必要です。
このように視聴者のインターネット環境を考慮した設定を行いましょう。
デバイス対応を考える
現代の動画配信はマルチデバイス対応が必要で、さまざまな端末での再生を考慮する必要があります。
デバイスごとに画面サイズや処理性能、対応コーデックが異なるため、それぞれエンコード設定を行いましょう。
例えば、PC向けにはフルHD(1920×1080)、スマートフォン向けにはHD(1280×720)といった設定を行い、古い端末でも再生できるよう互換性の高いH.264コーデックを選択するのがおすすめです。
正しいマルチデバイス対応により、すべての視聴者が快適に動画を楽しめるでしょう。
テスト配信の重要性
エンコード設定において、テスト配信は本格運用前のトラブル回避に欠かせない工程です。
実際の配信環境で再生確認を行うことで、画質の劣化や音声の遅延、再生エラーなどの問題を事前に発見できます。
テスト時には複数のデバイスや通信環境で確認しましょう。
PC、スマートフォン、タブレットそれぞれでの再生状況や、Wi-Fi・モバイル回線での読み込み速度をチェックし、配信プラットフォームの適合性や、想定視聴者数での負荷テストも実施します。
テスト結果に基づいてエンコード設定を調整すると、安定した動画配信を実現できます。
配信プラットフォームとULIZAの活用

安定した配信を実現するためには、プラットフォームの選定も重要です。
エンコード機能だけでなく、視聴者の回線状況に応じた画質で配信できるマルチビットレート機能を持つプラットフォームが求められます。
ULIZAのような専門的な動画配信プラットフォームでは、自動エンコード機能により手間を大幅に削減でき、CDN連携による高速配信やセキュリティ対策、視聴者管理機能など、企業の動画配信に必要な機能が統合されています。
配信に適したプラットフォーム選び
動画配信プラットフォーム選択において、安定性・セキュリティ・サポート体制は重要な評価基準です。
安定性の面では、CDN(コンテンツ配信ネットワーク)による高速配信やサーバの冗長化による可用性の高さが求められ、特に多数の視聴者が同時アクセスする場合でも、動画が途切れず配信できる能力が必要になります。
セキュリティ面では、DRM(デジタル著作権管理)機能や視聴制限機能によりコンテンツの不正利用を防ぐ仕組みが重要で、企業の機密情報を扱う場合は、暗号化通信やアクセス権限管理が欠かせません。
サポート体制については、技術的な問題が発生した際の対応や、エンコード設定に関する専門的なアドバイスがあると安心でき、24時間体制のサポートや、導入時の設定支援なども選択基準となります。
ULIZAの魅力と活用例
ULIZAは、企業向けに設計された動画配信プラットフォームで、高品質なエンコードと安定した配信環境を提供しています。
自動エンコード機能により、専門知識がなくても画質や容量の調整がスムーズに行え、マルチビットレート配信にも対応しています。
これにより視聴者の通信環境に応じて、最適な画質での再生が可能です。
セキュリティ面では、DRM機能や視聴制限機能を備えており、社内研修や限定配信などにも安心して活用できます。
ULIZAは製品紹介動画や教育コンテンツ、ウェビナーなど、さまざまな用途で豊富な実績があり、CDN連携による高速配信や導入支援も充実しています。
動画配信を検討中の企業にとって、導入から運用までしっかりサポートしてくれる頼れる選択肢といえるでしょう。
まとめ
動画エンコードは、圧縮や変換の技術を使って、配信に適した形式へと整える重要な工程です。
コーデックの選択や、解像度・ビットレートの調整によって、視聴者にとって快適な映像体験を提供できます。
一方で、エンコードには一定の専門知識と作業時間が求められるため、企業で活用するにはハードルを感じる場面もあるかもしれません。
その点、ULIZAなら自動エンコード機能によって、煩雑な設定を行わずにスムーズな動画配信を実現できます。
動画配信に挑戦したい方はぜひ導入を検討してみてください。
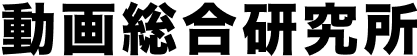
この記事の監修者: 動画総合研究所 編集部
動画総合研究所は、動画配信技術の活用による企業のDX推進をお手伝いするためのメディアです。
動画の収益化・動画制作・ライブ配信・セキュリティ・著作権など、動画配信に関わるのさまざまなコンテンツを提供いたします。





-45.jpg)








