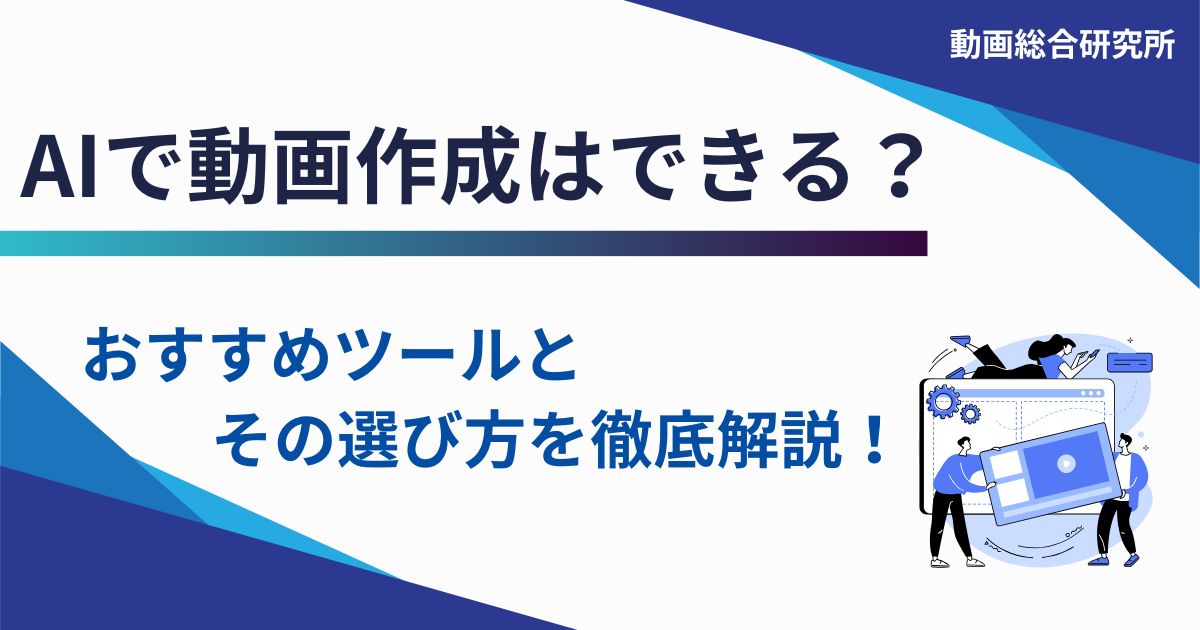2025.10.28
オンデマンド配信にかかる費用とは?料金相場とコスト削減のコツを解説

動画コンテンツをいつでも視聴できるオンデマンド配信は、企業や教育機関での導入が加速しています。
導入を検討する企業担当者にとって、特に懸念されるのが「費用面の不安」です。
初期費用や月額利用料はいくらかかるのか、予算内で運用できるのか、といった疑問を抱える人も多いでしょう。
本記事では、オンデマンド配信にかかる費用の詳しい内訳や、コストを効率的に抑えるためのポイントについて分かりやすく解説します。
オンデマンド配信にかかる基本費用の内訳

オンデマンド配信に必要な費用は、複数の要因で構成されています。
具体的には、初期費用、月額利用料、オプション機能の追加費用などが主な内訳となるでしょう。
また、配信する動画の量や利用人数によって料金は大きく変動するため、事前に詳しい内訳を把握しておくことが重要です。
ここでは、基本的な費用の内訳と概要について詳しく解説します。
システム導入・初期構築費
システム導入・初期構築費は、配信プラットフォームの基盤を整えるために必要な一時的な費用です。
クラウド型では10万〜30万円程度が相場となっており、比較的手軽に始められる価格帯といえるでしょう。
一方で、セキュリティを重視する企業が選ぶオンプレミス型では、300万〜1,000万円と高額になります。
クラウド型が人気を集める理由は、初期投資を抑えられるのに加え、システムを自社で保有する必要がなく、運用に関するリソース確保も不要だからです。
初期構築費には、配信システムの設定作業やユーザー環境の構築、基本機能の実装、セキュリティ設定などが含まれており、導入方式によって大きく金額が変わる点を理解しておきましょう。
動画コンテンツ制作費
動画コンテンツ制作費は、撮影・編集・字幕作成など、動画の制作工程で発生する費用です。
動画制作・映像制作1本あたりの費用相場はおよそ30万円から200万円程度が一般的となっており、内容や尺によって大きく変わります。
撮影は動画制作のなかで費用がかかりやすい工程で、10万〜100万円程度が相場になります。
撮影費には機材費やスタッフの人件費、ロケーション費用などが含まれるため、規模によって幅が生まれるのが特徴です。
また、実写動画の編集費用は10万円から50万円程度、アニメーション動画の編集費用は20万円から100万円程度となっており、演出や特殊効果の有無で大きく変動することを把握しておきましょう。
配信システムの月額利用料
配信システムの月額利用料は、クラウド型配信サービスを利用する場合の継続的な運用費用です。
クラウド型動画配信システムでは、ベンダーが用意したインターネットを利用して動画を配信するため、月額利用料がかかるのが特徴です。
具体的な料金は10万〜20万円/月が相場となっています。
利用人数(ライセンス数)や同時ログイン人数、ストレージ容量(動画を保存できる容量)、月間転送量(1か月で動画を配信できる量)によって料金が変動するシステムが一般的です。
規模が小さければ月額5万円程度から始められるサービスもありますが、企業での本格運用を考えると上記の金額帯を想定しておくと安心でしょう。
利用規模によって変わる費用の目安

オンデマンド配信の費用は、配信対象の人数や配信期間などの条件によっても変動します。
利用人数が多いほど、帯域幅やデータストレージの需要が増え、それに伴って費用もかさむ仕組みになっています。
また、コンテンツのアップロードや再生にかかるデータ転送料金も重要な要因です。
企業の規模や利用目的に応じて、月額数万円から数十万円まで幅広い料金設定があるため、導入前に想定される利用状況を詳しく整理することが重要です。
視聴人数が多い場合の費用感
視聴人数が多い場合の費用感は、大規模な社内研修や会員向け配信など、数百人から数千人規模での配信を想定した料金体系になります。
視聴者数が増えるほど、同時接続に対応するための帯域幅やサーバー負荷が高まるため、月額利用料も比例して上昇する傾向があります。
一般的には月額15万円〜30万円程度の予算を見込む必要があり、さらに大規模になると50万円を超えるケースも珍しくありません。
また、ピーク時の同時接続数や月間の総視聴時間によって追加料金が発生する場合もあるため、事前に利用パターンを想定してプランを選択するのが重要です。
特に全社員向けの必須研修や大型イベントのライブ配信などでは、アクセス集中に備えた上位プランの検討が必要になるでしょう。
コンテンツ数と配信時間による影響
コンテンツ数と配信時間による影響は、1本あたりの動画時間や動画の本数によって費用が段階的に変わる仕組みです。
動画配信システムでは、ストレージ容量と月間転送量の2つの要因で料金が決まります。
長時間の動画や本数が多い場合、データ保存に必要なストレージ容量が増加し、ストレージ容量に応じて月額利用料も上昇します。
また、視聴回数が多い人気コンテンツは、月間のデータ転送量を押し上げる要因となり、上限を超えた場合は追加料金が発生する場合もあるでしょう。
例えば、30分の研修動画を100本配信する場合と、5分のマニュアル動画を500本配信する場合では総容量が異なるため、料金体系も変わってきます。
効率的な運用には、コンテンツの特性を踏まえたプラン選択が欠かせません。
保存期間・アーカイブ期間と料金の関係
保存期間・アーカイブ期間と料金の関係は、動画を長期間保管・配信する場合に発生するストレージ費用に直結します。
多くの動画配信システムでは、保存容量に応じた段階的な料金設定を採用しており、アーカイブ期間が長いほど必要な容量も増加します。
例えば、過去3年分の研修動画を保管する場合、新しいコンテンツを追加するたびに総容量が蓄積され、上位プランへの変更が必要になる可能性もあるでしょう。
そこで、自動削除設定や安価なストレージに移行する機能を利用すると、コストを抑制できる場合があります。
特に法的保管義務がある業界では、将来的な容量増加を見込んだプラン選択が重要になります。
費用を抑えるための工夫と注意点

限られた予算内でオンデマンド配信を行うためには、さまざまな工夫が求められます。
費用を抑えながら効果的な配信システムを構築するには、初期投資と運用コストの両面でコスト削減を検討するのが重要です。
また、必要な機能を見極めて段階的に導入していくことで、無駄な支出を避けながら理想的なシステムを実現できるでしょう。
ここでは、予算を抑えつつ品質の高い配信環境を整えるための具体的な方法について解説します。
外注と内製のバランスを見極める
外注と内製のバランスを見極めるのは、動画制作費用を大幅に削減できる重要なポイントです。
すべてを外注するのではなく、社内で対応可能な部分を見極めて分担すると、コストを効率的に抑制できます。
例えば、企画や構成は社内で担当し、撮影と編集のみを制作会社に依頼する方法なども効果的でしょう。
また、簡単な動画編集は社内スタッフが習得し、高度な技術が必要な部分のみプロに任せれば、継続的なコスト削減も実現できます。
特に研修動画やマニュアル動画など、定期的に制作が必要なコンテンツについては、内製化のメリットが大きくなります。
一方、品質を重視する企業向けプロモーション動画などは、専門技術を持つ制作会社への依頼を検討しましょう。
配信期間や回数を限定して最適化
配信期間や回数を限定して最適化すると、オンデマンド配信の運用コストを効果的に削減できます。
配信状況に合った公開期間を設定すれば、ストレージ容量の圧迫を防ぎ、長期保存による費用増加を回避できるでしょう。
例えば、研修動画は3ヶ月間のみ配信、セミナー録画は1年間で自動削除するなど、コンテンツごとに配信期間を設定することが大切です。
また、同時視聴数やアクセス制限を設けると、サーバー負荷を軽減し、上位プランへの変更を防げます。
特に社内向けコンテンツでは、部署単位でのアクセス権限管理を利用すれば、必要最小限のリソースでの運用が可能になります。
オンデマンド配信とライブ配信の費用比較

オンデマンド配信とライブ配信では、発生する費用の構造が異なります。
オンデマンド配信は事前に録画された動画を視聴者が好きな時に視聴できる仕組みで、ライブ配信はリアルタイムで配信される動画を同時刻に視聴する仕組みです。
それぞれの特性によって必要な設備や技術要件が変わるため、コスト面でも大きな違いが生まれます。
ここでは、両者の費用構造や導入時のメリット・デメリットを比較してみましょう。
運用にかかる人件費・手間の違い
運用にかかる人件費と手間は、オンデマンド配信とライブ配信で大きく異なります。
オンデマンド配信は、一度制作すれば継続的な運用コストが抑えられるのが特徴で、制作後は視聴者が自由にアクセスできるため、リアルタイムでの対応は基本的に不要です。
一方、ライブ配信では配信時に専任スタッフの常駐が必要になり、機材操作や音響調整、視聴者からの質問対応など、多くの人的リソースを投入する必要があります。
また、ライブ配信はトラブルが発生した際に即座の対応が求められるため、技術的な知識を持つスタッフの確保も重要になります。
長期的な運用を考えた場合、オンデマンド配信の方が人件費を抑えられる傾向があり、特に定期的な研修には適しているといえるでしょう。
安定性・再生環境によるコスト差
安定性・再生環境によるコスト差は、配信方式の特性によって生まれる重要な費用要因です。
ライブ配信では、配信中のトラブルが即座に視聴体験に影響するため、高性能なサーバーや冗長化システムが必要になり、インフラコストが高額になる傾向があります。
また、録画保存機能を利用する場合は、追加のストレージ費用やエンコーディング処理費用が発生するケースが多いでしょう。
一方、オンデマンド配信は事前に品質チェックを行えるため、配信時の技術的トラブルリスクが低く、比較的安価なインフラでも安定した配信が可能です。
さらに視聴者のアクセスが分散されるため、運用コストを抑制できる利点もあります。
法人向けオンデマンド配信サービスの選び方

実際にオンデマンド配信を始めるにあたっては、信頼できる配信プラットフォームの選定がポイントとなります。
企業向けの配信サービスは多数存在し、それぞれ異なる機能や料金体系を持っているため、自社のニーズに合ったプラットフォームを見極めるのが大切です。
サービスの安定性やセキュリティ対策、サポート体制なども含めて総合的に判断する必要があるでしょう。
ここでは、法人向けオンデマンド配信サービスの選び方について詳しく解説します。
コストと機能のバランスを見極める
コストと機能のバランスを見極めるのは、法人向けオンデマンド配信サービス選択における最重要ポイントです。
価格帯だけでなく、視聴分析やセキュリティ機能などの充実度も確認する必要があります。
安価なサービスでも基本的な配信機能は利用できますが、企業利用ではIP制限や暗号化配信、詳細な視聴ログ分析といった高度な機能が必要になるケースが多いでしょう。
また、ユーザー管理機能やアクセス権限設定の柔軟性も、社内研修や顧客向けコンテンツ配信では重要なポイントになります。
月額利用料と必要機能を比較し、長期的な運用コストと投資対効果を総合的に評価すれば、自社に合ったサービスを選択できるでしょう。
ULIZAならコストも安心、高機能で導入しやすい
法人向け動画配信サービス「ULIZA」は、コストパフォーマンスが良く、高機能で導入しやすいオンデマンド配信プラットフォームとして注目されています。
500を超える企業が導入しており、HuluやTVerなどの大手配信サービスを技術面でサポートしてきた実績に裏付けされた、安定性の高い配信環境が魅力です。
エントリープランのULIZA miniでも、オンデマンド配信とライブ配信の両方に対応しており、月額1万円から利用できる手頃な料金設定となっています。
また国内開発サービスならではの丁寧なサポート体制も特徴で、導入から運用まで経験豊富なスタッフがしっかりとサポートしてくれます。
配信の安定性、多彩な機能、手厚いサポートの3つの強みにより、法人のビジネス動画配信がワンストップで支援されます。
まとめ
オンデマンド配信は、初期費用や月額利用料、動画制作費など複数の要素が関わるため、費用構造が複雑になりがちです。
しかし、目的に合った活用方法を選べば、無駄な支出を抑えながら、効率的かつ継続的な情報発信が可能になります。
法人での導入を検討する際には、高機能かつサポート体制が整った「ULIZA」などの専用サービスを選択肢に入れるとよいでしょう。
自社の利用目的と予算を明確にし、コストと機能のバランスを見極めることで、投資効果の高い配信環境を実現できます。
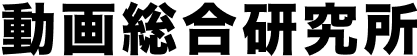
この記事の監修者: 動画総合研究所 編集部
動画総合研究所は、動画配信技術の活用による企業のDX推進をお手伝いするためのメディアです。
動画の収益化・動画制作・ライブ配信・セキュリティ・著作権など、動画配信に関わるのさまざまなコンテンツを提供いたします。